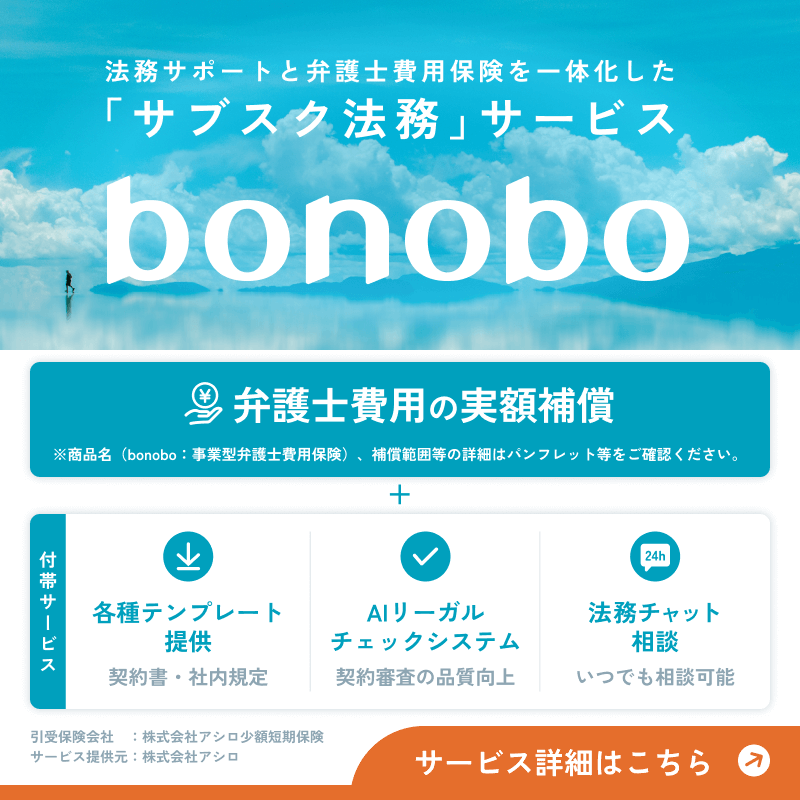残業代の計算方法は、勤務形態によってさまざまです。
ご自身の勤務形態について、残業代計算の正しい考え方を身に着けておきましょう。
実際に残業代計算が必要となった場合には、正確を期して円滑に残業代請求を行うため、お早めに弁護士までご相談ください。
この記事では、労働基準法の割増賃金に関するルールや、勤務形態ごとの残業代計算の考え方を解説します。
残業代が発生する場合とは?割増率と併せて解説
労働基準法上、いわゆる「残業代」が発生するのは、労働者が「法定内残業」「法定外残業(時間外労働)」「深夜労働」「休日労働」のいずれかを行った場合です。
このうち、「法定外残業(時間外労働)」「深夜労働」「休日労働」の3つについては、通常の賃金に対して一定以上の割増率をかけた「割増賃金」を支払う必要があります。
| 残業の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 法定内残業 | 規定なし |
| 法定外残業(時間外労働) | 原則:25%以上 例外:月60時間を超える部分は50%以上(現行法では大企業のみ) |
| 深夜労働 | 25%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
| 時間外労働かつ深夜労働 | 原則:50%以上 例外:時間外労働として月60時間を超える部分は75%以上(現行法では大企業のみ) |
| 深夜労働かつ休日労働 | 60%以上 |
所定労働時間を超えて労働した場合(法定内残業)
「法定内残業」とは、「所定労働時間」を超え、かつ「法定労働時間」を超えないの範囲の労働時間をいいます。
- 所定労働時間:労働契約や就業規則で定められる労働時間
- 法定労働時間:1日当たり8時間、1週当たり40時間(労働基準法32条)
たとえば所定労働時間が7時間の労働日に、9時間労働した場合、1時間分が「法定内残業」に当たります。
法定内残業に対しては、通常の賃金を支払うことが必要です。
法定労働時間を超えて労働した場合(法定外残業)
「法定外残業(時間外労働)」は、法定労働時間を超える労働時間をいいます。
たとえば、ある労働日に10時間労働した場合、2時間分が「法定外残業(時間外労働)」に当たります。
法定外残業(時間外労働)に対しては、原則として、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。
また、1か月当たり60時間を超える法定外残業(時間外労働)が行われた場合、超過分については50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
ただし現行法上、この規定は大企業限定で適用されており、中小企業には2023年4月から適用されることになっています。
午後10時から午前5時までに労働した場合(深夜労働)
「深夜労働」とは、午後10時から午前5時までの労働時間をいいます(労働基準法37条4項)。
深夜労働に対しては、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
なお、「時間外労働かつ深夜労働」または「深夜労働かつ休日労働」という組み合わせも認められており、その場合は割増率が加算されます。
法定休日に労働した場合(休日労働)
「休日労働」とは、法定休日における労働時間をいいます。
法定休日として認められるのは、1週間のうち1日のみです(労働基準法35条1項)。
就業規則などによって、1週間当たり複数の休日が設定されている場合には、以下の要領で法定休日が定まります。
- ①就業規則などで法定休日が指定されている場合には、その指定による
- ②法定休日の指定がない場合は、「日曜~土曜」の中で後に来る曜日が法定休日となる
(例)
土曜・日曜が休日の会社で、法定休日の指定がない場合
→土曜が法定休日
休日労働に対しては、通常の賃金に対して35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
参考:労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令|e-gov法令検索
「深夜労働かつ休日労働」が認められることは、前述のとおりです。
これに対して、「時間外労働かつ休日労働」という重複は認められていません。
残業代の計算方法は?
残業代には基本的な計算式がありますが、実際の計算に当たっては、給与体系や勤務体系によって異なる注意点が存在します。
ご自身の給与体系や勤務形態に応じて、正しい計算方法により残業代を計算してください。
残業代の計算式
残業代の基本的な計算式は、以下のとおりです。
残業代=1時間当たりの基礎賃金×割増率×残業時間数
すでに解説した「法定内残業」「法定外残業」「深夜労働」「休日労働」の各時間数を把握したうえで、所定の割増率をかけて残業代を計算しましょう。
1時間当たりの基礎賃金の求め方
残業代を計算する際にポイントとなるのが、「1時間当たりの基礎賃金」の求め方です。
1時間当たりの基礎賃金の計算式は、以下のとおりです。
1時間当たりの基礎賃金
=(給与計算期間中の総賃金-控除できる手当)÷給与計算期間に対応する所定労働時間
「基礎賃金」には原則として、給与計算期間中に労働者に対して支給された金銭(賃金)が、名目の如何にかかわらずすべて含まれます。
ただし例外的に、以下の手当については、基礎賃金に含まれません(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
したがって、給与計算期間中の総賃金から上記の各手当を控除した金額が「基礎賃金」となります。
この基礎賃金を、給与計算期間の所定労働時間で割れば、「1時間当たりの基礎賃金」が求められます。
残業代の計算例
それでは、さまざまな給与体系について、設例を用いて残業代を実際に計算してみましょう。
月給制の場合の計算例
<設例①>
1か月間の基礎賃金:30万円
1日の所定労働時間:7.5時間
1年間の勤務日数:240日
2021年8月の時間外労働:30時間
2021年8月の残業代は?
月給制の場合、1時間当たりの基礎賃金は、以下の計算式によって求められます。
1か月間の所定労働時間について、1年間の平均をとるのがポイントです。
1時間当たりの基礎賃金(月給制)=1か月間の基礎賃金÷1か月間の平均所定労働時間
したがって、設例①における1時間当たりの基礎賃金は、以下となります。
30万円÷(7.5時間×240日÷12か月)=2000円
最後に、1時間当たりの基礎賃金・割増率・残業時間数を計算式に当てはめれば、残業代の金額は以下のとおりです。
設例①(月給制)の残業代
=2000円×1.25×30時間
=7万5000円
年俸制の場合の計算例
<設例②>
1年間の基礎賃金:750万円
1日の所定労働時間:7.5時間
1年間の勤務日数:250日
2021年8月の時間外労働:35時間
2021年8月の残業代は?
年俸制の場合、1時間当たりの基礎賃金は、以下の計算式によって求められます。
1時間当たりの基礎賃金(年俸制)=1年間の基礎賃金÷1年間の所定労働時間
したがって、設例②における1時間当たりの基礎賃金は、以下となります。
750万円÷(7.5時間×250日)=4000円
したがって、残業代の金額は以下のとおりです。
設例②(年俸制)の残業代
=4000円×1.25×35時間
=17万5000円
日給制の場合の計算例
<設例③>
1日の基礎賃金:1万5000円
1日の所定労働時間:7.5時間
2021年8月の時間外労働:40時間
2021年8月の残業代は?
日給制の場合、1時間当たりの基礎賃金は、以下の計算式によって求められます。
なお、日によって所定労働時間が異なる場合、1週間の平均をとります。
1時間当たりの基礎賃金(日給制)=1日の基礎賃金÷1日の所定労働時間
したがって、設例③における1時間当たりの基礎賃金は、以下になります。
1万5000円÷7.5時間=2000円
したがって、残業代の金額は以下のとおりです。
設例③(日給制)の残業代
=2000円×1.25×30時間
=7万5000円
時給制の場合の計算例
<設例④>
時給:1600円
2021年8月の時間外労働:10時間
2021年8月の残業代は?
日給制の場合、時給がそのまま1時間当たりの基礎賃金となります。
残業代の金額は以下のとおりです。
設例④(時給制)の残業代
=1600円×1.25×10時間
=2万円
歩合給制が併用されている場合、残業代はどのように計算する?
歩合給制における残業代の計算方法は、一般的な給与体系の場合よりも複雑です。
日本の労働法では、完全歩合給制(フルコミッション)は認められていません(労働基準法27条)。
そのため、歩合給制の労働者の賃金には、基本給と歩合給が併存することになります。
歩合給制の労働者の残業代を計算する際には、基本給部分と歩合給部分について、それぞれ異なる計算を行います。
そして最終的に、基本給部分と歩合給部分の残業代を合算することにより、歩合給制の残業代が求められるのです。
固定残業代制の場合も、追加で残業代が発生することがある
労働者に対して、あらかじめ決まった額の残業代を支給する「固定残業代制」を採用する企業も、数多く存在します。
固定残業代制の場合、「定額の残業代さえ支払えば、追加で残業代は発生しない」と考えている方もいらっしゃいますが、これは誤った考え方です。
固定残業代制を導入する場合、使用者は労働者に対して、以下の事項を明示しなければなりません。
- ①固定残業代を除いた基本給の額
- ②固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
- ③固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、割増賃金を追加で支払う旨
上記のとおり、あらかじめ固定残業時間を定める必要があり、固定残業時間を超える残業には追加で割増賃金が発生します。
長時間残業が続いているにもかかわらず、「固定残業代制だから」という理由で追加の残業代が支給されていない場合には、弁護士にご相談ください。
変形労働時間制・フレックスタイム制における残業代の考え方
変形労働時間制とフレックスタイム制では、労働時間がイレギュラーな形で定まるため、残業代計算の考え方も複雑になります。
変形労働時間制の場合
「変形労働時間制」とは、一定期間における1週間の平均労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、各労働日の労働時間を調整・変更できる制度です(労働基準法32条の2、32条の4)。
(変形労働時間制の例)
2021年8月の1~4週目について、各労働日の所定労働時間を以下のとおり定める。
1週目:6.5時間
2週目:6.5時間
3週目:8時間
4週目:9時間
→1週間の平均労働時間は37.5時間なので、法定労働時間の範囲内
変形労働時間制の場合、各労働日の労働時間を超えて働いた場合に、残業代が発生します。
残業代が通常の賃金か、それとも割増賃金(25%以上)かについては、その残業が法定労働時間を超えているかそうでないかで判断します。
たとえば上記の例において、1週目の金曜に8時間働いたとします。
この場合、所定労働時間の6.5時間を超える1.5時間が残業に当たります。
しかし1日単位で見れば8時間以内、1週単位で見れば40時間以内に収まっているため、この1.5時間に対しては通常の賃金を支払えば足りるのです。
これに対して、1週目の金曜に9時間働いた場合、「1日8時間」を超える1時間については割増賃金の支払いが必要です。
また1週目の木曜と金曜に9時間ずつ働いた場合、「1週40時間」を0.5時間超過するため、やはり割増賃金の支払いが必要になります。
フレックスタイム制の場合
「フレックスタイム制」とは、一定期間(清算期間)について総労働時間を設定し、その範囲で労働者が始業・終業時刻を自ら決定できる制度です(労働基準法32条の3)。
(フレックスタイム制の例)
2021年8月の1~4週目を清算期間とし、総労働時間を140時間とする。
フレックスタイム制では、清算期間中の労働時間が総労働時間を超えた場合に、超過分について残業代が発生します。
残業代が通常の賃金か、それとも割増賃金(25%以上)かについては、清算期間における法定労働時間を超過しているかどうかによって決まります。
たとえば上記の例において、2021年8月の1~4週目の間に170時間働いたとしましょう。
この場合、総労働時間の140時間を超える30時間分が残業に当たります。
法定労働時間は「1週40時間」なので、この4週間における法定労働時間は160時間です。
したがって、法定労働時間内の20時間分については通常の賃金が、法定労働時間外の10時間分については割増賃金が支払われます。
残業代が発生しない勤務形態について
労働基準法上、労働者の業務内容や勤務形態によっては、残業代を支払わなくてよいケースが存在します。
ただし、会社の誤解や都合のよい解釈により、それぞれ間違った運用がなされているケースもあります。
何らかの理由で残業代が支払われていない場合には、その取扱いが本当に正しいのかどうか確認するため、弁護士にご相談ください。
農林・畜産・養蚕・水産事業
農林事業および畜産・養蚕・水産事業に従事する労働者については、労働時間の規制が適用されず、残業代が発生しません(労働基準法41条1号)。
農林事業および畜産・養蚕・水産事業の例は、以下のとおりです。
①農林事業
・土地の耕作、開墾
・植物の栽植、栽培、採取、伐採 など
②畜産・養蚕・水産事業
・動物の飼育
・水産動植物の採捕、養殖 など
管理監督者、機密の事務を取り扱う者
経営者と一体的な立場にある「管理監督者」については、労働時間の規制が適用されず、残業代が発生しません(労働基準法41条2号)。
ただし、管理監督者に当たるかどうかは、権限・待遇・時間的裁量などの観点から実質的に判断されます。
これらの点で経営者と一体とは到底評価できないのに、単に「管理職」だからという理由で残業代を支払わないのは違法です(「名ばかり管理職」)。
また、経営者または管理監督者の活動と一体不可分の職務を行う「機密の事務を取り扱う者」についても、残業代が発生しません。
代表的な例としては、経営者の秘書が挙げられます。
監視または断続的労働
手待ち時間が長い監視または断続的労働に従事する労働者は、労働時間に比べて業務上の負荷が比較的軽いと評価できます。
そのため、労働時間規制が適用されず、残業代が発生しません(労働基準法41条3号)。
監視または断続的労働に従事する労働者の例は、以下のとおりです。
(例)
・守衛
・学校の用務員
・団地の管理人
・会社役員の専属運転手 など
なお、これらの労働者について労働時間等の規制を適用除外とするためには、所轄労働基準監督署長の許可を得る必要があります。
事業場外みなし労働時間制
事業場の外で業務に従事したため、労働時間の算定が難しい場合には、原則として所定労働時間働いたものとみなされます(労働基準法38条の2第1項)。
この場合、残業代は発生しません。
ただし、業務に所定労働時間を超える時間を通常要すると認められる場合には、例外的に残業代が発生します(同条第2項)。
事業場外みなし労働時間制の名の下に、理不尽な長時間労働を強いられている場合には、残業代が発生している可能性を疑いましょう。
専門業務型裁量労働制
以下の法定業務については、専門性の高い労働者に対して、業務の遂行手段や時間配分の決定を委ねる「専門業務裁量労働制」を導入することができます(労働基準法38条の3)。
- ①新商品や新技術などの研究開発業務
- ②情報処理システムの分析、設計業務
- ③記事取材、編集などの業務
- ④新たなデザインの考案業務
- ⑤放送プロデューサー、ディレクター業務
- ⑥コピーライター業務
- ⑦システムコンサルタント業務
- ⑧インテリアコーディネーター業務
- ⑨ゲームソフトの創作業務
- ⑩証券アナリスト業務
- ⑪金融商品の開発業務
- ⑫大学教授の業務
- ⑬公認会計士業務
- ⑭弁護士業務
- ⑮建築士業務
- ⑯不動産鑑定士業務
- ⑰弁理士業務
- ⑱税理士業務
- ⑲中小企業診断士業務
専門業務型裁量労働制の対象者は、労使協定で定められる時間数の労働をしたものとみなされます。
みなし労働時間が法定労働時間を超えない場合、残業代は発生しません。
これに対して、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、超過分については割増賃金を支払う必要があります。
企画業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制の対象に含まれない業務であっても、企画・立案・調査・分析を内容とする業務については、労働者の大幅な裁量を認めるべきケースがあります。
このような業務については、「企画業務型裁量労働制」を導入して、専門業務型裁量労働制と同じくみなし労働時間制を採用することが認められています(労働基準法38条の4)。
なお、企画業務型裁量労働制の条件については、労使協定よりも厳格な「労使委員会決議」で定めなければなりません。
まとめ
残業代の計算方法については、給与体系や勤務形態ごとに異なる注意点が存在し、考慮すべき内容もかなり多岐にわたります。
そのため、正確に残業代を計算することは難しいですが、弁護士に依頼するとスムーズかつ正確に計算を行ってもらえます。
会社に対する残業代請求をご検討中の方は、一度弁護士までご相談ください。
参考:給与計算とは?基本からシミュレーション、覚え方までわかりやすく解説|kyozon

◆100万円以上の債権回収に対応◆大手信託銀行の勤務経験◆元・司法書士、マンション管理士等も保有◆家賃滞納・明渡しの他、貸金・売掛金・請負代金のトラブルもご相談を。解決に自信があるからこその有料相談!
事務所詳細を見る
【来所不要/全国対応】100万円以上の債権でお困りの法人・個人事業主様の為に。豊富な知見を活かした独自の交渉術で、諦めていた問題も解決に導きます【未払金請求、契約違反や不法行為等の損害賠償請求など幅広く対応】
事務所詳細を見る
【顧問契約5.5万~|約2,000万円の債権回収実績】法人・個人事業主・不動産オーナー様の売掛金回収、未払い賃料回収なら◆企業の福利厚生でのご利用可◆オンライン面談◎※個人案件・詐欺のご相談はお受けしておりません
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

給料・賃金・残業代に関する新着コラム
-
残業代(時間外労働手当など)については、労働基準法で詳細にルールが定められています。会社に対して正しく残業代を請求するため、労働基準法上のルールを理解しておきま...
-
残業代の計算方法は、勤務形態によってさまざまです。労働基準法の割増賃金に関するルールや、勤務形態ごとの残業代計算の考え方を解説します。
-
給料未払いが発生した場合、労働基準監督署に相談すれば、勤務先の会社に対する監督指導が行われる可能性があります。給料未払いがあったときに労働基準監督署で受けられる...
-
給料未払いが発生した場合、相談先としては労働基準監督署・弁護士・司法書士・社会保険労務士などが考えられます。各相談先のメリット・デメリットについて解説します。
-
未払いの残業代を請求するにあたって必ず意識しなければならないのが『時効』の存在です。残業代請求の時効については、近年に法改正がおこなわれて期間が変更されているの...
-
時間外労働に対しては残業代が支払われるのが当然です。しかし、さまざまな理由をつけて残業代を支給しない会社も少なくありません。残業代が発生する仕組みの基本や残業代...
-
残業代請求訴訟では、証拠があっても必ず勝訴できるとは限りません。少しでも有利な立場で進めるためには失敗するケースを踏まえたうえで、それらを回避する必要があります...
-
給料未払いの問題についてはさまざまな回収方法がありますので、状況に応じて適切に判断対応するようにしましょう。また回収にあたっては時効期間もあるため、速やかに対応...
給料・賃金・残業代に関する人気コラム
-
給料未払いの問題についてはさまざまな回収方法がありますので、状況に応じて適切に判断対応するようにしましょう。また回収にあたっては時効期間もあるため、速やかに対応...
-
給料未払いが発生した場合、労働基準監督署に相談すれば、勤務先の会社に対する監督指導が行われる可能性があります。給料未払いがあったときに労働基準監督署で受けられる...
-
未払いの残業代を請求するにあたって必ず意識しなければならないのが『時効』の存在です。残業代請求の時効については、近年に法改正がおこなわれて期間が変更されているの...
-
給料未払いが発生した場合、相談先としては労働基準監督署・弁護士・司法書士・社会保険労務士などが考えられます。各相談先のメリット・デメリットについて解説します。
-
残業代(時間外労働手当など)については、労働基準法で詳細にルールが定められています。会社に対して正しく残業代を請求するため、労働基準法上のルールを理解しておきま...
-
時間外労働に対しては残業代が支払われるのが当然です。しかし、さまざまな理由をつけて残業代を支給しない会社も少なくありません。残業代が発生する仕組みの基本や残業代...
-
残業代請求訴訟では、証拠があっても必ず勝訴できるとは限りません。少しでも有利な立場で進めるためには失敗するケースを踏まえたうえで、それらを回避する必要があります...
-
残業代の計算方法は、勤務形態によってさまざまです。労働基準法の割増賃金に関するルールや、勤務形態ごとの残業代計算の考え方を解説します。
給料・賃金・残業代の関連コラム
-
残業代請求訴訟では、証拠があっても必ず勝訴できるとは限りません。少しでも有利な立場で進めるためには失敗するケースを踏まえたうえで、それらを回避する必要があります...
-
残業代の計算方法は、勤務形態によってさまざまです。労働基準法の割増賃金に関するルールや、勤務形態ごとの残業代計算の考え方を解説します。
-
給料未払いの問題についてはさまざまな回収方法がありますので、状況に応じて適切に判断対応するようにしましょう。また回収にあたっては時効期間もあるため、速やかに対応...
-
給料未払いが発生した場合、相談先としては労働基準監督署・弁護士・司法書士・社会保険労務士などが考えられます。各相談先のメリット・デメリットについて解説します。
-
未払いの残業代を請求するにあたって必ず意識しなければならないのが『時効』の存在です。残業代請求の時効については、近年に法改正がおこなわれて期間が変更されているの...
-
時間外労働に対しては残業代が支払われるのが当然です。しかし、さまざまな理由をつけて残業代を支給しない会社も少なくありません。残業代が発生する仕組みの基本や残業代...
-
残業代(時間外労働手当など)については、労働基準法で詳細にルールが定められています。会社に対して正しく残業代を請求するため、労働基準法上のルールを理解しておきま...
-
給料未払いが発生した場合、労働基準監督署に相談すれば、勤務先の会社に対する監督指導が行われる可能性があります。給料未払いがあったときに労働基準監督署で受けられる...