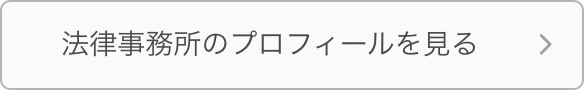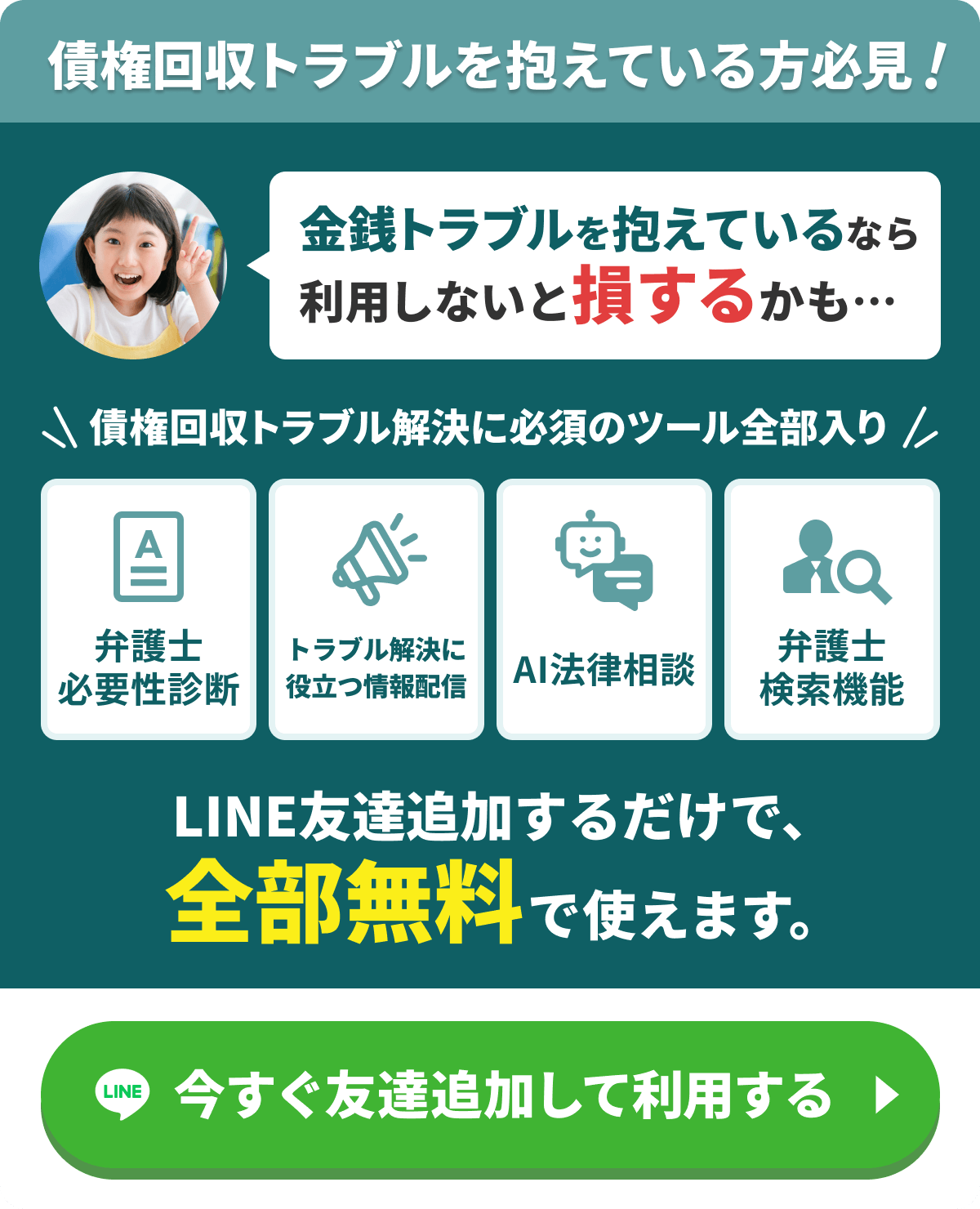離婚した相手が養育費を支払ってくれない場合は、相手の給料等を差し押さえて養育費を取り立てることが可能です。なお、これは例え相手が再婚をした場合も同様です。
今回の記事では養育費を差し押さえるための条件から手続き、差し押さえ前に必ず知っておいてもらいたい注意点などをまとめましたので、「絶対に養育費を支払ってもらいたい!」という方はぜひ参考にしてください。
養育費の差し押さえを検討している方へ
相手が養育費を支払わない場合は、給料等を差し押さえて養育費を取り立てることが可能です。
ただ養育費の差し押さえをするには、3つの条件を満たす必要があります。
- 相手に支払い能力がある
- 現住所を把握している
- 債務名義を持っている
また差し押さえをしたとしても、裁判所が取り立てに関わることはなく、債権者自身が相手の勤め先と話し合わなければなりません。
養育費でお困りの方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談をすれば、あなたの状況に適した解決策を提案してくれる事でしょう。
また依頼をした際には、相手の調査や差し押さえの法的手続き、相手との養育費交渉などを一任することが可能です。
初回相談が無料の弁護士事務所も掲載しているので、まずはご相談ください。
追加保険料0円で家族も補償対象のベンナビ弁護士保険登場
万が一の法律トラブルに備える保険は既に多くありますが、>ベンナビ弁護士保険はご加入者のご家族まで補償!
契約者の家族(契約者の配偶者及び1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の実子)も追加保険料0円で補償範囲(被保険者)に含まれます。

保険料は月2,950円となりますので対象家族が5人の場合、1人あたりの保険料は月590円に!対象となる家族が多い方にオススメです。
⇒ベンナビ弁護士保険の資料を無料で取り寄せる
KL2020・OD・039
養育費の差し押さえを行うための4つの条件
養育費を差し押さえるためには、以下すべての条件を満たす必要があります。
- 相手に支払い能力がある
- 相手の現住所を把握している
- 債務名義を取得している
- 相手の財産を把握している
満たしていない場合は、差し押さえ手続きの前に、やっておきましょう。
1.相手に支払い能力がある
相手に支払い能力があるか、確認が必要です。
相手が支払わない理由には、以下のような原因が考えられます。
- 単純に養育費の支払いを忘れている
- 養育費の支払いを拒否しており、意図的に払っていない
- 養育費を支払えるだけの余裕がない
仮に、相手が「養育費を支払えるだけの余裕がない」場合は、差し押さえが難しいケースがあります。
つまり、「絶対に差し押さえたい!」と思っていても、相手方は持ち合わせがなく、どうすることもできません。
2.相手の現住所を把握している
次項でも差し押さえの手順は解説しますが、手続き上、相手の現住所がわからないと差し押さえすることはできません。
もしもわからない場合は住民票の調査から行う必要がありますが、この調査は弁護士に依頼をすれば行ってもらうことができます。
3.債務名義を取得している
差し押さえには、「債務名義」(さいむめいぎ)が必ず必要になります。債務名義とは請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、かみ砕いて言うと“強制執行できる権利”を示した公的文書です。
債務名義の取得方法
主な債務名義の種類や取得方法は以下となります。
|
債務名義
|
取得方法
|
|
確定判決
|
訴訟
|
|
仮執行宣言付判決
|
|
和解調書
|
|
公正証書
|
相手との話し合い
|
債務名義についての詳細はこちら▶︎「債務名義の取得」をご覧ください
4.相手の財産を把握している
相手の財産を差し押さえようとしても、特定できなければ処理が行えません。
そのため、差し押さえる対象の財産を決めて、特定しておく必要があります。
例えば、給料を差し押さえたいときは相手の勤務先を特定する、預貯金を差し押さえたい場合は、相手の預貯金がある金融機関と支店名を特定する、といった具合です。
差し押さえられる財産には、以下のようなものが挙げられます。
【例】
|
不動産
|
土地・家など
|
|
動産
|
家具・現金・有価証券など
|
|
債権
|
給料・預貯金など
|
養育費を差し押さえるまでの手順

申し立てに必要な書類を揃える
差し押さえを行うには、「申し立て」をしなければなりません。
申し立てをする際には、書類が必要になるため、以下の書類を用意しましょう。
|
当事者目緑
|
自分と相手の住所等を記載したもの
|
|
資格証明書
|
相手の会社住所などを記載したもの
|
|
請求債権目録
|
相手への債権情報、請求金額を記載したもの
|
|
差し押さえ債権目録
|
相手の債権や勤務先などを記載したもの
|
|
債務名義
|
離婚公正証書正本など執行文付与を受けたもの
|
|
送達証明書
|
相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類
|
参考:裁判所|書式一覧
債権差押命令の申し立てをする
必要書類が揃ったあとは、1冊の本のようにまとめて裁判所に提出します。
提出の際は、収入印紙代4,000円と、数千円分の郵便切手代が必要になります。
債権差押命令が出される
申し立てが完了すると、裁判所から債務者である相手方へ「債権差押命令」という通知書が送達されます。
また、給料債権の差し押さえの場合には、相手の職場に対しても差押命令が送られます。
申し立てた人のもとに送達通知書が送られてくるので、必ず確認しましょう。
給料債権差押えの場合は相手の会社と話し合う
一般的には、債権差押命令が送達された段階で、相手の職場から債権者宛に電話等の連絡が入ります。そこで債権者が相手の職場と直接話し合いを行い、どのような方法で支払いを受け取るのかを決定することになります。
一般的には指定口座番号を伝えて、毎月相手の職場から差し押さえ相当額を振り込んでいただくことになるでしょう。
養育費の場合、差し押さえ額は、原則として社会保険料等を控除した手取額の2分の1と考えておくといいかもしれません。
取立完了届を提出する
養育費が無事に振り込まれたら、その旨を裁判所に伝えるために取立(完了)届を提出します。
▶取立完了届
養育費を差し押さえる際の注意点
裁判所が取り立てまで関わってくれることはない
差し押さえを行ったとしても、裁判所が取立てに関与してくれるわけではありませんし、自動で養育費が口座に振り込まれるわけでもありません。
相手の勤め先の人と話し合うのは、あくまでも申し立てを行った債権者本人になります。
給料の全額を差し押さえることはできない
差し押さえを行っても、相手の給料の全額を差し押さえることはできません。
給料の中から以下の項目などを引いた金額の2分の1は、差し押さえ禁止になります。
相手に弁護士費用は請求できない
次項で差し押さえを弁護士に依頼した場合の弁護士費用についてお伝えしますが、申し立てにかかった費用は相手に請求できても、この弁護士費用は相手に請求することができません。
相手が財産を持っているか確認する
差し押さえに関する手続きを行う前に、相手が財産を持っているか確認しましょう。もしも差し押さえを行った場合でも、相手に支払い能力が無ければ 2020年の民事執行法改正により、債務の弁済をしてもらえない場合の対策として、以下の2つの手続が制定されました。
(1)第三者情報取得手続
第三者情報取得手続を使うと、相手が養育費の支払に使える財産を持っているかに関する情報が、相手以外の第三者(金融機関、保険会社、証券会社等)より提供され、相手が財産を持っているかどうか等々がわかります。
その上で、素早く当該財産を差し押さえることにより、実効的に債権回収を図ることが期待できます。
(2)財産開示請求手続
相手に財産があるか確認する方法として、財産開示請求手続があります。
財産開示手続を利用することで、裁判所から相手方に対して財産開示期日の呼び出しが行われます。その際、合わせて財産目録の提出を要請されます。
また、裁判所での財産開示期日にて、債務者は、自身の財産状況を陳述しなくてはならず、陳述により、強制執行対象となる財産の有無を知ることができます。
不当に拒否した場合には後述の罰則があります。
罰則
2020年の民事執行法改正で、裁判所へ出頭を拒否した場合の罰則が、30万円の過料から6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下への罰金へと強化されました。
過料と違い、罰金は刑事罰です。
以前は、30万円支払っても出頭を拒否するケースが散見されました。
出頭を拒否すると前科がつくように改正されたため、今後は財産開示請求に応じる率が格段に上がることが想定されます。
せっかく債務名義を取得しても、強制執行対象たりうる財産の所在が分からないことが多々あります。そのような場合は、第三者情報取得手続や財産開示請求手続の活用を検討することがおすすめです。
養育費の差し押さえは弁護士依頼がおすすめの理由
差し押えをする際は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
なぜなら、法的手続きが必要になるからです。
また、必要書類も複数枚あり、「なにをどうしたらいいのかわからない」手探り状態では、時間と労力がどうしてもかかってしまいます。
家事・育児に追われている中、すべて自分で行おうとすると、体調を崩してしまいかねません。
弁護士に依頼すると、以下のことを一任できます。
- 差し押さえに関する法的手続き
- 必要書類の作成
- 事前の財産調査
また、差し押さえる財産についても、最適なものをアドバイスしてもらえるため、安心できるのではないでしょうか。
弁護士に依頼した際の費用
「弁護士に依頼したいけど、費用が心配…」と思う方もいるでしょう。
弁護士費用を紹介します。
【費用の目安】
|
相談料
|
30分~1時間:5,000円程度
|
|
着手金
|
平均20~40万円程度
|
|
報酬金
|
回収金額の約10~20%程度
|
|
実費
|
交通費・宿泊費 など
|
事務所や、債券の回収金額、トラブルの複雑さによって金額が変わります。
相談料や着手金を無料で提供しているところもありますので、まずは弁護士に相談してみましょう。
まとめ|養育費の差し押さえは弁護士に相談しながら進めよう
差し押さえをする際は、さまざまな法的手続きがあり、自分で行おうと思うと手間がかかります。
弁護士に依頼すると、手続きや交渉の代理をしてもらえるので手間や労力が省け、仕事や家事・育児に集中できます。
毎日多忙にしている方にとっては大きな利点ではないでしょうか。
とはいえ、弁護士費用がかかるのは事実です。
相手と連絡がとれるのであれば、差し押さえを行わずに交渉で支払ってもらうのが一番てっとり早く、差し押さえ費用や弁護士費用もかからずに済みます。
「このまま支払われなければ差し押さえをするつもりである」という旨を伝えるだけでも、会社に差し押さえの通知がいくのを嫌う相手から支払いを受けられることも少なくないので、試してみてはいかがでしょうか。
養育費の差し押さえを検討している方へ
相手が養育費を支払わない場合は、給料等を差し押さえて養育費を取り立てることが可能です。
ただ養育費の差し押さえをするには、3つの条件を満たす必要があります。
- 相手に支払い能力がある
- 現住所を把握している
- 債務名義を持っている
また差し押さえをしたとしても、裁判所が取り立てに関わることはなく、債権者自身が相手の勤め先と話し合わなければなりません。
養育費でお困りの方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談をすれば、あなたの状況に適した解決策を提案してくれる事でしょう。
また依頼をした際には、相手の調査や差し押さえの法的手続き、相手との養育費交渉などを一任することが可能です。
初回相談が無料の弁護士事務所も掲載しているので、まずはご相談ください。