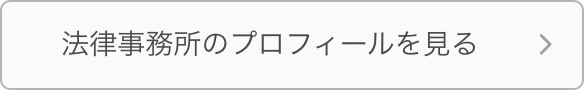弁済に応じない相手から債権回収をするために、給料を差し押さえするのは効果的な方法だといえるでしょう。
回収したい相手がたとえアルバイトでも、雇用されていれば差し押さえ後に継続的に給料の一部から弁済してもらうことができるからです。
本記事では、給料を差し押さえるにあたり、知っておきたい基本事項や差押えをする方法と手順について説明していきます。
また、給料の差し押さえを回避されてしまう事例についても紹介しています。
給料の差押えをご検討中の方へ
給料差し押さえは、執行機関に申し立てて強制執行手続きを経て債権回収をする方法ですので、法律の規定に沿った手続きが必要となります。
また差し押さえができる給料には上限金額が設定されています。
給料の差し押さえを検討している方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
- 給料の差し押さえが自身の状況にあった債権回収の仕方か分かる
- 給料の差し押さえのために必要な手続きをすべて任せることが可能 など
弁護士なら給料の差し押え額が債権額に満たなかった場合でも、適切な対処をしてもらうことが可能でしょう。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたのお悩みをご相談ください
給料を差し押さえるために知っておくべきポイント
まず、給料の差し押さえをする前に、差し押さえとはそもそもどういったものなのかについて理解しておきましょう。
差し押さえとは?
差し押さえとは、裁判所を通じて、相手側が所有する特定の権利を強制的に、申し立てた人へ移すための手続きです。
「貸したお金が返ってこない」「養育費の支払いが滞っている」などの場面で、債務名義があるにもかかわらず、相手側から支払いをしてもらえない場合におこなう強制執行のことであり、最終手段としておこなわれます。
給料の差し押さえは、執行機関に申し立てて、強制執行手続きを経て国家権力により債権回収をする方法なので、法律の規定に沿った手続きが必要となります。
なお、月給だけでなくボーナスや退職金なども差し押さえの対象になります。
債務名義の一覧
差し押さえをするためには、裁判所で強制執行手続きをおこなわなければなりません。
強制執行の申し立てをするには、債務名義を取得している必要があります。
債務名義とは、公的に債権者の債権の存在を示すための文書になります。
民事訴訟によって取得できる確定判決をイメージするとわかりやすいでしょう。
確定判決以外にも、和解調書、調停調書、公正証書、仮執行宣言付支払督促などがあげられます。
各種、債務名義の取得方法は以下の表を参考にしてください。
|
債務名義
|
取得方法
|
裁判所
|
|
公正証書
|
債務者との話合い
|
×
|
|
仮執行宣言付支払督促
|
支払督促
|
○
|
|
少額訴訟判決
|
少額訴訟
|
○
|
|
和解調書
|
訴訟
|
○
|
|
仮執行宣言付判決
|
○
|
|
確定判決
|
○
|
給料差し押さえに必要な情報
強制執行で預金を差し押さえる場合は、銀行名や支店名などが必要になります。
給料を差し押さえる場合には、「勤務先」がわかっていれば差し押さえのための手続きをおこなうことができます。
雇用主が第三債務者になる
給料の差し押さえをおこなうことによって、相手側が所有する給料債権の一部は差し押さえられます。
差し押さえの対象となる相手側は、給料債権という面では法的に債権者であり、この相手側の雇用主は債務者にあたります。
雇用主は、差し押さえを申し立てられたことによって、差し押さえを申し立てた人の債務者として、申立人へ弁済をしなければなりません。
つまりは、差し押さえをすることで、申立人は雇用主から給料分を弁済してもらうということです。
- 申し立てをおこなう人:債権者
- 相手方:基本は債務者、給料については債権者
- 相手方の雇用主:第三債務者
給料差し押さえの上限金額
差し押さえることができる給料には上限金額が設定されています。
これは差し押さえられる側の最低限度の生活を保障するためです。
手取り額が44万円以下の場合と、44万円を超える場合で上限金額は異なり、差し押さえ可能な給料の上限金額は以下のとおりになります。
- 手取り額が月額44万円以下の場合:手取り額の4分の1
- 手取り額が月額44万円を超える場合:手取り額から33万円控除した金額
※手取り額:所得税・住民税・社会保険料・通勤手当などを控除した金額
養育費など扶養義務債権の場合
養育費の滞納などを理由に差し押さえをする場合は、差し押さえ可能な給料の額は高額になります。
手取り額が月額66万円以下の場合と、66万円を超える場合で異なり、上限金額は以下のとおりです。
- 手取り額が月額66万円以下の場合:手取り額の内の2分の1
- 手取り額が月額66万円を超える場合:手取り額から33万円控除した金額
役員報酬は全額差し押さえ可能
給与を差し押さえる相手が、取締役や監査役などの地位についている場合は、給料(役員報酬)の全額を差し押さえることができます。
取締役や監査役の方は、会社から雇用されているわけではありません。
会社とは雇用契約ではなく、委任契約を結んでいることになるため、全額の差し押さえが可能です。
給料から差し押さえ可能な金額の計算例
それでは次に、差し押さえ可能な具体的な金額を計算してみましょう。
- 手取り額が月20万円の場合:手取り額の4分の1が上限ですので「5万円」
- 手取り額が月45万円の場合:手取り額から33万円を控除した金額が上限ですので「12万円」
一方で、養育費の滞納など扶養義務債権を理由に差し押さえをおこなう場合は限度額が上がるため、以下のとおりです。
- 手取り額が月20万円の場合:手取り額の2分の1が上限ですので「10万円」
- 手取り額が月50万円の場合:手取り額の2分の1が上限ですので「25万円」
- 手取り額が月67万円の場合:手取り額から33万円を控除した金額が上限ですので「34万円」
養育費などの扶養義務債権以外の場合、差し押さえできる上限額は「月の手取り額の4分の1」と少ないように感じるかもしれません。
しかし、現状で交渉に応じてもらえないために給料の差し押さえを検討している方が多いのではないでしょうか。
給料からの差し押さえは、少しずつではありますが、債権の回収に有効です。
給料を差し押さえると、差し押さえられる側の勤務先にも通告されるため心理的効果が非常に大きいです。
最終催告書や差押予告書などの通知をおこなうだけでも、交渉に応じてもらえる可能性があります。
まずは弁護士に相談をして、現状で取れる対策についてアドバイスを受けるのも良いでしょう。
給料を差し押さえる方法と手順

給料の差し押さえは、債権差し押さえとしておこないます。
債権差し押さえの手続きの方法を順を追って解説します。
1.債権差し押さえの申立て
まず、債権差し押さえの申立てをしますが、申立てには以下の書類が必要です。
必要書類の記載方法については「債権執行」を確認してください。
また、申立時には手数料として約4,000円、郵便切手代として約3,000円を納めなければなりません。
2.差押命令
債権差し押さえの申立てが受理されると、差押命令正本が債務者である相手方と第三債務者である雇用主へ郵送されます。
郵送されると、差押命令正本が郵送されたことを伝える送達通知書が、債権者である申立人に届きます。
3.陳述書の返送
第三債務者は、差押命令が送られたあとに、裁判所へ陳述書を返送しなければなりません。
4.債権の差し押さえ
「ほかに債権者がいた場合」や「第三債務者が供託をした場合」など、状況によって金銭の受け取り方法が異なります。
|
※供託とは:金銭や有価証券などの所有する資産を供託所に預けるための手続。各債権者は、供託所に預けられた債権・資産を、配当という形で債権額に応じて配当金を受け取ることになる。
|
裁判所にて配当手続き(債権者がほかにもいた場合)
給料債権を差し押さえている債権者がほかにいた場合、第三債務者は供託の手続きをしなければなりません。
各債権者には、第三債務者が供託した資産の中から、配当が割り当てられます。
配当を受け取るために裁判所の指示に従って手続きをおこなってください。
裁判所にて弁済金交付手続き(第三債務者が供託した場合)
「ほかに債権者はいないが、第三債務者が供託をした」という場合、弁済金交付手続きによって弁済してもらうことになります。
裁判所から手続きの方法に関する連絡が届くので、裁判所の指示どおりに手続きをおこないましょう。
取り立て(上記に該当しない場合)
上記に該当しないのであれば、差押命令から1週間後に、第三債務者へそのまま取り立てることが可能です。
どのように弁済してもらうかは、第三債務者と話し合ったうえで決めましょう。
5.取立完了届の提出
給料の差し押さえは、債権額と申立費用の合計額に達するまでおこなうことができます。
請求金額の全額に達したら、裁判所へ取立完了届を提出してください。
その債権、回収できるかもしれません!

差し押さえすれば、諦めていた債権を回収できる可能性があります。
まずは差し押さえで債権回収に成功した事例や、弁護士の選び方を確認しましょう。
差し押さえで債権回収に成功した事例を見る
給料差し押さえを回避されるケース
給料の差し押さえ手続きをおこなっても、なかには請求金額を全て受け取れないまま回避されるケースもあるので念頭に置いておきましょう。
債務者の勤務先がわからない・短期間で転職を繰り返している場合
給料の差し押さえをおこなうには、債務者の勤務先情報が必須になります。
相手が公務員や上場企業の社員などの場合は、すぐに転職ということも考えにくいので、継続的に給料から差し押さえをおこなうことが可能でしょう。
一方、相手が転職をしてしまい、勤務先がわからなくなった場合には再度手続きをおこなうことが困難となってしまいます。
そのほかにも、短い期間で職を転々としている場合も手続きが難しいため、給料差し押さえ以外の方法が取れないか検討してみましょう。
債務者が個人再生手続きを開始した場合
債務者の借入残高が大きくて借金返済が困難な場合、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理がおこなわれる可能性があります。
個人再生とは、借金などの返済ができなくなった人が裁判所に再生計画(返済計画)を提出し、認可を受けることで借金を大幅に減額する手続きのことです。
この手続きが開始されると、強制執行(給料差し押さえ)は中止され支払いがおこなわれなくなります。
ただしその場合でも、勤務先が差し押さえ分を会社内部で保管するため、債務者が給料を全額受け取れるわけではありません。
債務者が自己破産した場合
前述の個人再生と同様に、債務者が自己破産した場合も、強制執行(給料差し押さえ)は中止され支払いがおこなわれなくなります。
自己破産とは、「借金の返済ができない状態に陥っている」と裁判所から認めてもらったうえで免責許可決定を得ることで、一定の負債の返済義務を免れることができる手続きのことです。
自己破産については、「同時廃止事件」や「管財事件」などいくつかのパターンがあり、それぞれ以下のように取り扱いが異なります。
同時廃止事件の場合|差し押さえは中止・一時停止
自己破産の同時廃止事件とは、借金の返済が困難な状況で、総資産が20万円以下かつ免責不許可事由が明らかにない場合に個人がおこなう自己破産の手続きのことです。
自己破産手続きにはお金がかかりますが、同時廃止事件の場合はその費用を支払うことも困難であると判断され、破産管財人が選任されません。
自己破産の同時廃止事件では、手続きと同時に強制執行(給料差し押さえ)がストップされます。
しかし、個人再生の場合と同様に、債務者が給料を全額受け取れるわけではなく、勤務先が差し押さえた分を会社内部で保管または供託されることになります。
その後、免責が確定された場合は、差し押さえは失効という流れになります。
管財事件の場合|差し押さえは失効
自己破産の管財事件とは、借金の返済が困難な状況で、一定額以上の財産がある場合にその財産を換金して債権者への配当などをおこなう自己破産の手続きのことです。
破産法第42条では、自己破産の申立てをして、裁判所が破産手続開始決定をすると、すでに開始されている強制執行手続は効力を失うと定められています。
そのため、給料の差し押さえを含む強制執行は失効となり、差し押さえは停止されます。
個人再生や自己破産をしても支払い義務が残る場合がある
個人再生や自己破産をしても支払い義務が残るものを「非免責債権」といいます。
たとえば、租税・悪意で加えた損害賠償請求権・養育費などがこれにあたります。
給料の差し押さえ額が債権額に満たなかった場合の対処法
ここでは「給料の差し押さえをしたが、回収途中で相手側が仕事を辞めてしまい回収できなかった」というような場合にどうすればよいのかを解説します。
取下書を提出する
まず、途中で回収不能になった場合は、差押命令を取下げるための取下書と、債務名義を手元に戻すための債務名義還付申請書を裁判所へ提出しましょう。
取下書の提出は、弁済が完了した時点でも必要です。
ほかの財産も差し押さえする
次に、差し押さえをしたい相手側に、ほかに差し押さえることができる財産がないか検討しましょう。
預金・銀行口座
もし、相手側が貯蓄している預け先の金融機関がわかっているのであれば、預金を差し押さえることができます。
預金の差し押さえも、給料の差し押さえと同様の方法でおこないます。
不動産
相手側が不動産を所有している場合は、不動産の差し押さえも検討しましょう。
不動産は高額な資産であるため、十分な回収が見込めます。
しかし、申立費用が高く、十分な回収ができないこともあるので注意してください。
不動産を差し押さえる方法については以下の記事を参考にしてください。
換金価値のある資産
自動車や有価証券など換金価値のある資産を差し押さえることもひとつの手段です。
その場合は動産執行を通じて差し押さえることになり、手続きの方法は「動産執行」を参考にしてください。
給料の差し押さえを弁護士に依頼するべきかどうか
ここでは、給料の差し押さえを弁護士に依頼するべきかどうかの判断基準として、弁護士に依頼するメリットや費用相場などを解説します。
弁護士に依頼する3つのメリット
弁護士に依頼するべきかどうかは依頼する人の状況によって異なりますが、依頼することでどのようなメリットがあるのかを知っておきましょう。
1.債権回収できる可能性が高まる
弁護士に依頼する大きなメリットは、個人で対応するより、債権回収できる可能性が高まることです。
弁護士に依頼することで、どの資産を差し押さえることが一番効果的であるのかを調査したうえで、差し押さえの手続きに踏み出すことができます。
これによって、「差し押さえの申立てをしたのに回収できない」などのリスクを減らすことが可能です。
2.差し押さえの手続きを一任できる
裁判所の手続きに不慣れな方にとって、差し押さえは負担が大きいでしょう。
弁護士に依頼することで、申立書類の収集から作成まで代わりにおこなってもらえます。
ただでさえストレスの多い債権回収ですので、手続きのわずらわしさが楽になるだけでも心理的負担を軽くすることができるでしょう。
3.相手にプレッシャーを与えられる
今まで個人間で交渉にあたっても応じてもらえなかった場合でも、弁護士を通すことで相手にプレッシャーをかけることができ、交渉に応じてくれることもあります。
状況によりどのような対処法が適しているかは異なりますが、弁護士から連絡が来るというのは相手の弁済に対するプレッシャーになることでしょう。
また、債権回収が得意な弁護士は、個別の状況ごとに適した方法を見極めて助言をしてくれます。
弁護士への依頼を考えている方は、ぜひ債権回収が得意な弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士費用の相場
差し押さえによって回収した金額と比べて、弁護士費用のほうが高くついてしまったら意味がありません。
そのため、事前に弁護士費用がどれくらいかかるのかを押さえておくべきです。
主な弁護士費用としては、受任時に発生する「着手金」や、案件完了時に発生する「報酬金」などがあり、費用の相場は以下のとおりです。
<着手金>
|
請求金額
|
着手金相場
|
|
300万円以下
|
請求金額の4%~8%
|
|
300万円超、3,000万円以下
|
請求金額の2.5%~5%
|
|
3,000万円超、3億円以下
|
請求金額の1.5%~3%
|
|
3億円超
|
請求金額の1%~2%
|
<報酬金>
|
回収金額
|
報酬金相場
|
|
300万円以下
|
回収金額の4%~16%
|
|
300万円超、3,000万円以下
|
回収金額の2.5%~10%
|
|
3,000万円超、3億円以下
|
回収金額の1.5%~6%
|
|
3億円超
|
回収金額の1%~4%
|
どれくらいの回収金額が期待できるのか、弁護士費用の総額はどれくらいかかるのかについては、弁護士事務所に直接相談してください。
その債権、回収できるかもしれません!

差し押さえをすれば、諦めていた債権を回収できる可能性があります。
まずは差し押さえで債権回収に成功した事例や、弁護士の選び方を確認しましょう。
差し押さえで債権回収に成功した事例を見る
給料の差し押さえに関するよくある質問
ここからは、給料の差し押さえに関してよくある質問を紹介します。
差し押さえたお金はいつ受け取れますか?
送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間を過ぎると、第三債務者から差し押さえた給料をもらうことができます。
差し押さえたお金はどのような方法で支払われますか?
自身で第三債務者である相手の会社に連絡をとり、支払い方法について相談する必要があります。
なお、弁護士に依頼した場合はこれにかぎりません。
第三債務者が供託した場合、お金は受け取れますか?
第三債務者が法務局に供託した場合には、直接お金を受け取ることはできません。
裁判所が配当などの手続きをおこない、その決定に従う形となります。
まとめ
本記事のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 給料差し押さえには債務名義と相手の勤務先情報が必要
- 差し押さえができる給料の上限額は決まっている
- 給料差し押さえをしても回避されるケースがある
- 債権トラブルは弁護士に相談することで回収できる可能性が上がる
給料の差し押さえは債権回収のひとつの手段ですが、最後の手段として検討しましょう。
ほかの資産も差し押さえることができるのか事前に調べておくと、債権回収の際に役立ちます。
債権トラブルは一人で悩まずに弁護士に相談することで、より適した対応策を見つけることができます。
弁済に応じない相手に立ち向かうことは、心理的にもストレスになることでしょう。
ぜひ、債権回収が得意な弁護士に相談してみることをおすすめします。
給料の差押えをご検討中の方へ
給料差し押さえは、執行機関に申し立てて、強制執行手続きを経て債権回収をする方法ですので、法律の規定に沿った手続きが必要となります。
また差し押さえができる給料には上限金額が設定されています。
給料の差し押さえを検討している方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
- 給料の差し押さえが自身の状況にあった債権回収の仕方か分かる
- 給料の差し押さえのために必要な手続きをすべて任せることが可能 など
弁護士なら給料の差し押え額が債権額に満たなかった場合でも、適切な対処をしてもらうことが可能でしょう。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたのお悩みをご相談ください