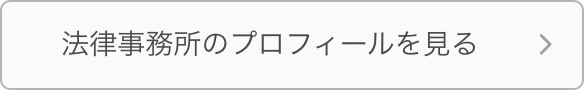顧問弁護士とは、法律に関する助言や、有事の際に法的問題に対処してくれる専属の弁護士を指す言葉です。会社を運営していくと、様々な点から業務に法的問題が発生しますが、そんな時に専属の弁護士がついていると心強いと思います。
では、一般的な弁護士と顧問弁護士には、どのような違いがあるのでしょうか。今回の記事では顧問弁護士が行う業務内容や、顧問弁護士に依頼するメリット、費用の相場についてまとめました。
顧問弁護士とは|社内の事業に関わる法務コンサルタント
顧問弁護士は法的トラブルにおける主治医と例えられることがしばしばあります。病気と同じく潜在化に眠っている法的トラブルは専門家でないと見分けることが難しいからです。日頃から自社の業務内容について理解している顧問弁護士がついていることで、法的トラブルが発生する前の段階で対処してもらうことができます。
主な業務内容|一般の弁護士との違い
顧問弁護士の行う業務内容は、一般の弁護士と変わりありません。そのため、顧問弁護士には、法律に関する相談、契約書の確認から作成、その他の自社の運営に関わる法律問題をオールラウンドに対応してもらうことができます。
しかし、両者の違いは、顧問弁護士は単発ではなく継続的な契約である点です。弁護士に相談するほどでもない問題でも気兼ねなく相談でき、またこちら側の事情も予め把握しているため、新規の弁護士に相談する場合のタイムラグがありません。
いつでも気軽に相談することができる弁護士が側についているため、顧問弁護士と契約を結ぶことで事業に専念することができます。
顧問弁護士の利用の対象は大企業だけではない?
顧問弁護士と聞くと、大手の企業が契約をするイメージを持たれるかもしれません。しかし、実際のところは中小企業、自営業者、個人事業主も顧問契約を締結することも多々あります。また、事業主に限らず最近では一般の個人の方が顧問弁護士を利用するケースも増えてきています。
顧問弁護士を利用するメリット
顧問弁護士についてより理解を深めてもらうためにも、顧問弁護士と契約をするメリットについて確認していきましょう。
法的トラブルが発生した際の迅速な対応
法的トラブルを解決するためには迅速な対応が必要です。しかし、法的トラブルが発生してから弁護士が依頼を受任するまでには1、2週間近くの期間を要します。顧問弁護士の場合、優先的に案件を受任してもらうことができるので、受任するまでに発生するタイムラグがありません。
刑事事件は早期対応が必要
自社の従業員が取引先の会社へ事件を起こしたために、刑事事件に巻き込まれるケースは無きにしもあらずです。この場合、従業員だけでなく会社も責任を取らなければなりません。少しでも事態を悪化させないためにも、事件が発生してから、なるべく早く従業員に弁護士に依頼する必要があります。
一般の弁護士と違い、顧問弁護士と契約をしていれば、早期に刑事事件に対応してもらうことが可能です。
経営上必要な法的コンサルタント
顧問弁護士には、経営上に必要な法律に関する相談から、アドバイスを受けることが可能です。長期的に関わりを持つ顧問弁護士であれば社内の事業内容に関して理解があるため、実のある法的コンサルタントを受けることができます。
また、顧問弁護士を利用することで、自社の事業に携わる法律の改正や新たな判例の情報などを提供してもらうことも期待できます。
法務部門の設立よりも費用がかからない
会社によっては社内で発生する法的トラブルに備えて法務部門を設けています。法務部門を設けると、部門に必要な従業員の人件費も負担しなければなりませんが、会社の規模によっては顧問弁護士に依頼した方がコスパが良いです。
また、人件費削減のために法務部門で働く従業員を、容易に解雇することはできません。顧問弁護士は、契約期間が完了すれば契約を継続する必要がなくなるので法務部門を設立するよりもリスクが少ないです。
顧問割引制度
契約書の作成や債権回収など顧問契約外の業務を依頼した場合の弁護士費用は、月々に支払う顧問料とは別料金です。しかし、一般の弁護士に個別で依頼するよりも、顧問弁護士の方が、弁護士費用が安く設定されているため、顧問弁護士に依頼する頻度が高くなるほど、費用対効果は高くなります、
業務内容以外の相談も可能
顧問弁護士には、社長が亡くなった際の相続問題、従業員の事故への対処など、業務以外の個人的な相談ができる場合もあるようです。個人の相談に応じてくれるかどうかは弁護士によって異なるため、詳しくは問い合わせの際に確認してみてください。
個人で顧問弁護士を利用するメリット
先ほども申しましたが、顧問弁護士は個人の方が利用することもできます。日常生活で発生する法律問題に関する相談や、トラブルが発生した場合の弁護人を行うのが一般的です。
問題が大きくなる前に早期解決
個人においても法的トラブルを解決するためには、早期の対応が必要になります。一般的に弁護士が受任するまでには1週間〜2週間の期間を要するため、法的被害にあった被害者が泣き寝入りするケースは少なくありません。
介護が必要な親戚、一人暮らしをするお子さんのために、顧問弁護士を依頼する人も少なくありませんが、日常生活における不安を払拭するために顧問弁護士は個人の方へも有効なことがわかります。個人の方が利用する顧問弁護士に関して詳しくは以下の記事を参照にしてください。
顧問弁護士の費用の相場
では顧問弁護士に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
顧問料
まず、最もベーシックとなる弁護士費用は、月額顧問料です。「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」によると、顧問弁護士に依頼した場合の弁護士費用は以下の通りになります。大体、3万円~5万円を目安に考えるといいでしょう。
<有事の際に優先的にアポイントを取ることができる場合(個々の相談料は別途料金)>
- 1万円・・・1.0%
- 2万円・・・6.7%
- 3万円・・・40.0%
- 4万円・・・3.8%
- 5万円・・・45.7%
- 6万円・・・1.9%
- 7万円・・・0.0%
- 8万円・・・0.0%
- 9万円・・・0.0%
- 10万円・・・5.7%
- その他・・・1.9%

委託可能な業務内容
顧問料の範囲内で弁護士に委託できる主な業務は法律相談です。対面による相談は月々に2時間〜5時間と制約を設けられていますが、電話、メールにおける相談に関しては多くの場合、制限が設けられていません。
また、法律事務所によっては契約書のチェック、簡易的な内容証明の作成などは顧問料の範囲内で委託することができます。
ランニングコストに気をつける
気をつけなければならないのが、弁護士の顧問料は年間契約であるという点です。年間契約であるため、月々に発生する顧問料に変更はありませんが、顧問弁護士をあまり利用しない場合、元が取れません。そこで弁護士の利用頻度が少ない法人の多くが、タイムチャージ制を利用します。
タイムチャージ制は顧問料が低額(または無料)の代わりに、弁護士に業務を依頼した際に、仕事にかかった時間に応じて弁護士費用が算出される制度です。同じ顧問契約であるため、法的トラブルが生じた場合は即座に対応してもらうことが可能ですが、利用頻度が高くなった場合、一般の契約より高くつくため請求金額に気をつけましょう。
顧問料の範囲外の案件の費用相場
顧問料の範囲に含まれていない案件に関しては、別途で依頼してその都度、料金が発生します。以下、日本弁護士連合会の統計を元に、それぞれの費用の相場を確認していきましょう。
作成契約書の作成依頼
|
弁護士費用 |
顧問契約がある場合 |
顧問契約がない場合 |
|
5万円前後 |
49.0% |
25.0% |
|
10万円前後 |
21.4% |
43.8% |
|
15万円前後 |
2.3% |
10.9% |
|
20万円前後 |
3.9% |
8.9% |
|
30万円前後 |
0% |
5.9% |
|
0円 |
11.2% |
- |
|
その他 |
7.2% |
3.9% |
参考:「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」
労働事件
|
着手金 |
||
|
|
顧問契約がある場合 |
顧問契約がない場合 |
|
10万円前後 |
15.1% |
3.6% |
|
20万円前後 |
31.3% |
11.2% |
|
30万円前後 |
31.9% |
46.1% |
|
40万円前後 |
3.3% |
9.5% |
|
50万円前後 |
5.3% |
18.8% |
|
その他 |
1.0% |
1.0% |
|
報酬金 |
||
|
20万円前後 |
31.9% |
18.1% |
|
30万円前後 |
28.6% |
25.0% |
|
50万円前後 |
19.1% |
33.2% |
|
70万円前後 |
2.6% |
6.9% |
|
90万円前後 |
1.0% |
3.3% |
|
その他 |
3.0% |
0.7% |
参考:「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」
売掛金回収
|
着手金 |
||
|
|
顧問契約がある場合 |
顧問契約がない場合 |
|
50万円前後 |
53.3% |
30.9% |
|
70万円前後 |
20.7% |
19.1% |
|
100万円前後 |
12.2% |
44.4% |
|
120万円前後 |
0.3% |
1.0% |
|
150万円前後 |
0% |
1.3% |
|
その他 |
10.2% |
1.6% |
|
報酬金 |
||
|
100万円前後 |
35.2% |
17.4% |
|
150万円前後 |
29.6% |
17.1% |
|
200万円前後 |
26.0% |
58.2% |
|
250万円前後 |
1.0% |
3.6% |
|
300万円前後 |
0% |
0.7% |
|
その他 |
5.3% |
1.3% |
参考:「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」
以上のことから顧問弁護士の利用頻度や依頼する案件によっては、月額の顧問料を含めても顧問弁護士に依頼した方がお得かもしれません。
顧問弁護士を選ぶための基準とは?
どのような基準で、顧問弁護士を選べばいいのでしょうか。
自社ビジネスに対する理解
まず、顧問弁護士に依頼する主な目的は、社内の事業に関わる法律のアドバイスをしてもらうことです。そのため社内の事業内容に関わる法律に精通した顧問弁護士に依頼する必要があります。弁護士によって専門分野は異なるため、どのような法律の問題に対処してもらう必要があるのかを、洗い出した上で依頼する弁護士を決めましょう。
電話・メールの返答が早い
法的トラブルが発生した場合、問題解決のために、弁護士には迅速な対応をとってもらわなければなりません対応の早い弁護士に依頼するために、電話、メールなどのレスポンスの早い弁護士に依頼するといいでしょう。
顧問弁護士を探す方法
具体的にどのように顧問弁護士を見つけたらいいのか、その方法について紹介していきます。
同業者からの紹介
まず、同業他社から紹介してもらうのが一つの手段です。同業社であれば似た性質の法律問題を抱えているため、自社の法律問題に適した顧問弁護士を紹介してもらいやすくなります。また、弁護士の人柄や能力について、事前に情報をもらうことができるため、自社に合った弁護士かどうか品定めすることが可能です。
ネットを介して見つける方法
ネットを介して見つけるのも一つの手段です。検索する際は、地域名に絞って顧問弁護士を探してみてください。その中から弁護士費用、専門性、過去の経歴を元にいくつか候補を決めるといいと思います。
まとめ
実際のところ顧問弁護士に依頼するべきかどうかは、依頼する方の状況や依頼する目的によって異なるので一概には言えません。顧問弁護士を活用しなければ顧問料が無駄と思うかもしれませんが、専属の顧問弁護士がついていることで、その分、自社の事業に専念することができます。
顧問弁護士を検討されている方の多くが中小企業だと思われますが、中小企業の経営者の方は早期の段階で事業承継問題に取り掛からなければなりません。事業承継について詳しくは、「事業承継を弁護士に依頼するメリットと事業承継の手順の流れ」を参考にしてください。

◆即日交渉可◆LINE相談可◆電話で弁護士と直接話せる◆「今すぐ弁護士に相談したい!」という方はご相談を!LINEや電話で即日ご相談いただけます【男女間の金銭トラブルにも注力!】《解決実績は写真をクリック!》
事務所詳細を見る
【他事務所で断られた方歓迎|土日深夜も弁護士直通・LINEできる】男女トラブル・個人間の貸金回収は、早期の相談で回収率が大幅に変わります。迅速に対応します、ご相談ください。
事務所詳細を見る
【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

債権回収に関する新着コラム
-
はじめて債権管理を担当することになった方のなかには、上記のような不安がある方も多いでしょう。そこで、本記事では債権管理の基本的な概念・具体的な業務内容・システム...
-
未回収リスクとは、売掛金が期日通りに回収できないことで生じるリスクで、とくに中小企業にとっては経営を揺るがす大きな問題となりえます。本記事では、未回収リスクの基...
-
売掛金などの債権を長期間回収できずにいると、「長期滞留債権」として企業経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。本記事では、「長期滞留債権」とは何かや回収方法、...
-
通販では、支払いを後払いとすることも多く、代金未回収のリスクが発生します。本記事では、代金未払いで困っている場合、代金の回収のために、どのような手段を取り得るこ...
-
本記事では、どれだけ催告しても金銭債務を履行しない債務者にとることができる法的手段の種類、滞納状態にある債務者への対応を弁護士へ依頼するメリットなどについてわか...
-
債権回収が長い間できておらず売掛金があるため、債権回収の時効がどのくらいなのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、債権の消滅時効が成立する...
-
後払いの滞納に悩みがある事業者は少なくないですが、悩みの解決策の一つが少額かつ大量の債権の回収業務に注力している弁護士に依頼することです。本記事では、後払い代金...
-
占い詐欺に遭った際は、弁護士への相談がおすすめです。弁護士であれば、被害金の回収に向けた有効なアドバイスが望めるほか、返金請求を依頼することもできます。本記事で...
-
業務委託による報酬が未払いの場合、債務者に対して債権回収を行うべきでしょう。ただし対応にあたっては、状況に応じて回収方法を判断する必要がある上、時効期間などにも...
-
金銭トラブルで悩んでいる場合、弁護士に相談することでスムーズに解決できることも多いです。弁護士費用が高額にならないか不安であれば、無料相談を活用してはいかがでし...
債権回収に関する人気コラム
-
「お金を貸した相手と連絡が取れない」「いつまで経ってもお金を返してもらえない」など、借金の回収について頭を悩ませている方もいるでしょう。本記事では、借金の回収方...
-
貸したお金を返してもらえないとき、どのように回収をすれば良いかご存知でしょうか。借金の回収は、お金を貸した相手の状況に応じて適切な対応を判断する必要があります。...
-
差し押さえは、交渉での債権回収が困難な場合の最終手段として使われる法的手段です。差し押さえを行うために必要な費用や、手続き方法について、詳しくご紹介していきます...
-
少額訴訟にかかる費用は、自分で手続きを行った場合、または専門家に依頼した場合に、一体いくら発生するのでしょうか?
-
差し押さえは、債権回収の法的手段の一種で最終手段として使われます。それにより、不動産や預金、給与などの財産から強制的にお金を支払ってもらうことができます。この記...
-
債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...
-
少額訴訟は手続きがスムーズだったりしますが、訴状の書き方がわからないために諦めるという方も多くいらっしゃいます。書き方がわからない場合は、各相談窓口で教えてもら...
-
少額訴訟を行うにあたってかかる費用は自身で手続きを行う場合場合は裁判費用のみ、弁護士に依頼して行う場合は裁判費用に加え弁護士費用がかかります。この記事では詳細な...
-
債権回収を依頼した場合の弁護士費用相場は依頼状況などによっても異なりますが、ある程度の目安はあります。費用倒れを防ぐためにも弁護士費用について知っておきましょう...
-
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
債権回収の関連コラム
-
候補者へ事業継承させる上で様々な問題と直面しますが、今回の記事では希望の候補者へ事業を承継させるために必要な知識についてまとめました。
-
債務者(弁済者)の方にとって、代物弁済をする上で発生する税金に関する情報は気になるポイントだと思いますが、当記事では代物弁済における債務者、債権者の双方が負担す...
-
今回の記事では、債権回収を外部に代行するために、回収業務を行っている専門家・業者の説明から、抑えておきたい債権回収の知識などについて紹介していきます。
-
本記事では、どれだけ催告しても金銭債務を履行しない債務者にとることができる法的手段の種類、滞納状態にある債務者への対応を弁護士へ依頼するメリットなどについてわか...
-
最近ではコロナウイルスの影響などもあり、経営状況が悪化している会社もあります。取引先が倒産した場合に備えて、この記事で対処法を身につけておきましょう。この記事で...
-
今回の記事では、一般的な支払督促の申立の手順の手続きの流れから、支払督促後の強制執行の手順、債務者から異議を申し立てられた場合の対象方法などについて紹介していき...
-
貸したお金が返ってこない場合や、売掛金が回収できない場合などには、債権回収を弁護士に依頼することが早期解決に繋がることがあります。債権回収に強い弁護士を選ぶ際に...
-
家賃滞納とは、借主が賃貸人(大家さん)へ納めるべき賃料(家賃)の支払いを怠っている状態を指します。この記事では、大家さんに向けて家賃滞納をされた場合の対処法を、...
-
住宅ローンなどでお金を融資する際に、抵当権を設定することになりますが、債権者にとっていったいどのような利点があるのでしょうか。この記事では、抵当権の仕組みや効力...
-
貸したお金が返ってこない、催促しても音沙汰無し。ある程度自分で手を尽くしても回収が難しいならば債権回収会社に委託する方が得策です。委託するメリットや債権回収会社...
-
仮想通貨をめぐっては詐欺トラブルなども発生しており、「絶対に損はしない」などと騙され、一切お金が返ってこないというケースもあるようです。仮想通貨で大損を被らない...
-
差し押さえは、交渉での債権回収が困難な場合の最終手段として使われる法的手段です。差し押さえを行うために必要な費用や、手続き方法について、詳しくご紹介していきます...