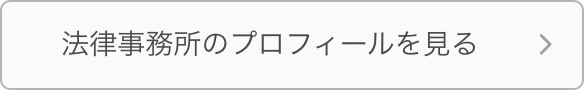最近ではコロナウイルスの影響などもあり、経営状況が悪化している会社もあります。ある日突然、取引先が倒産してしまう可能性もゼロではありません。この記事にて対処法について知っておきましょう。
この記事では、取引先が倒産した際に債権回収する方法や、倒産時に確認すべきポイントなどについて解説していきます。
取引先が倒産した場合にまず確認する2つのこと
帝国データバンクが発表している「新型コロナウイルス関連倒産」によると、2020年5月1日時点で新型コロナウイルス関連による会社の倒産件数は全国で115件となっています。また新型コロナウイルス関連の倒産は全国34都道府県で発生している状況です。日本をはじめとした世界各国の景気判断も軒並み引き下げられており、リーマン・ショック以来の苦境などという声も上がっています。
日本の経済状況の悪化により、どの会社にとっても「取引先の倒産」は他人事ではありません。優良な取引先だと評価していた会社が、急な経営状態の悪化により倒産するリスクすらあるのです。もし取引先が倒産した場合、経営者や取引の担当者はまず何をすべきでしょうか。確認すべきポイントは2つあります。
①倒産の情報の正確性
取引先の倒産を噂や人伝で耳にした場合は、情報の真偽を確認する必要があります。同業者などから「倒産したらしい」という話を耳にしても、倒産ではなく経営状況の悪化を勘違いして伝えていることもあるからです。
迅速な債権回収を行うためにも、まずは「取引先が本当に倒産したのか」(法的な倒産手続きを申し立てているのか)を確認しましょう。法的な倒産手続きが開始されているか否かで対応は異なりますので、まずは事実確認をきちんとしましょう。
②倒産手続きが再建か清算か
仮に、債務者が倒産手続きを履践していることが判明したとして、その場合もさらに情報の確認は必要です。一言で倒産といっても、さらに再建手続きと清算手続きの2つのパターンに分かれるため、詳しく確認しましょう。
倒産手続きのうち再建手続きは、法的手続きを通じて倒産会社の債務を減免するなどして、再建をはかるパターンです。具体的には、民事再生手続きや会社更生手続きなどがこの再建パターンの倒産に該当します。再建手続きの場合には、倒産会社は消滅せず、手続き終了後も事業が継続されます。
倒産手続きのうち精算手続きは、倒産会社が会社財産の一切を精算して消滅する手続きです。具体的には破産手続きや特別清算手続きがこれに該当します。精算手続きの場合には、倒産会社は会社財産を全て換価して、これを会社債権者や株主に分配し、最終的に消滅します。そのため、手続き終了後は当然事業もなくなります。
倒産の情報が確定的だと確認できたら、取引先がどちらのパターンなのかを確認した上で、各手続きに従った対応を行うことになります。
取引先が倒産した際の債権回収方法
取引先が倒産手続きに入った場合には、基本的に取引先に対する権利は倒産手続きを通じて処理されます。この場合、手続きを無視して抜け駆け的に回収しても、手続きの中で弁済としての効力が否定される可能性もあります。そのため、取引先が法的手続きに入った場合には、おとなしく手続きに服するべきでしょう。
なお、以下のような権利行使は倒産手続きの中でも可能な場合がありますので、留意してください。
取引先からの債務と相殺
取引先と自社が持っている債権を相殺する方法です。たとえば、自社が倒産したA会社に対して100万円の債権を有していたとします。またA会社も自社に対して同じく100万円の債権を有している場合、この債権同士を相殺することによって、回収したに等しい効果を生み出すのです。
このような相殺処理は、倒産手続きの中でも実施できる場合が多いです。
担保権の実行
取引先に対する債権に担保権が付着している場合、倒産手続きの中でもその点が考慮される場合が多いです。担保権には以下のような種類があります。
- 抵当権
- 根抵当権
- 先取特権
- 留置権
- 譲渡担保権
- 質権 など
ただし、会社更生手続きの場合には、この担保権についても実行することが不可とされますので、担保を有していても回収できない場合もありますので、注意しましょう。
動産売買先取特権の活用
動産売買先取特権とは「動産を売却した会社が代金などを優先的に債権回収できる権利」です。この先取特権も倒産手続きの中では優位性がある債権として処理されます。
取引先の倒産により連鎖倒産しないために今からできること
多くの会社は取引先の経営状況と密接な関係にあります。取引先の経営状況が悪化すると債権回収などに影響が出て、自社も経営状況が悪化してしまい、最終的に取引先に引っ張られる形で連鎖倒産することもよくあるケースです。
取引先の倒産による自社の連鎖倒産を防ぐためには、常日頃からの対策が重要になります。連鎖倒産しないためにも、3つのことをしておきましょう。
契約書を締結する
極めて基本的な事柄ですが、取引先に対して明確な権利主張をするためには、権利の内容や発生根拠がある程度明確とされているべきです。そのため、取引先との間で何らかの取引を行っている場合には、取引の内容・条件について明確にする契約書を締結しておくべきでしょう。
このような契約書がない場合、仮に取引との間で支払いについてトラブルとなった時に、そもそもの権利の存在自体を争われてしまう可能性もゼロではありません。このようなトラブルを予防する意味でも、契約書の締結は重要です。
担保の確保
上記のとおり、取引先が倒産した場合には権利に担保(物的担保)がついているかいないかで手続きでの取扱いが大きく変わる可能性があります。また、物的担保が付されていなくても、人的担保(保証人)がいれば第三者である保証人からの回収可能性があるかもしれません。
そのため、取引先の信用が高くないような場合には、取引にあたって何らかの担保を差し入れてもらうようにしたり、最低でも一定の金額を保証金として預かるなどの権利保全の措置を講じておくことも検討しましょう。
取引企業倒産対応資金など公的融資の活用の検討
取引企業倒産対応資金などの公的融資を活用することも連鎖倒産防止に役立ちます。取引企業倒産対応資金は、日本政策金融公庫で提供している「取引先の倒産などより経営難に陥った会社に対する公的融資」です。
公的融資は、金融機関の融資より全体的に金利が低めに設定されており、経営難の際にも融資を受けられる可能性が高いというメリットがあります。使えそうな公的融資を確認しておくと共に、いざというときは有効活用しましょう。
まとめ
新型コロナウイルスの感染拡大により、日本経済の悪化が懸念されています。すでに新型コロナウイルスの影響で倒産する会社なども出ており、今後さらに倒産企業が出てくるのではないかと予想されているのが現状です。取引先の倒産や、取引先倒産に伴う連鎖倒産は、決して他人事ではありません。
もしものときのために、取引先の債権回収について最低限の知識は持っておくべきです。本記事が参考となれば幸いです。

【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

債権回収に関する新着コラム
-
はじめて債権管理を担当することになった方のなかには、上記のような不安がある方も多いでしょう。そこで、本記事では債権管理の基本的な概念・具体的な業務内容・システム...
-
未回収リスクとは、売掛金が期日通りに回収できないことで生じるリスクで、とくに中小企業にとっては経営を揺るがす大きな問題となりえます。本記事では、未回収リスクの基...
-
売掛金などの債権を長期間回収できずにいると、「長期滞留債権」として企業経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。本記事では、「長期滞留債権」とは何かや回収方法、...
-
通販では、支払いを後払いとすることも多く、代金未回収のリスクが発生します。本記事では、代金未払いで困っている場合、代金の回収のために、どのような手段を取り得るこ...
-
本記事では、どれだけ催告しても金銭債務を履行しない債務者にとることができる法的手段の種類、滞納状態にある債務者への対応を弁護士へ依頼するメリットなどについてわか...
-
債権回収が長い間できておらず売掛金があるため、債権回収の時効がどのくらいなのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、債権の消滅時効が成立する...
-
後払いの滞納に悩みがある事業者は少なくないですが、悩みの解決策の一つが少額かつ大量の債権の回収業務に注力している弁護士に依頼することです。本記事では、後払い代金...
-
占い詐欺に遭った際は、弁護士への相談がおすすめです。弁護士であれば、被害金の回収に向けた有効なアドバイスが望めるほか、返金請求を依頼することもできます。本記事で...
-
業務委託による報酬が未払いの場合、債務者に対して債権回収を行うべきでしょう。ただし対応にあたっては、状況に応じて回収方法を判断する必要がある上、時効期間などにも...
-
金銭トラブルで悩んでいる場合、弁護士に相談することでスムーズに解決できることも多いです。弁護士費用が高額にならないか不安であれば、無料相談を活用してはいかがでし...
債権回収に関する人気コラム
-
「お金を貸した相手と連絡が取れない」「いつまで経ってもお金を返してもらえない」など、借金の回収について頭を悩ませている方もいるでしょう。本記事では、借金の回収方...
-
貸したお金を返してもらえないとき、どのように回収をすれば良いかご存知でしょうか。借金の回収は、お金を貸した相手の状況に応じて適切な対応を判断する必要があります。...
-
差し押さえは、交渉での債権回収が困難な場合の最終手段として使われる法的手段です。差し押さえを行うために必要な費用や、手続き方法について、詳しくご紹介していきます...
-
少額訴訟にかかる費用は、自分で手続きを行った場合、または専門家に依頼した場合に、一体いくら発生するのでしょうか?
-
差し押さえは、債権回収の法的手段の一種で最終手段として使われます。それにより、不動産や預金、給与などの財産から強制的にお金を支払ってもらうことができます。この記...
-
債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...
-
少額訴訟は手続きがスムーズだったりしますが、訴状の書き方がわからないために諦めるという方も多くいらっしゃいます。書き方がわからない場合は、各相談窓口で教えてもら...
-
少額訴訟を行うにあたってかかる費用は自身で手続きを行う場合場合は裁判費用のみ、弁護士に依頼して行う場合は裁判費用に加え弁護士費用がかかります。この記事では詳細な...
-
債権回収を依頼した場合の弁護士費用相場は依頼状況などによっても異なりますが、ある程度の目安はあります。費用倒れを防ぐためにも弁護士費用について知っておきましょう...
-
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
債権回収の関連コラム
-
仮想通貨詐欺に遭ってしまったという方は、1円でも多く被害金を取り返すためにも、この記事で紹介するポイントを知っておきましょう。この記事では、仮想通貨詐欺に遭った...
-
患者が診療費を支払ってくれない場合は、任意的手段または法的手段の内から、回収対応を行うことが考えられます。この記事では、動物病院での診療費が未払いとなっている際...
-
貸したお金が返ってこない、催促しても音沙汰無し。ある程度自分で手を尽くしても回収が難しいならば債権回収会社に委託する方が得策です。委託するメリットや債権回収会社...
-
債権譲渡担保(さいけんじょうとたんぽ)とは、ある債権において債務者から買掛金の未払いなど弁済がなされなかった場合に備え、債務者が所有する債権を担保にかける目的で...
-
今回の記事では、債権回収を行う上での民事訴訟のメリット・デメリット、手続きの手順や費用についてまとめました。
-
問題が起きた時にすぐに対応してくれるのが顧問弁護士。通常の弁護士と違い、顧問弁護士を雇うことで時間をかけずにトラブル解決できます。ここでは、顧問弁護士の顧問料の...
-
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
-
裁判では立ち退き以外にも滞納した家賃の支払いを求めることができます。 今回の記事では家賃滞納者へ向けて裁判を起こす方法や、裁判費用を安く抑えるために必要なこと...
-
差し押さえは、債権回収の法的手段の一種で最終手段として使われます。それにより、不動産や預金、給与などの財産から強制的にお金を支払ってもらうことができます。この記...
-
債務者に直接請求する方法や裁判所を介して請求する方法など、依頼状況に応じて選ぶべき回収手段は異なります。特にスムーズに全額返金してもらいたい方は、弁護士への依頼...
-
債務者本人からの債権回収が難しい場合、保証人へ請求することになりますが、請求の進め方はケースに応じて選択する必要があります。そこで今回は、保証人請求のタイミング...
-
仮想通貨をめぐっては詐欺トラブルなども発生しており、「絶対に損はしない」などと騙され、一切お金が返ってこないというケースもあるようです。仮想通貨で大損を被らない...