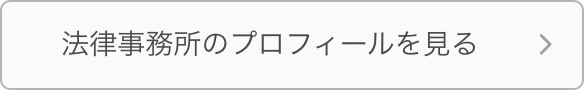事業承継とは事業を後継者や親族に引き継ぐことを指します。昨今、少子高齢化の影響もあり、承継する後継者が親族にいない、経営者の高齢化により事業承継が上手くできず、廃業に追い込まれる中小企業は珍しくありません。
事業承継の現実
中小企業白書によれば、中規模企業の経営者のうち、何らかの形で事業を引き継ぎたいと考えている人は、約6割にのぼります(参考:2014年度版中小企業白書)。しかし、実際には事業承継がうまくいかず、結果的に廃業を選択する人も多いのです。ここで、事業承継がうまくいかなかった理由としては、『将来の業績低迷が予測され、事業承継に消極的になった』との理由が大半を占めます。他にも、『後継者が見つからなかった』『事業承継に関して誰にも相談しなかった』という理由も挙げられました。
引用:事業承継の現実
事業承継は中小企業の継続、発展において重要なカギとなります。そしてこの問題を解決するために、弁護士へ依頼する中小企業が増えてきていますが、弁護士に依頼するメリットはどういったものなのでしょうか。
今回の記事では、事業承継をする上で弁護士に依頼する利点と費用、弁護士に依頼した場合の事業承継の手順などについてまとめてみました。
事業承継を弁護士に相談・依頼する3つのメリット
まず、早速ですが事業承継を弁護士に依頼するメリットについて確認していきましょう。
事業承継の時間が短縮できる
まず前提として事業承継を行うためには準備期間として5年~10年近くの年月を要すると思ってください。経営者の高齢化が進んでいる会社は特に、なるべく早期の段階から事業承継に取り組む必要がありますが、どのように準備を進めればいいのか、日常の業務に加えて手順を組み立てていくのは負担が大きいでしょう。
会社によって事業承継を進めるプロセスは異なりますが、弁護士に依頼することで、道筋が明確になり、事業承継の準備を円滑に進めることができます。
後継者の教育が捗る
特に事業承継において、時間がかかることは後継者への教育と、周囲からの理解を得ることです。例え後継者となる人間が、社内において生産性の高い人材でも、経営者として優秀とは限りません。
そのため後継者には経営の能力を身に付けさせるために、経営のノウハウや実務経験を与える必要があります。他社、自社の子会社、関連会社において、経営、部署を引率する経験をさせるのが一般的な手法です。
周囲への理解も深められる
事業承継をするにあたり、経営者が、親族、社内または社外の人間へ代わることになりますが、取引先や社内の人間の理解を得るために準備をしなければなりません。特に規模の大きくない会社においては旧経営者の人脈の元に取引先との関係を保っているケースが多いです。
また、親族経営の場合、他者からの買収(m&a)、社内の人間が事業承継をする場合、親族の人間から簡単に賛同は得られないでしょう。この通り、ある程度の時間をかけて、経営者の教育、周囲への理解を得ることになります。
会社経営の問題に関する取り扱い経験のある弁護士に依頼することで、過去の事例を元に手続きを進めることができるので、事業承継をスムーズに進めることが可能です。
自社の問題点・方向性が定まる
事業承継は時間のかかる手続きになりますが、同時にどのように進めていくべきかは会社によって異なります。
なるべく早く事業承継の準備に取り掛かるべきですが、弁護士に依頼することのメリットはどのような方向性で手続きを進めればいいのか、自社の抱える問題点を加味した上で、方向性が明らかになることです。
株式相続などに関する問題も解決できる
会社を承継させたい後継者が決まっている場合、後継者に事業承継させるためには高い保有率で自社株を所有している必要があります。
そのため、旧経営者が所有している株式を後継者へ、経営者の生存中に贈与、または遺言により株式を相続させることが一般的です。しかしながら、自社株式の移転は旧経営者の親族(相続人)の遺留分を侵害する危険性があります。
※遺留分:法律上、相続人へ確保された最低限の財産
そのため旧経営者の相続人に対する遺留分を侵害しないよう配慮する必要がありますが、事業承継の案件の取り扱いに慣れている弁護士に依頼することで、相続の問題に対処することができます。
弁護士に事業承継を依頼した際の費用
では、弁護士に事業承継を依頼した場合、どれくらいの費用が発生するのでしょうか。
相談料
料金形態は、候補者へ事業承継させるのか、他社から買収(m&a)してもらうのかで異なるのが一般的です。どの事業承継を選択されるのかは弁護士へ相談しながら決めていくことになりますが、相談時には相談料が発生します。
初回相談を無料している弁護士事務所もありますが、大体30分~1時間あたりにつき5000円が相場です。
候補者へ承継
候補者への承継を弁護士へ依頼した場合、事業承継の計画書の作成費用を負担することになりますが、承継させる純資産の額を元に算出されるケースが多いです。
各事務所によって料金の取り決め方も異なるため、大体の相場になりますが、事業承継の計画書の作成費用は以下の表を参照にしてください。
|
純資産額 |
費用 |
|
・300万円以下 |
10万円~12万円 |
|
・300万円超え、3000万円以下 |
16万円〜37万円 |
|
・3000万円超え、3億円以下 |
37万円~136万円 |
|
・3億円越え |
136万円〜 |
その他、旧経営者の相続に関わる案件を依頼する場合は、別途で費用が加算されます。
他社からの買収(M&a)
他社から買収される場合、主な弁護士費用は買収価格に応じて弁護士費用が換算されます。費用の相場として以下の表を参考にしてください。
|
株式譲渡(売却)価格 |
費用 |
|
・5億円以下 |
〜2500万円 |
|
・5億円超~10億円以下 |
2500万円超〜4000万円 |
|
・10億円超~50億円以下 |
4000万円超〜1億5000万円 |
|
・50億円超~100億円以下 |
1億5000万円超〜2億円 |
|
・100億円越 |
2億円超 |
弁護士に依頼する前に理解しておくべき!各承継方法の違いについて
次に事業承継にはどのような手続きがあるのか確認していきましょう。事業承継をするためには、親族への承継、従業員への承継、他社からの買収(m&a)の3つがあります。
親族への事業承継
親族への事業承継とは、文字通り親族の人間の誰かに経営権を託すことです。ひと昔前まで中小企業の事業承継では、親族へ事業承継させることが主流でしたが、親族へ事業承継させるメリットは、
-
関係者からの理解が得やすい
-
後継者の目星がつけやすく十分な教育期間を設けられる
-
株式移転が相続で行えるため遺留分問題・相続税対策に対処しやすい
になります。対し親族の人間に事業承継させるデメリットは以下の通りです。
-
社内の実務経験がなく事業・業務内容を理解していない
-
経営者としての素質のある後継者がいない
冒頭でも申しましたが、少子高齢化により適任の後継者が見つからないという課題があります。
従業員への事業承継
その反面、従業員へ経営権を託すことのメリットは、社内での実務経験が十分にあることでしょう。社内の従業員へ事業承継させるメリットをまとめると、
-
親族に限らず広く人材を候補者にすることが可能
-
社内の事業内容・業務内容に対する理解
の通りになります。反対に親族への事業承継と異なり、株式の移転に伴う問題があげられますが、従業員への事業承継をするデメリットをまとめると、
-
経営者としての素質があるとは限らない
-
株式を取得する資金力がない
-
旧経営者の融資の際の抵当が解除されない
-
相続人への遺留分への配慮
などがあげられます。承継に伴う株式の問題など後継者への事業承継に関して詳しくは以下の記事を参照にしてください。
他社からのm&A(買収)
m&aとは会社を買収することを意味しますが、m&aは他社の経営者へ会社の経営権を譲渡することで事業承継問題を解決する手法です。
他社の経営者が経営の舵を握るメリットは、自社を買収する経営者の手腕によってはより会社が発展する見込みがあることでしょう。他社からm&aをしてもらうメリットをまとめると、
-
会社の発展に繋がる可能性がある
-
会社売却の利益を経営者が得ることができる
-
債務の引き継ぎも可能
-
広く候補者を確保することができる
になります。反対にデメリットとして
-
買取価格が不十分な場合がある
-
承継後に旧経営者が経営に深く関わることが難しい
をあげることができます。
弁護士に依頼した場合の事業承継の手順
では最後に、弁護士に依頼した際の事業承継の流れについて確認していきましょう。
①会社の現状の整理
事業承継をするにあたり会社の現状を理解する必要がありますが、
-
後継者候補の有無
-
社内の資産内容
-
株の評価額
-
株式の保有状況
の確認を行います。もし、承継させたい候補者がいる場合、株式の保有状況を確認しなければなりませんが、それは候補者に経営権を譲渡させるにあたりどれくらいの株式が必要なのか明確にしなければならないからです。
また、先ほども説明した通り、他の候補者へ承継させるにあたり相続人の遺留分へ配慮しなければなりません。
そのため、株の評価額や資産内容の確認が必要になりますが、同時に株式の移転後の候補者が負担する相続税の問題を事前に対処するためにも株の評価額を把握しておく必要があります。
②事業承継の方法を選択
上記の内容を加味した上で、経営的素質が備わっている候補者の選択を行いますが、目ぼしい候補者がいない場合は他社から買収(m&a)してもらうことも検討しましょう。
上場していない企業の場合、事業承継ができないまま経営者が亡くなると廃業に追い込まれてしまいます。廃業のリスクを避けるためにも、m&aは一つの手段です。
③関係者からの理解を得る
事業承継の方向性が定まったら、今度は親族、取引先、社内の人間からの理解を得なければなりません。社内の人間の生産性を下げないためにも従業員からの理解は大切ですし、既存事業を引き続き運営するためにも取引先からの理解は必要です。
事業承継後の会社のプランを明確にした上で、廃業に追い込まれることのリスク、事業承継をすることのメリットを伝えましょう。
④後継者へ事業承継
(1)株式の買い取り
もし候補者へ事業承継させる場合は、候補者へ移転させることができる株が自社株の内、どれくらいの保有率(目安は2/3以上)になるのかを踏まえた上で、経営の主導権を握るために足りない株式を買い取る必要があります。
(2)後継者への教育
それと並行して、後継者への教育を進めることが必要です。経営者としての能力を身に着けさせるためにも、セミナーや本を介した勉強、子会社や関連会社において経営の実務経験をさせましょう。
(3)相続税対策
旧経営者が亡くなった後、候補者へは譲渡した株式による相続税が発生しますが、相続税が高額にならないために自社株の評価額を下げる試みが行われます。詳しくは「相続税対策:株価の引き下げ」を参照にしてください。
(4)個人保証・担保の解除
会社が融資を受けるために、経営者自身が人的担保、または自身の不動産を抵当にかけている場合は珍しくありません。
経営者を引退するにあたり、抵当を解除することができないことがありますが、弁護士と相談しながら抵当を解除していきましょう。
④他社からのM&A
他者からm&aしてもらえば、経営者が設定した担保を解除することが可能です。
そのため事業承継をするにあたりm&aを選択する中小企業も増えてきておりますが、他社から買収(m&a)をしてもらうためには、自社のブランド価値を上げなければなりません。
(1)自社の強みを理解する
そのためにはまず自社の強みを理解する必要があります。他社が自社を買い取る上で、どのような利点があるのか、自社の商材が魅力的、社員のパフォーマンス能力の高さなど、自社の強みを洗いだしましょう。
(2)社内の統制を強化
他社へ自社をより魅力的に見せるために、社内の統制を強化しましょう。各社員の役割が明確になっているのか、他の部門と円滑に業務連携できているのか、今一度、確認してください。
(3)買い手のニーズを知る
買い取り手のニーズとマッチングすることでm&aは成立します。そのため、買い取り先のニーズを知ることで、自社を必要としている候補の会社を絞りだすことが必要です。
主にm&aをする目的として、既存事業の拡大、新規事業の開拓などがあげられます。
まとめ
事業承継は数年単位でかかる手続きになりますが、早期の段階で準備を進めることが大切です。手続きをスムーズに行うためにも弁護士に依頼するのは効果的ですが、社内の問題を明らかにするためにも一度、弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。

◆即日交渉可◆LINE相談可◆電話で弁護士と直接話せる◆「今すぐ弁護士に相談したい!」という方はご相談を!LINEや電話で即日ご相談いただけます【男女間の金銭トラブルにも注力!】《解決実績は写真をクリック!》
事務所詳細を見る
【他事務所で断られた方歓迎|土日深夜も弁護士直通・LINEできる】男女トラブル・個人間の貸金回収は、早期の相談で回収率が大幅に変わります。迅速に対応します、ご相談ください。
事務所詳細を見る
【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

その他の債権知識に関する新着コラム
-
本記事では、債権について理解したい方に向けて、債権に関する一覧表、発生原因別・目的別の債権の種類、種類ごとの債権のルールや特徴、債権がもっている主な効力などにつ...
-
ロマンス詐欺は解決が難しい事件です。被害回復できる事案が限られるため、信頼できる弁護士への相談が大切といえるでしょう。中には着手金をだまし取るような行為をして二...
-
債権トラブルを抱えている場合、金銭債権について把握することも大切です。金銭債権は、債権債務関係における金銭の支払い請求権を指します。本記事では、金銭債権について...
-
お金を振り込んでから、振り込め詐欺に遭ったことに気づいたとしても諦めることはありません。振り込め詐欺救済法に従って手続きをすれば返金してもらえる可能性があるから...
-
結婚詐欺の被害は弁護士に相談、依頼することで、被害金を取り戻せたり、加害者の逮捕につなげられたりする可能性があります。本記事では、弁護士に相談できる窓口を紹介す...
-
インターネット上の詐欺被害に遭ってしまい、どこに相談したらよいのかもわからず、ひとりで悩んでいる方は多いのではないでしょうか。本記事では、詐欺被害の相談先や上手...
-
本記事では、LINEで詐欺被害に遭ってしまった場合の相談窓口を紹介します。 すでに被害に遭ってしまった場合はもちろん、疑わしいLINEグループに入れられ、個人...
-
振り込め詐欺に遭ったら、一人で悩まず、すぐにでも専門機関に相談することが重要です。警察や法律事務所、消費生活センターに相談することができます。本記事では、消費生...
-
2024年から新NISAが始まり、投資に関心を持つ方が増えています。投資を始めたばかりの方は、インターネット上で横行している投資詐欺に騙されないように注意すべき...
-
スマートフォン(スマホ)利用者をターゲットにした、いわゆる「スマホ詐欺」が横行しています。フィッシング詐欺もスマホ詐欺の一種です。本記事では、スマホ詐欺の代表的...
その他の債権知識に関する人気コラム
-
債権と債務の違いをわかりやすく図解します。相続・相殺・双務契約などの状況別に債権と債務の関係性をお伝えします。個人・法人に関わらず、まずは債権債務の理解を深めて...
-
債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...
-
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
-
今回の記事では、債権者代位権における、行使することで生じる効果、利用要件、またどのようなシチュエーションで行使されるのかについてまとめました。
-
債権者にとって債権者破産はどのようなメリットがあるのでしょうか。今回の記事では債権者破産がどのような目的で行われるのか、申立方法や申立要件など債権者破産について...
-
債権者保護手続きとは、債権者の利益を保護するための手続きです。主に会社分割や合併など組織再編をする際に、必要になります。通常の債権者保護手続は、官報公告と個別通...
-
投資詐欺の被害に遭ってしまった方は、「どうすればお金を返してもらえるのか」と悩んでいるでしょう。この記事では、投資詐欺の返金を受けるための方法や、そのために準備...
-
今回の記事では顧問弁護士を利用する上で発生する各費用の相場、費用に対して請け負ってもらえる仕事内容についてまとめました。
-
個人の方が顧問弁護士を利用するメリットはどこにあるのでしょうか。今回の記事では顧問弁護士を個人の方が利用するメリットや事例、顧問弁護士を利用する上での注意点につ...
-
今回の記事では、実際に債権者破産の申立をする上で、必要な申立方法や申立書類の作成方法、申立費用について解説していきます。
その他の債権知識の関連コラム
-
お金を振り込んでから、振り込め詐欺に遭ったことに気づいたとしても諦めることはありません。振り込め詐欺救済法に従って手続きをすれば返金してもらえる可能性があるから...
-
投資詐欺の被害に遭ってしまった場合は、早期に弁護士へ対応を依頼することで、被害金を回収できる可能性が高まります。投資詐欺に強い弁護士を選ぶ際に注目すべきポイント...
-
2024年から新NISAが始まり、投資に関心を持つ方が増えています。投資を始めたばかりの方は、インターネット上で横行している投資詐欺に騙されないように注意すべき...
-
今回の記事では顧問弁護士を利用するメリットとデメリット、それを踏まえた上で顧問弁護士を選ぶ上で確認しておきたいポイントについてまとめてみました。
-
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
-
詐欺被害に遭ってしまうと、どのように対応すべきか分からず、途方に暮れてしまう方がたくさんいらっしゃいます。被害者支援センターなどの窓口へ速やかに相談しましょう。...
-
債権トラブルを抱えている場合、金銭債権について把握することも大切です。金銭債権は、債権債務関係における金銭の支払い請求権を指します。本記事では、金銭債権について...
-
現在、まだ改正された法律の施行はされていませんが、今回の記事では債権者主義の解説、またどのような法改正がなされたのか、債権者主義が成立しそうな状況になった場合の...
-
投資詐欺被害に遭いお金を取り返したい人は、泣き寝入りする前に「弁護士事務所」へ直接相談し、取り返せるか判断してもらうことが解決への近道です。この記事では、投資詐...
-
本記事では、LINEで詐欺被害に遭ってしまった場合の相談窓口を紹介します。 すでに被害に遭ってしまった場合はもちろん、疑わしいLINEグループに入れられ、個人...
-
スマートフォン(スマホ)利用者をターゲットにした、いわゆる「スマホ詐欺」が横行しています。フィッシング詐欺もスマホ詐欺の一種です。本記事では、スマホ詐欺の代表的...
-
インターネット上の詐欺被害に遭ってしまい、どこに相談したらよいのかもわからず、ひとりで悩んでいる方は多いのではないでしょうか。本記事では、詐欺被害の相談先や上手...