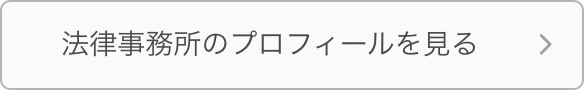顧問弁護士を利用するとどれくらいの費用がかかるのでしょうか。顧問弁護士にかかる費用は、月額あたりの顧問料、個別の案件を依頼した場合に発生する着手金、報酬金などがあります。
これから顧問弁護士の利用を検討されている方は、各費用の相場について気になっていると思いますが、今回の記事では顧問弁護士の費用相場から、費用を抑えるポイントについて紹介していきます。
顧問弁護士契約をご検討中の方へ
自分の会社は中小企業だから、顧問弁護士はいらないと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかしどんなビジネスであっても、取引や契約が発生します。
この取引や契約を円滑に行うには、様々な法律を理解しておく必要があるのです。
顧問弁護士契約を結ぶメリットには以下のようなものがあります。
- 日常的な法律問題を気軽に相談できる
- 法的トラブルを未然に防げる可能性が高まる
- トラブルが起きても対応がスムーズになる
- 企業の事情に合った、法務サービスを受けることができる など
法務トラブルを未然に防ぐことができれば、本業に取り組むことができるでしょう。
ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)では、顧問弁護士契約に対応可能な弁護士事務所を多数掲載しております。
まずは下記からご相談ください。
この記事に記載の情報は2023年11月13日時点のものです
顧問弁護士を利用する際の顧問料の相場と委託できる業務内容
顧問弁護士に依頼すると、基本料金として月額あたり顧問料が発生します。最初に、顧問料の相場から、顧問料の範囲内で弁護士に依頼できる業務内容について確認していきましょう。
顧問料の相場は3万円~5万円
日弁連の調査によると、顧問弁護士の顧問料は、全体の顧問弁護士に対して月額5万円で設定している弁護士が45.7%、3万円が40.0%、2万円が6.7%、10万円が5.7%です。

参照:「中小企業のための弁護士報酬の目安|日本弁護士連合会」
80%以上の顧問弁護士が顧問料を3万円に設定しています。月額顧問料は、大体3万円~5万円を相場だと思ってください。
顧問料内で委託可能な業務内容の範囲
顧問料の相場を確認した上で、顧問料の範囲内で任せることができる業務内容について確認していきましょう。
業務上における法律相談
まず、業務上における法律相談、アドバイスを受けることができます。実際のところ電話・メールでの相談に関しては制限を設けていない顧問弁護士が多く、対面による相談の場合、月々2~5時間までと制約がある場合が多いです。
契約書のチェック・内容証明郵便の作成
そして契約書のチェックや、簡易的な内容証明郵便の作成においては顧問料の範囲内で行ってもらえます。顧問料の範囲内で任せられる業務は、金額に見合った内容になります。そのため、費用に見合わない案件を依頼する際には、別途で料金が発生すると思ってください。
顧問弁護士に顧問契約外の業務を委託した場合の弁護士費用の相場
では顧問弁護士に顧問料の範囲外の仕事を依頼した場合の費用の相場を、確認していきましょう。顧問弁護士を利用していない方の弁護士費用の相場と比較しながら説明していきます。
書類作成の費用相場
取引先へ契約書や催告書を作成する機会はありますが、後の法的トラブルを避けるために弁護士に依頼することは一般的です。日本弁護士連合会の調査によると、顧問弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は大体5万円~10万円、顧問弁護士に依頼しなかった場合の費用相場は、5万円~15万円になります。
|
弁護士費用
|
顧問契約がある場合
|
顧問契約がない場合
|
|
5万円前後
|
49.0%
|
25.0%
|
|
10万円前後
|
21.4%
|
43.8%
|
|
15万円前後
|
2.3%
|
10.9%
|
|
20万円前後
|
3.9%
|
8.9%
|
|
30万円前後
|
0%
|
5.9%
|
|
0円
|
11.2%
|
-
|
|
その他
|
7.2%
|
3.9%
|
参考:「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」
労働事件の費用相場
不当解雇や長時間労働などで従業員から訴えられた場合(労働事件)、着手金、報酬金は、日弁連の調査によると以下の通りになります。
|
着手金
|
|
|
顧問契約がある場合
|
顧問契約がない場合
|
|
10万円前後
|
15.1%
|
3.6%
|
|
20万円前後
|
31.3%
|
11.2%
|
|
30万円前後
|
31.9%
|
46.1%
|
|
40万円前後
|
3.3%
|
9.5%
|
|
50万円前後
|
5.3%
|
18.8%
|
|
その他
|
1.0%
|
1.0%
|
|
報酬金
|
|
20万円前後
|
31.9%
|
18.1%
|
|
30万円前後
|
28.6%
|
25.0%
|
|
50万円前後
|
19.1%
|
33.2%
|
|
70万円前後
|
2.6%
|
6.9%
|
|
90万円前後
|
1.0%
|
3.3%
|
|
その他
|
3.0%
|
0.7%
|
参考:「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」
顧問弁護士に依頼した場合、着手金の相場は約10万円~約30万円、報酬金の相場は約20万円~約50万円です。対して顧問弁護士に依頼しなかった場合の費用相場は、着手金が約20万円~約50万円、報酬金の相場が約20万円~約50万円になります。
売掛金回収における着手金・報酬金の相場
中小企業が取引先へ2,000万円の売掛金回収を弁護士に依頼した場合の費用の相場について確認していきましょう。日弁連の調査によると、顧問弁護士に依頼した場合の費用の相場は、着手金が約50万円~約70万円、報酬金が約100万円~約150万円になります。
それに対して顧問契約のない弁護士に依頼した場合の費用の相場は、着手金が約50万円~約100万円、報酬金が約100万円~約200万円です。
|
着手金
|
|
|
顧問契約がある場合
|
顧問契約がない場合
|
|
50万円前後
|
53.3%
|
30.9%
|
|
70万円前後
|
20.7%
|
19.1%
|
|
100万円前後
|
12.2%
|
44.4%
|
|
120万円前後
|
0.3%
|
1.0%
|
|
150万円前後
|
0%
|
1.3%
|
|
その他
|
10.2%
|
1.6%
|
|
報酬金
|
|
100万円前後
|
35.2%
|
17.4%
|
|
150万円前後
|
29.6%
|
17.1%
|
|
200万円前後
|
26.0%
|
58.2%
|
|
250万円前後
|
1.0%
|
3.6%
|
|
300万円前後
|
0%
|
0.7%
|
|
その他
|
5.3%
|
1.3%
|
参考:「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」
以上のことから、顧問弁護士を利用することで一般の案件を安く請け負ってもらえることがわかります
顧問弁護士を利用するメリット
毎月、顧問料を支払ってまで顧問弁護士を利用するメリットはどこにあるのか、顧問弁護士を利用するメリットについて紹介していきます。
法的トラブルへの予防と迅速な対応
まず、顧問弁護士を利用するメリットの一つは、法的トラブルを未然に防止できることです。事業を運営していく上で、沢山の契約書を作成する機会があると思いますが、書類に不備があった場合、後の問題に発展しかねません。
顧問弁護士を利用していれば、気軽に契約書の確認をしてもらえるため、契約書の不備によって生じるトラブルを未然に防ぐことができます。
また、従業員からの不当解雇・残業代の訴え、回収できない不良債権の発生、消費者からのクレームなどの不測の事態は付き物ですが、顧問弁護士からアドバイスをうけることで、このような法的トラブルを未然に防ぐことが可能です。
他の依頼人より優先的に対応
予期していない法的トラブルが発生した場合、弁護士が案件を受任するまでには2週間近くの期間を要します。それに対して顧問弁護士の利用者は問題が発生した時点で弁護士に受任してもらえるためタイムラグが生じません。
法務部門を設立するより低額
自社の業務が法的なリスクを犯さないために法務部門を設立する会社は多いでしょうが、法務部門を設立すると人件費などのコストがばらになりません。そのため、規模の大きくない会社は、法務部門を設立しない代わりに顧問弁護士にリーガルチェックを依頼することで費用を抑えることができます。
企業の実情を踏まえた上でのアドバイス
顧問契約を結んでいない弁護士に依頼すると、会社の実情に適した解決方法を提示してもらえないことがあります。長期的にお付き合いをする顧問弁護士であれば、会社の実情に詳しくなるので、法的トラブルが発生した場合、会社に適した解決方法を提示してもらうことが可能です。
顧問弁護士の費用を抑えるためには?
では最後になりますが、顧問弁護士の費用を抑えるために必要なことについて確認していきましょう。
利用頻度の少ない法人はタイムチャージ制を利用する
会社によっては顧問弁護士をあまり活用しない会社も多いと思います。基本的に顧問料は年間契約で毎月、定額の費用を納めなければならないため、利用頻度の少ない会社にとって顧問料は割りに合わないでしょう。
そこで顧問弁護士の利用頻度の少ない会社はタイムチャージ制を利用するのが良いかもしれません。タイムチャージ制とは、顧問料を格安にする代わりに、顧問弁護士の利用時間に応じて月々の弁護士費用を換算する制度です。
タイムチャージ制は請求金額が不明瞭になりやすいので、月々の請求金額に注意する必要があります。
顧問料の積立制度を利用する
弁護士事務所によっては、顧問弁護士を利用しなかった月の顧問料を積み立ててくれます。積み立てた顧問料は、後の法的トラブルが発生した際の弁護士費用に回すことが可能です。顧問弁護士を活用する頻度が少ない企業は、顧問料の積立を行っている弁護士事務所へ依頼するのが適しているかもしれません。
顧問料が高額な顧問弁護士が有能とは限らない
顧問料の額に応じて業務内容の質が高くなると思われがちですが、実際はそうでもありません。多くの案件を抱えている弁護士ほど時間が足りていない分、高額な顧問料を設置する傾向にありますが、「忙しい弁護士=有能」とは限らないためです。
そのため、顧問料の高さで弁護士を選ぶことは危険で、以下で紹介する「費用に見合った顧問弁護士を選ぶ方法」を参考に弁護士を選ぶことをオススメします。
費用に見合った顧問弁護士を選ぶ方法
では、腕の立つ顧問弁護士を見つけるためにはどうすればいいのでしょうか。
同業他社から紹介してもらう
同業他社の経営者から紹介してもらうことは一つの手段です。同じ業種の会社の顧問弁護士として実績があるのならば、弁護士の質は担保されています。また、紹介ということもあり相手側の弁護士も丁寧に対応してくれるでしょう。
専門分野に適した弁護士に依頼する
また、会社の規模によって法律トラブルの性質は異なるため、会社の規模に適した法律の専門性に特化した弁護士に依頼するべきです。中小企業であれば債権回収、人事、労働問題に特化した弁護士、大企業であれば資金調達やM&Aの分野に特化した弁護士に依頼するべきでしょう。
自社のビジネスへの理解
顧問弁護士によって、過去に顧問を担当した企業の業務内容は異なるでしょう。自社の業務内容を早く理解してもらうためにも、自社の業務内容に近い会社の顧問経験のある弁護士に依頼するべきです。メール・電話などの無料相談を介して過去に顧問した会社の業務内容を弁護士事務所へ確認してみましょう。
まとめ
顧問弁護士を依頼する上で費用の相場は気になるところです。費用に見合った顧問弁護士を探すために今回の記事を参考にしていただけたらと思います。
顧問弁護士契約をご検討中の方へ
自分の会社は中小企業だから、顧問弁護士はいらないと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかしどんなビジネスであっても、取引や契約が発生します。
この取引や契約を円滑に行うには、様々な法律を理解しておく必要があるのです。
顧問弁護士契約を結ぶメリットには以下のようなものがあります。
- 日常的な法律問題を気軽に相談できる
- 法的トラブルを未然に防げる可能性が高まる
- トラブルが起きても対応がスムーズになる
- 企業の事情に合った、法務サービスを受けることができる など
法務トラブルを未然に防ぐことができれば、本業に取り組むことができるでしょう。
ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)では、顧問弁護士契約に対応可能な弁護士事務所を多数掲載しております。
まずは下記からご相談ください。