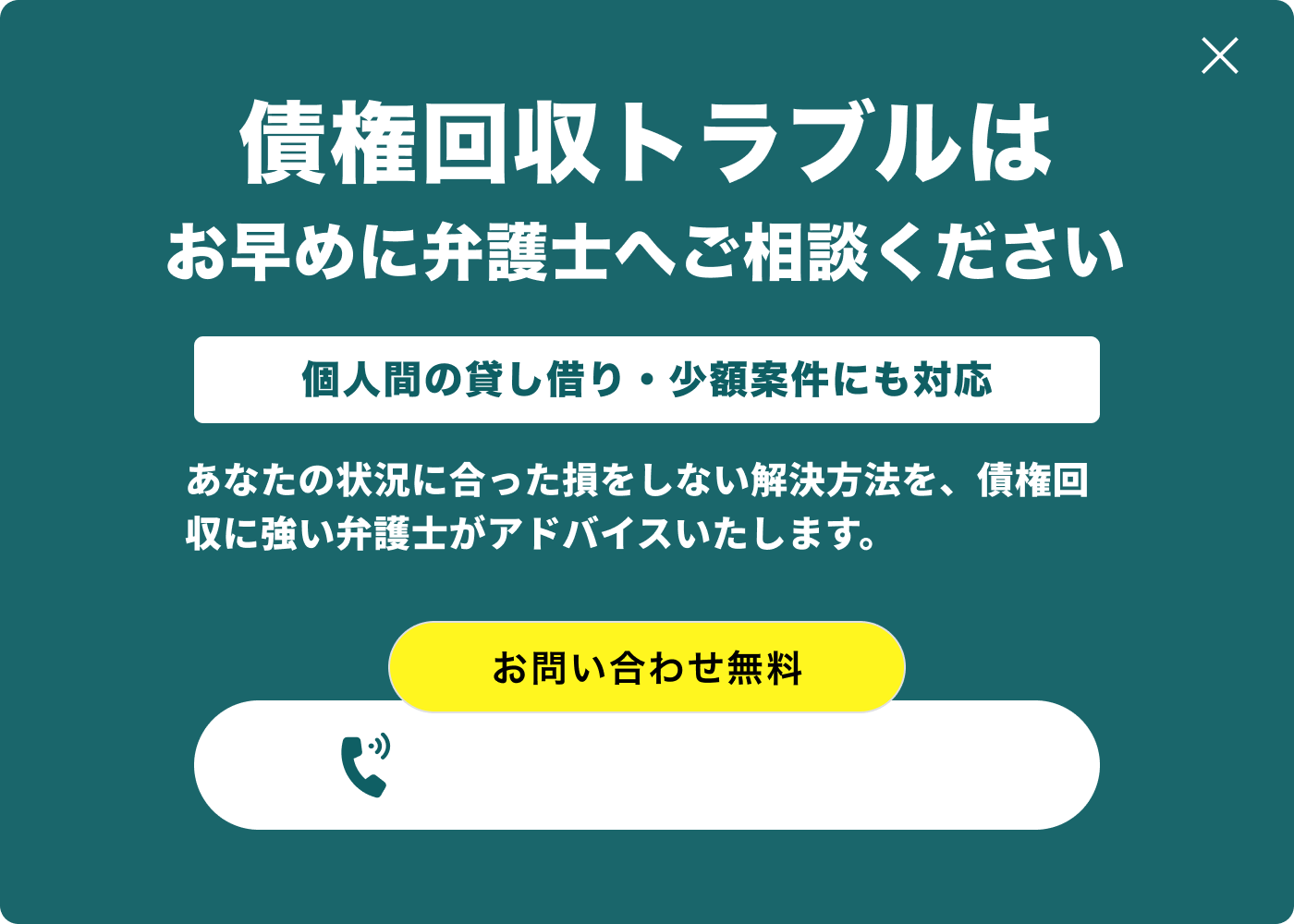弁護士へ依頼すると数十万~数百万の費用がかかる場合があります。
ベンナビ弁護士保険は弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険で、月額2,950円で幅広い法的トラブルで利用できます。
- 離婚
- 相続
- 交通事故(自転車事故)
- 近隣トラブル
- ネットの誹謗中傷 など
弁護士保険で法律トラブルに備える


スマートフォン(スマホ)利用者をターゲットにした、いわゆる「スマホ詐欺」が横行しています。
警察庁と金融庁は連名で、フィッシング詐欺とみられる不正送金被害が急増していることについて注意喚起をしています。フィッシング詐欺もスマホ詐欺の一種です。
スマホ詐欺にだまされないようにするためには、代表的なスマホ詐欺の手口を知っておきましょう。
また、万が一スマホ詐欺にだまされてしまった場合には、速やかに弁護士などへご相談ください。
本記事では、スマホ詐欺の代表的な手口や、被害に遭ってしまった場合の相談窓口などを紹介します。
スマホ詐欺の被害に遭ってどうすればよいか分からない方や、スマホ詐欺に遭わないように予防をしたい方は参考にしてください。
スマホ詐欺とは、スマートフォン(スマホ)利用者をターゲットとして金銭などをだまし取ろうとする詐欺です。
代表的なスマホ詐欺の手口・種類としては、以下の例が挙げられます。
「フィッシング詐欺」とは、著名な事業者(金融機関、ECサイト、携帯電話キャリアなど)や行政機関などを装って電子メールやSMSでリンク付URLを送り、クリックした人から暗証番号やパスワードなどを盗む詐欺手口です。
フィッシング詐欺の電子メールやSMSで送られてくるメッセージには、偽サイトへのリンク付URLが記載されています。
サイトの外観が実際に存在する著名な事業者や行政機関のものに似せて作られているため、一目では見抜きにくいケースも多いです。
偽サイトには通常、暗証番号やパスワードなどを入力する欄が設けられています。
ログインして通知などの内容を確認すべきではないかと不安に感じた人が、偽サイトに暗証番号やパスワードなどを入力すると、それが詐欺グループに転送されて盗まれてしまうという仕組みです。
特に、インターネットバンキングやクレジットカードの暗証番号などを盗まれてしまうと、不正出金や不正利用のきっかけになってしまいます。
「ワンクリック詐欺」とは、ウェブサイト上のリンクや電子メール・SMSなどのメッセージに記載されたURLをクリックしただけで、一方的にサービス入会などの契約成立を宣言し、多額の料金の支払いを請求するという詐欺手口です。
法的には、リンクやURLをクリックしただけで契約が成立することはあり得ません。
契約は当事者の合意によって成立するところ、リンクやURLのクリックだけで同意したことにはならないからです。
しかしワンクリック詐欺をおこなう詐欺グループは、あらゆる手段で相手の不安な心理に付け込んできます。
ワンクリック詐欺としてよく見られるのは、アダルトサイトや出会い系サイトなどの閲覧者をターゲットとしたものです。
こうしたサイトの閲覧者は、トラブルがあったことについて家族に知られたくないと考え、ワンクリック詐欺の請求に応じてしまうケースがあります。
また、「期限内に支払わない場合は訴訟を提起します」「高額の遅延損害金も併せて請求します」「ご自宅へ訪問して取り立てます」など、閲覧者の恐怖心を煽るような文言が記載されていることが多いのも、ワンクリック詐欺の特徴です。
実際に詐欺グループ側がこのような行動をとることはまずないので、ワンクリック詐欺の請求には絶対に応じないようにしましょう。
「サポート詐欺」とは、「あなたのサイトがコンピュータウイルスに感染しています。
問題を解決するにはこちらへ連絡してください。」などと虚偽の警告を表示し、不安に感じて連絡してきた相手に対して、サポート料などの名目で多額の金銭を請求する詐欺手口です。
サポート詐欺の警告画面には、実在の企業のロゴなどが使われているケースもよくあります。
また、警告音を鳴らす、警告メッセージを音声で流す、警告画面を閉じられないようにするなどして不安を煽るのが、サポート詐欺のよくある特徴です。
また、サポート詐欺をおこなう詐欺グループは、金銭を請求するだけでなく、セキュリティソフトを装って遠隔操作ソフトなどをインストールするよう誘導するケースもあります。
詐欺グループにスマホを遠隔操作されると、さらなる詐欺被害に遭う可能性が高まるので要注意です。
「当選詐欺」とは、何らかのキャンペーンなどに当選したという虚偽の事実を伝えたうえで、当選金の支払いに手数料が必要などと称して金銭をだまし取ったり、個人情報を入力させて盗んだりする詐欺手口です。
そもそも、キャンペーンなどに応募していなければ当選することはありません。
身に覚えがないのに突然「当選した」というメッセージなどが届いたら、間違いなく詐欺グループからのものと考えるべきです。
当選詐欺のメッセージなどを受け取ったら、決して返信せず、またメッセージ中のリンクもクリックしないようにしましょう。
「架空請求」とは、実際には購入していない商品や、利用していないサービスについて請求書を送り付け、お金を振り込むように求める詐欺手口です。
封書(手紙)で請求書を送りつけるのが古典的な手口ですが、近年ではスマホ利用者に対しても架空請求がおこなわれています。
身に覚えがない請求を受けたとしても、決してお金を振り込んではいけません。
スマホを通じた詐欺被害に遭った場合は、速やかに行政機関や専門家などへ相談することが大切です。
特に以下の4つの窓口は、スマホ詐欺の被害について幅広く相談に乗ってくれるので、いずれかの窓口へ速やかに相談しましょう。
消費者ホットラインは、一般消費者からの消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどについて、専門の相談員が対応する専用ダイヤルです。
消費者ホットラインに電話をすると、各都道府県の消費生活センターなどへ電話が繋がります。
土日祝日で消費生活センターなどが開所していない場合には、国民生活センターへ電話がつながります。
いずれの場合でも、専門の相談員からスマホ詐欺への対処法などについて一般的なアドバイスを受けることができます。
|
電話番号 |
188 |
|
公式サイト |
スマホ詐欺は犯罪行為なので、被害者は警察に相談することもできます。
警察に被害届を提出すれば、詐欺グループの捜査・摘発に動いてもらえる可能性が高いです。
警察に相談する際には、最寄りの警察署の窓口へ行く方法のほか、各都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口に連絡する方法もあります。
サイバー犯罪相談窓口では、主にインターネット上における詐欺被害などの相談を受け付けています。
|
最寄りの警察署 |
|
|
全国のサイバー犯罪相談窓口 |
|
|
警察相談専用電話 |
#9110 |
詐欺グループの銀行口座にお金を振り込んでしまった場合は、その銀行に対して速やかに連絡しましょう。
詐欺グループの口座を凍結してもらえるほか、振り込め詐欺救済法に基づく救済を受けられる可能性があります。
また、詐欺をきっかけとしてクレジットカードを不正利用された場合は、カード会社に対して速やかに連絡しましょう。
カードの利用を停止してもらえるほか、利用規約等に従い、不正利用金の引き落としを止められる可能性があります。
銀行やカード会社への連絡は、迅速におこなうことが非常に大切です。
詐欺被害に遭ったことが分かった時点で、速やかに銀行やカード会社に連絡しましょう。
法律の専門家である弁護士は、スマホを通じた詐欺被害全般に関する相談を受け付けています。
弁護士の大きな特徴は、被害者の代理人として問題解決に向けて尽力する点です。
詐欺グループに関する調査、被害金の返金交渉、訴訟の提起など、詐欺被害の回復に向けた対応は幅広く弁護士に依頼できます。
相談できる弁護士に心当たりがない方は、以下の窓口などへ連絡してみましょう。
【弁護士と相談できる主な窓口】
インターネットを通じた詐欺の被害について弁護士に相談したい場合は、「ベンナビ債権回収」を利用するのが便利です。
地域や相談内容に応じて、スムーズに弁護士を検索できます。
「ベンナビ債権回収」には、詐欺被害について無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されており、電話やメッセージにて直接の問い合わせが可能です。
詐欺被害に遭ってしまいお困りの方は、「ベンナビ債権回収」をご利用ください。
詐欺被害に関する特定の問題を解決したい場合は、以下の窓口に相談することも考えられます。
フィッシング詐欺の被害について注意喚起を促してほしい場合は、一般社団法人が運営する「フィッシング対策協議会」に連絡することが考えられます。
フィッシング対策協議会は、フィッシング詐欺の情報収集・提供や、注意喚起などの活動をおこなっています。
報道機関や関係府省などへの情報提供もおこなっているので、詐欺被害の深刻さを伝えることができれば、その状況を幅広く拡散してもらえる可能性があります。
|
メールアドレス |
info@antiphishing.jp |
|
報告フォーム |
|
|
公式サイト |
スマートフォンを通じた詐欺被害を未然に防ぐため、詐欺のメッセージが届かないようにするなど情報セキュリティに関する対策をおこないたい場合は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)に相談することが考えられます。
IPAが運営する「情報セキュリティ安心相談窓口」では、一般的な情報セキュリティ(主にウイルスや不正アクセス)に関する技術的な相談に対してアドバイスを提供しています。
詐欺メールを防げるスマートフォンの設定や、セキュリティソフトの導入などについてアドバイスを受けられるでしょう。
|
メール |
anshin@ipa.go.jp |
|
公式サイト |
海外事業者が運営するECサイトで詐欺被害に遭ってしまったときは、独立行政法人国民生活センターが運営する「越境消費者センター」に相談しましょう。
越境消費者センターの相談受付フォームに相談事項を入力すると、4~5営業日程度でトラブルへの対処法などに関する返信を受けられます。
また、海外事業者の所在国・地域に越境消費者センターと連携している機関がある場合は、当該連携機関に対して相談内容を伝え、交渉などを依頼してもらえる場合があります。
|
相談内容入力フォーム |
|
|
公式サイト |
通信販売に関する詐欺被害に遭ってしまった場合は、公益社団法人日本通信販売協会の消費者相談窓口に相談することが考えられます。
公益社団法人日本通信販売協会は、特定商取引法30条の規定に基づいて設立された法人です。
詐欺などの消費者被害についても、消費者団体や官公庁の消費者窓口と協力して対応しています。
|
電話番号 |
03-5651-1122 |
|
お問い合わせフォーム |
|
|
公式サイト |
詐欺的な内容の迷惑メールに困っている場合は、一般社団法人日本データ通信協会が運営する「迷惑メール相談センター」に相談することが考えられます。
迷惑メール相談センターでは、不特定多数の人に対して同意を得ずに送られる広告宣伝目的の迷惑メールに関する相談を電話で受け付けています。
迷惑メールの受信を停止するにはどうすればよいかなどについて、専門の相談員からアドバイスを受けることができます。
|
電話番号 |
03-5974-0068 |
|
公式サイト |
スマホ詐欺の被害について行政機関・警察・弁護士などに相談する際には、特に以下の3つのポイントに留意しましょう。
詐欺被害に遭ってしまったら、とにかくすぐに行政機関・警察・弁護士などに相談することが大切です。
銀行口座の凍結や返金請求などが遅れると、詐欺グループによる出金がおこなわれたり、詐欺グループが倒産したりして、被害金を回収できなくなってしまいます。
そうなる前に対応するには、早期の相談が必要不可欠です。
詐欺被害に遭ってショックを受けている状況でも、トラブルの解決に向けた迅速な対応をとるため、速やかに行政機関・警察・弁護士などへ相談しましょう。
詐欺グループとやり取りしたメッセージなどについては、できる限りすべてコピーして持参しましょう。
相談の際にメッセージの内容を見せれば、窓口担当者に状況を理解してもらいやすいです。
また、実際に詐欺グループに対して金銭を振り込んだ場合には、振込履歴などの資料も持参しましょう。
金融機関への連絡などを含めて、必要な対応についてアドバイスを受けられます。
詐欺被害に遭った状況については、相談窓口の担当者に対して順序だてて説明できるように、メモを作って時系列順にまとめておきましょう。
行政機関や警察は、事実関係が不明瞭な事案については対応してくれない可能性があります。
詐欺グループの摘発等に動いてもらえる可能性を高めるには、事前に事実関係を整理しておくことが大切です。
また、弁護士に相談する際には、相談時間が限られているケースが多いです。
あらかじめ事実関係を整理しておけば、相談時間の範囲内で有益なアドバイスを受けることができます。
詐欺被害で失ってしまったお金を回収するには、迅速な対応が必要不可欠です。
詐欺被害に遭ったことが分かったら速やかに弁護士などへ相談しましょう。
「ベンナビ債権回収」を利用すれば、詐欺被害への対応を得意とする弁護士をスムーズに探すことができます。
無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されているので、詐欺被害に遭ってしまいお悩みの方は、「ベンナビ債権回収」を通じてすぐに弁護士へご相談ください。

◆顧問契約のご案内も可◆企業の未収金回収・継続的なサポート◆倒産手続等の経験を活かし費用対効果も含めてご提案致します。◆ご相談はすべて面談形式で丁寧に対応!◆まずは写真をクリックしてご予約方法をご覧下さい。
事務所詳細を見る
◆100万円以上の債権回収に対応◆大手信託銀行の勤務経験◆元・司法書士、マンション管理士等も保有◆家賃滞納・明渡しの他、貸金・売掛金・請負代金のトラブルもご相談を。解決に自信があるからこその有料相談!
事務所詳細を見る
債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

本記事では、債権について理解したい方に向けて、債権に関する一覧表、発生原因別・目的別の債権の種類、種類ごとの債権のルールや特徴、債権がもっている主な効力などにつ...
ロマンス詐欺は解決が難しい事件です。被害回復できる事案が限られるため、信頼できる弁護士への相談が大切といえるでしょう。中には着手金をだまし取るような行為をして二...
債権トラブルを抱えている場合、金銭債権について把握することも大切です。金銭債権は、債権債務関係における金銭の支払い請求権を指します。本記事では、金銭債権について...
お金を振り込んでから、振り込め詐欺に遭ったことに気づいたとしても諦めることはありません。振り込め詐欺救済法に従って手続きをすれば返金してもらえる可能性があるから...
結婚詐欺の被害は弁護士に相談、依頼することで、被害金を取り戻せたり、加害者の逮捕につなげられたりする可能性があります。本記事では、弁護士に相談できる窓口を紹介す...
インターネット上の詐欺被害に遭ってしまい、どこに相談したらよいのかもわからず、ひとりで悩んでいる方は多いのではないでしょうか。本記事では、詐欺被害の相談先や上手...
本記事では、LINEで詐欺被害に遭ってしまった場合の相談窓口を紹介します。 すでに被害に遭ってしまった場合はもちろん、疑わしいLINEグループに入れられ、個人...
振り込め詐欺に遭ったら、一人で悩まず、すぐにでも専門機関に相談することが重要です。警察や法律事務所、消費生活センターに相談することができます。本記事では、消費生...
2024年から新NISAが始まり、投資に関心を持つ方が増えています。投資を始めたばかりの方は、インターネット上で横行している投資詐欺に騙されないように注意すべき...
スマートフォン(スマホ)利用者をターゲットにした、いわゆる「スマホ詐欺」が横行しています。フィッシング詐欺もスマホ詐欺の一種です。本記事では、スマホ詐欺の代表的...
債権と債務の違いをわかりやすく図解します。相続・相殺・双務契約などの状況別に債権と債務の関係性をお伝えします。個人・法人に関わらず、まずは債権債務の理解を深めて...
債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
今回の記事では、債権者代位権における、行使することで生じる効果、利用要件、またどのようなシチュエーションで行使されるのかについてまとめました。
債権者にとって債権者破産はどのようなメリットがあるのでしょうか。今回の記事では債権者破産がどのような目的で行われるのか、申立方法や申立要件など債権者破産について...
債権者保護手続きとは、債権者の利益を保護するための手続きです。主に会社分割や合併など組織再編をする際に、必要になります。通常の債権者保護手続は、官報公告と個別通...
投資詐欺の被害に遭ってしまった方は、「どうすればお金を返してもらえるのか」と悩んでいるでしょう。この記事では、投資詐欺の返金を受けるための方法や、そのために準備...
個人の方が顧問弁護士を利用するメリットはどこにあるのでしょうか。今回の記事では顧問弁護士を個人の方が利用するメリットや事例、顧問弁護士を利用する上での注意点につ...
今回の記事では顧問弁護士を利用する上で発生する各費用の相場、費用に対して請け負ってもらえる仕事内容についてまとめました。
今回の記事では、実際に債権者破産の申立をする上で、必要な申立方法や申立書類の作成方法、申立費用について解説していきます。
持株会社を使うことによってよりスムーズに、事業承継をすることが可能になってきます。 今回は、持株会社を設立して事業承継をする方法やメリットについて、解...
事業承継を行う上で、後継者の相続時の負担を減らす方法を紹介していきます。
投資詐欺に遭ってしまったという方は、弁護士に依頼することで返金してもらえるかもしれません。この記事では、投資詐欺の返金を弁護士に依頼するメリット・依頼時の費用・...
振り込め詐欺に遭ったら、一人で悩まず、すぐにでも専門機関に相談することが重要です。警察や法律事務所、消費生活センターに相談することができます。本記事では、消費生...
全国サービサー協会は、研修・検定の実施や苦情受付などを通して債権回収会社の適切な運営の確保を目指す団体です。本記事では全国サービサー協会の概要、協会に対して苦情...
今回の記事では顧問弁護士を利用するメリットとデメリット、それを踏まえた上で顧問弁護士を選ぶ上で確認しておきたいポイントについてまとめてみました。
仮想通貨をめぐっては詐欺トラブルなども発生しており、「絶対に損はしない」などと騙され、一切お金が返ってこないというケースもあるようです。仮想通貨で大損を被らない...
債権トラブルを抱えている場合、金銭債権について把握することも大切です。金銭債権は、債権債務関係における金銭の支払い請求権を指します。本記事では、金銭債権について...
もはや回収の見込みがない債権のことを不良債権といいますが、それでも少しでも多く回収しなければ損失となってしまいますので、できるかぎりのことをしましょう。この記事...
個人の方が顧問弁護士を利用するメリットはどこにあるのでしょうか。今回の記事では顧問弁護士を個人の方が利用するメリットや事例、顧問弁護士を利用する上での注意点につ...
債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...
事業承継を円滑に行っていくためには、今この瞬間から準備しておくべきことがたくさんありますので、ぜひこの記事をご覧いただき、早めの着手をしていっていただけたらなと...