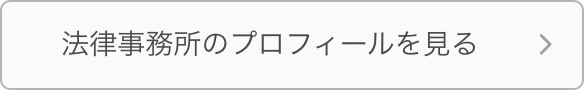未送付の請求書が見つかった際の内心は、穏やかではないでしょう。
「請求書を送付したつもりが、されていなかった」「うっかり出し忘れていた」など、さまざまな原因が考えられますが、すぐに未送付の請求書の支払い期限を確認しましょう。
請求書には時効があるため、時効が成立する前に更新の手続きをしなければ、売掛債権が消滅してしまう恐れがあります。
売掛債権の消滅時効は、割と短期で消滅してしまう権利の典型例です。
この記事では、請求書の時効期限や未送付の請求書が見つかった際に確認すべきこと、時効を更新する方法を紹介します。
相手が請求書の支払いに応じてくれない方へ
相手が請求書の支払いに応じてくれず、このまま時効を迎えるではないかと不安な方もいることでしょう。
時効が成立してしまえば、債権を回収することは出来なくなります。
請求書の時効でお悩みの方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリットは下記の通りです。
- 自身の状況に適した解決策のアドバイスをもらえる
- 相手にプレッシャーを与えることができる
- 裁判手続きなども任せることができる など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からお気軽にご相談ください。
請求書の時効は5年または2年
請求書の時効は、5年または2年です。
時効が異なるのは、令和2年に民法の大改正がされたからなのです。
売掛金が発生した時期によって時効の年数が変わるため、請求書の支払い期限をしっかり確認しましょう。
- 2020年4月以降に発生した売掛金は、新民法が適用 →「時効5年」
- 2020年3月以前に発生した売掛金は、旧民法が適用 →「時効2年」
|
たとえば、2020年10月に商品を納入したとします。
商品代金が「末締め、翌月末払い」の場合、支払い期限は2020年11月末日となります。
売掛債権、つまり請求書の時効は、支払い期限である2020年11月末日から5年後の2025年11月30日です。
2020年3月以前に発生した売掛金は、民法改正前の時効期間が適用されるので、「支払い期限から数えて2年」で時効となります。
未送付の請求書が見つかった際に確認すべき4つのこと
未送付の請求書が見つかった際には、落ち着いて以下の確認をおこないましょう。
- 自分以外の誰かが送付していないか確認する
- 本当に未入金であるか再度確認する
- 支払い期限の確認をする
- 時効の確認をする
|
自分以外の誰かが送付していないか確認する
同じ部署内の誰かが代わりに送付していないか、確認してみましょう。
代わりに送付したものの、あなたに報告をするのを忘れてしまっている可能性も考えられます。
また、紙ではなく、データで請求書を送っているケースもあるかもしれません。
本当に未入金であるか再度確認する
本当に入金されていないかどうか、再度確かめましょう。
請求書を出し忘れていた場合であっても、発注や納品などの一連の取引があった場合、「支払い義務があるから」と、入金する企業もあります。
入金している企業に対して、改めて請求書を送ってしまうとトラブルの原因になりかねません。
取引先との関係を良好に保つためにも、入金チェックは誤りのないよう何度も確認しましょう。
支払い期限の確認をする
支払い期限の確認も重要です。
改めて発行することで丸く収まるのか、あるいは、ずいぶん前に期限が過ぎているのかで、取るべき対応も変わってきます。
また、時効期間も支払い期限によって変わるため、よく見ておきましょう。
時効の確認をする
支払い期限から、時効の確認をしましょう。
チェック
- 売掛金の発生が2020年4月以降:時効5年
- 売掛金の発生が2020年3月以前:時効2年
「時効が過ぎてしまっている」と心配になった方もいるかもしれません。
時効期間が経過していても、諦めるには早いです。
なぜなら、相手方が「時効がきている」と主張しない限り、売掛金は発生している状態だからです。
相手方が時効の成立を主張するには、「時効の援用」という手続きをする必要があります。
「時効がきたので、売掛金は消滅しています」と主張する通知書を提出し、認められると時効は消滅となり、売掛金の請求はできなくなります。
つまり、時効の援用をしない限りは、時効期間が経過していても返済の義務は発生しているため、売掛金請求のお願いをする余地はあるのです。
時効期間が過ぎている場合でも、入金をお願いしてみましょう。
時効が未成立であった場合の対応方法
未送付の請求書の時効がまだきていない場合は、自社のミスを認め、誠意をもって対応することが重要です。
請求書の未送付について謝罪する
請求書の未送付について、相手方に謝罪をしましょう。
取引先と良好な関係を築くには、誠実な対応が必要不可欠です。
「請求書が未送付でも、取引はあったのだから支払ってもらって当然」と思うのではなく、未送付があった事実を詫び、今後同じことを繰り返さないよう努める旨を伝えましょう。
債務の確認をする
謝罪をしたうえで、債務の確認をします。
- 発注を受けた日
- 納入した日
- 納入した商品名
- 商品・製品の個数
- 商品代金
- 支払い期限
|
上記のような、取引に重要な項目を確かめて、承認してもらえるか伺いましょう。
承認された場合は、改めて請求書を発行し、入金のお願いをします。
承認されなかった場合でも、時効前のため、まだ請求は可能です。
送付が送れた分だけ支払い期限を延ばすなど、解決案を提案しながら、話し合いをしていきましょう。
話し合いをしても拒否されるようなら、法的手続きを検討するのも一つの手段です。
請求書の時効を更新する方法
「時効前なら請求書を送り続ければいいのではないか?」と考える方もいるかもしれませんが、請求書を送り続けたからといって時効が変わるわけではありません。
時効を更新するには、法的手続きをおこなうか、相手方に債務を承認してもらう必要があります。
- 裁判上の請求などで更新する
- 強制執行などで更新する
- 債務を承認してもらい更新する
|
裁判上の請求などで更新する
法的手続きをおこない、時効を更新する方法です。
以下のような法的手続きがあります。
| 法的手続き |
概要 |
|
訴訟の提起
|
訴えを起こして売掛金を請求する
|
|
支払督促
|
裁判所の書記官から支払いを命じる督促をしてもらう
|
|
民事調停
|
裁判官と調停委員に間に入ってもらいながら話し合う
|
たとえば、「売掛金が支払われていない」と訴訟を起こしたとします。
時効が更新するタイミングは、裁判で判決が確定したとき、または判決前に「和解」が成立したときです。
折り合いがつかないまま訴訟が終了した際は、時効は更新されません。
ただし、手続き終了時から6ヵ月間は、時効の成立が猶予されます。
強制執行などで更新する
差し押さえなどの強制執行を行い、更新する方法です。
強制執行の手続きをした場合は、手続きが終了したときに時効が更新されます。
仮差し押さえや仮処分については、時効は更新されません。
ただし、手続き終了後6ヵ月間は時効の成立が猶予されます。
債務を承認してもらい更新する
取引先に債務を承認してもらい、更新する方法です。
たとえば、時効期間内に取引先が「支払います」と言ったり、売掛金の一部を支払ったりした場合、債務を認めたことになり時効が更新されます。
債務の承認は、口頭だけでは後で「言った」「言わない」のトラブルに発展しかねません。
できれば書面を作成し、双方のサインを明記することをおすすめします。
今後請求書の未送付を防ぐために
取引先が多くなればなるほど、請求書の管理は大変になります。
しかし、未送付は本来あってはならないものです。
会社の損失につなげないためにも、また、今後の未送付を防ぐためにも、以下のような対策をおこなってはいかがでしょうか。
- 請求書に固有の番号を割り当てる
- 受注したタイミングで「請求予定」を入力する
- 請求書管理ツールを導入する
|
たとえば、取引の際に同封する「見積書」や「納品書」と、その取引にかかった「請求書」を同じ番号で管理すると、万が一、漏れがあってもすぐに割り出せます。
取引先ごとに、固有の番号を決めておくのも一つの方法です。
また、請求書管理ツールやシステムの導入も検討してみましょう。
請求書管理ツールを導入すると、見積書や請求書を作成・管理できます。
テンプレートが用意されているため、Excelで1から作成する必要はありません。
くわえて、印刷ではなくPDFデータとして添付送信も可能なため、印刷の手間も省けるでしょう。
まとめ|請求書を出し忘れた際は相手方に連絡を入れて新しい請求書を送付しよう
大量の請求書を管理する中で、「うっかり出し忘れている」請求書が見つかることもあるかもしれません。
未送付の請求書が見つかった際には、支払い期限や時効を確認したうえで、先方に連絡をとりましょう。
時効を更新する方法もご紹介しましたが、法的手続きは手間がかかり、双方が負担に感じてしまう可能性もあります。
誠意をもって謝罪し、新しい請求書を発行・入金してもらえないか交渉してみましょう。
相手が請求書の支払いに応じてくれない方へ
相手が請求書の支払いに応じてくれず、このまま時効を迎えるではないかと不安な方もいることでしょう。
時効が成立してしまえば、債権を回収することは出来なくなります。
請求書の時効でお悩みの方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリットは下記の通りです。
- 自身の状況に適した解決策のアドバイスをもらえる
- 相手にプレッシャーを与えることができる
- 裁判手続きなども任せることができる など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からお気軽にご相談ください。
参考:請求書を送ったのに滞納…催促方法を解説 |電帳法対応のファイルサーバー&文書管理システム