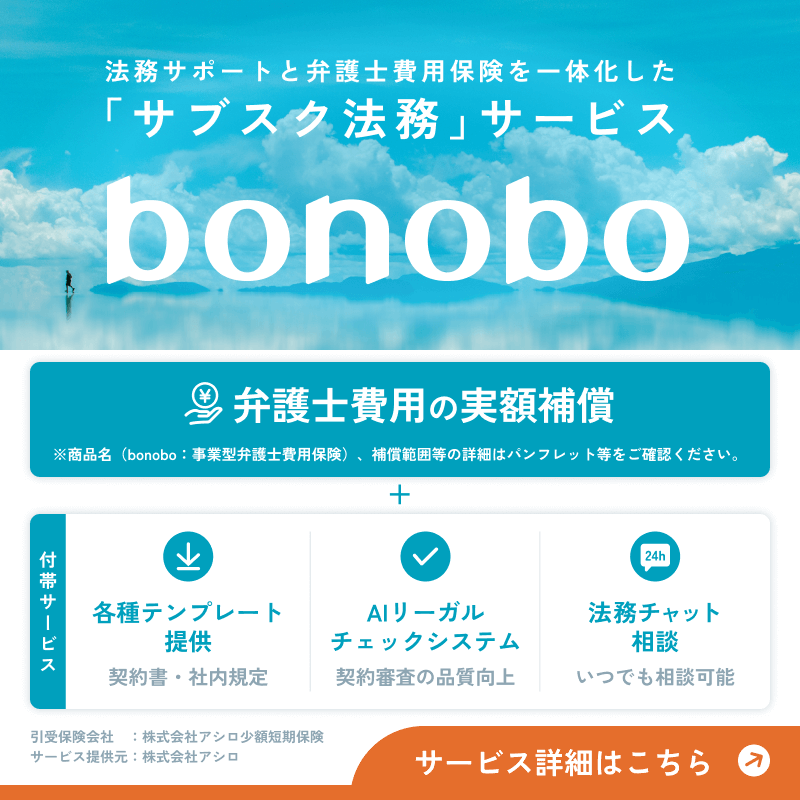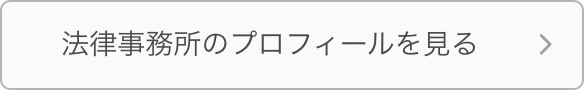分譲マンションでは、購入した居室(専有部分)以外に、エレベーター、廊下、エントランス、トイレの排水管といった、マンションの住民が共同で使用する「共用部分」が存在します。
全てのマンション所有者は、これら共用部分を日々管理するために、法律上当然に、これらの共用部分を管理する管理組合の構成員(組合員)とならなければいけません。
そして、組合員は、この共用部分を管理するための費用として、毎月一定額の「管理費」を支払わなければいけません。
ところが、マンションの所有者の中には、この管理費を支払わず滞納する人が出てくる場合があります。
ほとんどの場合、1・2ヶ月分の払い忘れ程度で終わりますが、中には3ヶ月、半年、一年と続く長期滞納者が出てくる場合もあります。
この長期滞納者がいるマンションの割合は、平成30年度マンション総合調査によると、3ヶ月以上の滞納で37%、1年以上の滞納で15.9%と、どのマンションで現れても決しておかしくない数値となっています。
管理費の滞納があったらどうなる?管理費の役割と滞納による影響
管理費って何に使われているの?
管理費とは、マンションのうち、エレベーター、廊下、エントランス、トイレの排水管といったように、マンションの住民が共同で使用する「共用部分」について、日々のメンテナンスのために、分譲マンションの所有者全員が毎月支払う金銭です。
また、ほとんどのマンションでは、管理費とは別に、長期修繕計画での大規模修繕工事のために積み立てておく「修繕積立金」を管理費と一緒に徴収しており、一般的に管理費という用語を使う場合、この修繕積立金も含む意味合いで使われることが多いです。
管理費滞納の長期化することによる影響
共用部分への悪影響
管理費の滞納が長期化すれば、当然、共用部分の日々のメンテナンスのための費用が足りなくなり、日常生活にも影響が出る場合があります。
また、共用部分の多くはエントランスや外壁といったように、マンションの居住者はもちろん、マンション外の人からも見える部分となります。
こういった部分のメンテナンスがおろそかになると、マンションの外観が悪くなり、組合員の当該マンションへの愛着が低下して売却してしまう、これからマンションの居室を購入する人が減少するなどにより、当該マンションの過疎化が進むきっかけになる場合もあります。
修繕積立金の融資への悪影響
大規模修繕工事には多額のお金がかかります。
この費用は、長年積み立ててきた修繕積立金から払うこととなりますが、それでも費用が足りない場合、住宅金融支援機構などから融資を受けて補填するなどの方策も必要です。
ところがこの融資を受けるには、マンション全体の滞納率が一定以下であることが条件として設定されています。
ですので、マンション全体の滞納率が高いと、いざ大規模修繕という時になって融資が受けられず、大規模修繕工事ができなくなる場合があります。
マンション管理状況の低評価
本来分譲マンションは、「管理を買え」というほど日々の管理が重要となります。
ところが日本では、マンションの管理状況を客観的に評価する基準がなく、管理状況がマンションの購入同機や資産価値に影響与えることはほとんどありませんでした。
しかし近年では、東京都がマンション管理状況の客観的基準を設けるとともに、各マンションがこの基準をどの程度遵守しているかを管理する「マンションの管理状況届出制度」を設け、この動きは他県にも広がっています。
この管理状況の中には、当然「管理費の滞納状況」も含まれています。
したがって今後は、管理費の滞納が多いと、当該マンションの購入が避けられて過疎化が進み、ひいてはマンションの資産価値が低下するなどの影響与えることとなるでしょう。
他の組合員との不公平
管理費は、組合員全員が平等に支払っているものです。
それにもかかわらずその中の1人が管理費を滞納し、しかもそれでなんのお咎めもないと、真面目に支払っている組合員との間で不公平感が発生し、最悪「それなら自分も滞納して大丈夫」と思われ、連鎖的に滞納が発生してしまいます。
管理費滞納問題における3つの傾向
1.督促できない、督促しても払ってもらえない
一般的に、滞納管理費の督促は、管理組合の理事が行うことが多いです。
しかし理事もそのマンションに住んでいる一般市民であり、督促のノウハウなどないのが通常です。
しかも、督促する理事と滞納者は共にマンションの住民であり、今後も長く付き合っていかなければならない関係上、理事としても強く督促しづらいという問題があります。
中には、滞納者の方がこのような関係を逆手に取り、督促する理事に対し強気に出る場合もあります。
結果的に、理事からはほとんど催促できない、催促できたとしても非常に弱々しい催促で、なかなか支払ってもらえない、という事態が多発します。
この点、マンション管理会社の担当者が理事に代わって督促する場合もありますが、マンション管理会社の担当者は管理組合のメッセンジャーを超えて、代理人として督促することは法律上認められていません。
ですので、滞納者との間で何かトラブルが生じた場合、結局理事が矢面に立たなければならず、上記問題の根本的解決にはなりません。
2.督促先がわからない
滞納管理費については、督促を躊躇してしまうという場合だけでなく、そもそも誰に督促すればいいのかわからないという場合もあります。
例えば、組合員が亡くなり、相続人が誰なのかもわからない、という場合です。
相続人の特定には高度な法律問題を含むことが多いため、理事では相続人が誰か判断がつかず、誰に対して督促していいのかわからない、という場合も珍しくありません。
3.自分以外の誰かが解決するだろうと放置してしまう
上記の通り、理事としても管理費の督促など普通はやりたくないものです。
しかも、理事は数年で交代することも多いので、「自分が解決しなくても、次の人がうまくやってくれるだろう」という考えのもと、放置してしまうことが多々あります。
結果、「これ以上放置すると取り返しのつかないことになる」というほど滞納が長期化した段階で、初めて問題解決に向けて本格的に動き始める、ということも珍しくありません。
管理費滞納の請求には消滅時効がある
管理費の時効は、通常、管理費の発生から5年です。
ただし、滞納管理費を裁判で請求し、債務名義を取得している場合、裁判で請求した管理費については、裁判が確定した時から10年となります。
このような特殊な処置をとっていなければ、滞納期間が5年を経過しそうな場合、時効を更新する方策を取らなければなりません。
時効の更新の方法としては、債務の承認、裁判上の請求といった方法があります。
なお、管理費の一部を支払っていた場合、支払った時点で時効が更新する場合があります。
ただし、常に時効が更新するわけではなく、支払ったときの状況次第では、時効の更新が認められない可能性もあります。
ですので「最近管理費の一部が支払われたから当面時効は大丈夫」と安心するのは危険です。
発生から5年が経過しそう、あるいは経過してしまった管理費がある場合、速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。
管理費を滞納している人への対応の4つの流れと法的処置
1.管理会社に連絡し、催促してもらう
管理組合と管理会社との管理委託契約では、滞納から6カ月間の督促は管理会社の業務となっていることが多いので、滞納初期の督促は、管理会社にお願いすることが考えられます。
ただし、管理会社は、法律上、管理組合の代理人とはなれないため、分割弁済の交渉などはできません。
あくまで管理組合のメッセンジャーとして通知書を出したり、機械的な督促を行えるに過ぎませんので、注意が必要です。
2.内容証明郵便による催促を行う
通常の督促でも相手方が払ってこない場合、内容証明郵便を使って督促をすることが考えられます。
ただし、ただこれまでと同じ督促内容を内容証明郵便で出すだけでは督促として十分とはいえません。
内容証明郵便での督促は最後通告であり、それでも支払ってこなければ、今度は裁判手続に移行することも併せて伝えるなど、組合の本気度を伝えることが、内容証明郵便で督促する上で重要となってきます。
3.裁判手続
内容証明郵便でも支払ってもなければ今度は裁判手続によって督促することが考えられます。
裁判手続には、支払督促、少額訴訟、通常の訴訟手続など、多様な方法がありますので、問題となっている滞納の状況に応じて、適切な方法を選ぶことが重要となってきます。
4.強制執行(差押)
裁判で勝訴判決が出ても相手方が支払ってこなければ、最終手段として、相手の財産を差押さえて、その財産を換価した金銭から滞納管理費を回収することとなります。
差押財産には、預金、給与、動産、不動産などがありますが、管理費の場合、滞納者は確実にマンションを持っていますので、強制執行のしやすい債権といえます。
管理費の滞納の予防や再発防止策
管理費を滞納した場合の処理をマニュアル化しておく
上で述べたように、管理組合で滞納者への督促が充分にできない理由としては、いつから、どういう風に督促すればいいのか、そういった督促のノウハウの不足が大きな要因です。
ですので、あらかじめ理事会などで、督促が生じた際には、何時から、どういう風に督促を進めていけばいいのか、督促マニュアルを作成しておくと効果的です。
その際、理事の裁量を広く認めるマニュアルにすると、理事としてはどうしても「自分が理事の間は督促を控えたい」という方向に気持ちが働きやすくなります。
そこでマニュアルでは、この期間滞納が続きたらこの書面を送る、この期間滞納が続いたら弁護士に相談する、裁判手続に移行するなど、できる限り理事の裁量をなくすようにした方が、新任の理事でも督促を進めやすく、また滞納者に対しても「決まっていることなので」と説明しやすくなります。
滞納した場合の罰則を定め、その内容を周知しておく
滞納した場合の罰則には、マンション居住者に管理費の滞納をさせないという予防効果と、いざ滞納が発生した場合でも、管理組合が当該督促に支出した費用を補填できるという2つの効果があります。
罰則の内容としては、法定利率以上の遅延損害金の付与、弁護士に委任した場合や裁判手続に移行した場合にその費用を全て滞納者負担として請求する、などが考えられます。
なお、滞納者をマンション住民に公表するという罰則は、たとえ管理費を滞納していても、滞納者のプライバシーとの関係から、管理組合が滞納者に損害賠償を請求される可能性があるので、控えた方がいいでしょう。
これらの罰則は、単に理事会や総会で決定しただけでは効果が発生せず、規約によって定めなければならない場合もあることに注意が必要です。
管理費滞納を弁護士に依頼したことによる解決事例
<回収例1>一括回収
【委任前の状況】
受託時の滞納期間は12か月(約40万円)
滞納者とは連絡が取れているものの、滞納者は「銀行からの借金を優先して返済しており、管理費は後回し」と言っており、払う気を見せていなかった。
【弁護士による対応】
①受任後
受任通知発送
②受任から2週間後
滞納者より「資金を用立てて近々支払う」との連絡があり。
③受任から約1ヶ月半後
一括回収
【ポイント】
滞納者は単に滞納するばかりか、理事に対して滞納を正当化するかのごとく強気にでていました。
ところが弁護士からの受任通知を見た途端、滞納者より弁済したい旨の連絡がありました。
弁護士からの受任通知を見て、管理組合が本気になったと悟って、支払を真剣に考えたと考えられます。
<回収例2>分割弁済による回収
【委任前の状況】
受託時滞納期間は70か月(約250万円)
マンション居室には居住しているものの、管理会社からの督促には一切反応なし。
【弁護士による対応】
①受任後
受任通知発送
②受任から約1週間後
滞納者から「2ヶ月後からの分割弁済とさせて欲しい」との連絡があったので、弁護士から滞納者に、具体的な分割弁済案を提示するよう回答。
③受任から約3ヶ月後
滞納者から10万円の弁済と共に分割返済案の提示があったので、当方から管理組合に分割返済案の検討を依頼。
④受任から約4ヶ月後
管理組合が分割返済案を了承し、分割返済が始まる。
【ポイント】
管理会社からの督促には全く反応がない状況でしたが、弁護士からの受任通知を送付すると、すぐに滞納者から分割返済の申出がありました。
分割返済となった場合、完済までの入金管理、不履行時の督促等含めて、全て弁護士の方で行います。
管理組合で分割案を受け入れる場合、その後の入金管理なども全て弁護士がやってくれることが決めてとなる場合も多いです。
<回収例3>相続人からの回収
【委任前の状況】
滞納期間は26か月(約54万円)
区分所有者は死亡しており、マンション居室は空室
相続人の一人とは当初連絡がとれていたが、突然音信不通となる。
【弁護士による対応】
①受任後
戸籍謄本等の請求により、相続人調査を開始。
②受任から約2ヶ月後
全相続人とその住所が判明したので、相続人宛に通知を発送。
③受任から約3ヶ月後
相続人から「翌月には支払います」との回答あり。
④受任から約4ヶ月後
一括回収
【ポイント】
亡くなった区分所有者の親族が協力してくれる場合は格別、そうでない場合、管理組合や管理会社が相続人調査をするのは困難です。
弁護士の場合は、受任事件であれば亡くなった区分所有者の戸籍謄本から相続人を調査し、更に相続人の住民票等を調査して、相続人に連絡を取る事ができます。
本件も、受任後に相続人調査を行った事で、相続人とコンタクトがとれ、一括回収に至りました。
最後に
滞納管理費の督促においては、管理組合が法律に詳しくない一般市民で構成されており、滞納者との交渉において専門の知識を有していないことがほとんどです。
特に、滞納から6ヶ月を経過すると、滞納額が高額となり、専門の知識がないと回収が困難となります。
他方で滞納管理費は、専門の知識があれば長期滞納であっても回収できる確率が非常に高く、また、弁護士に依頼をしても弁護士費用は少額で済むことが多い債権でもあります。
ですので、滞納から6ヶ月を経過してしまったら、一度、弁護士への相談を検討することもお勧めいたします。
今回の記事を通して、管理費の滞納に困っている管理組合のお役に立てたらと思います。

【投資詐欺に注力!】【相談料0円】経験豊富な弁護士があなたの代わりに返金請求◆「詐欺かも?」と感じたら、すぐにご相談を!詐欺被害者のご家族からのご相談も承っております◆身元の特定や振込先の口座凍結も可能です!
事務所詳細を見る
占い・出会い系・支援金・副業などの詐欺被害に多数の豊富な解決実績|「詐欺被害を誰にも打ち明けられずにいる」「頻繁に高額な支払いを要求される」などのお悩みはぜひご相談を◆企業の弱点を突く独自の交渉戦略で最善の結果を目指します【全国対応|面談無料】
事務所詳細を見る
【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

差押え・強制執行に関する新着コラム
-
借金が返済されなかったり、売掛金が支払われなかったりすると、債権者は民事訴訟などの法的措置によって債権回収を目指す必要があります。そこで本記事では、金銭債権を有...
-
仮差押えは、債権を回収するための一時的な措置ですが、仮差押えには供託金が必要になります。本記事では、仮差押え手続きにおける供託金の基礎知識や、還付の大まかな流れ...
-
債権トラブルを抱えている場合、仮差し押さえをしておくのもおすすめです。仮差し押さえをすれば、裁判勝訴後に債権回収できる可能性が高まり、迅速な解決が目指しやすくな...
-
給料を差し押さえるには裁判所での手続きが必要であり、上限額なども定められています。スムーズに回収手続きを済ませるためにもポイントを押さえておきましょう。本記事で...
-
第三債務者とは、例えば債権者Aに対して債務をもつ債務者Xに対してさらに債務をもつ債務者Yのことを指します。差し押さえのよる債権回収を行うにあたっては本来の債務者...
-
なんとか回収をする場合に検討したいのが、時効の更新・完成猶予によって、時効の主張をされるのを止めることです。 その一つの原因となるのが「仮差押え」です。この記...
-
養育費を差し押さえるための条件から手続き、差し押さえ前に必ず知っておいてもらいたい注意点などをまとめました。
-
借金の返済に応じない相手には、強制執行により給料や財産を差押さえることができます。この記事では、差押えの手順と差押えられる金額の範囲についてご紹介します。
-
マンションの所有者の中には、この管理費を支払わず滞納する人が出てくる場合があります滞納問題に管理組合が取るべき4つの解決策について、弁護士が詳しく解説いたします...
-
差し押さえを弁護士に依頼した場合にどのようなメリットがあるのか、弁護士に依頼すべき理由、弁護士費用について解説します。
差押え・強制執行に関する人気コラム
-
強制執行を完了させるまでの流れは差押えする財産によって変わります。今回の記事では大まかな強制執行の流れや費用倒れしないための知識について解説します。
-
差し押さえは、交渉での債権回収が困難な場合の最終手段として使われる法的手段です。差し押さえを行うために必要な費用や、手続き方法について、詳しくご紹介していきます...
-
差し押さえは、債権回収の法的手段の一種で最終手段として使われます。それにより、不動産や預金、給与などの財産から強制的にお金を支払ってもらうことができます。この記...
-
強制執行にかかる費用は、対象となる財産によって費用が違います。今回の記事では、強制執行を申し立てる上で必要な裁判所費用や弁護士費用、費用倒れしないためのポイント...
-
給料を差し押さえるには裁判所での手続きが必要であり、上限額なども定められています。スムーズに回収手続きを済ませるためにもポイントを押さえておきましょう。本記事で...
-
申立書とは裁判や調停を行う際に裁判所等に提出する書類を指します。今回の記事では、支払督促を行う上で、簡易裁判所に提出する際の申立書の書き方を中心に、申立に必要な...
-
今回の記事では、強制執行停止の手続きの方法から手順、手続きを行う上での注意点などを紹介していきます。また差し押さえを目的とする相手側の動きを知るためにも強制執行...
-
差し押さえを行うのに一体いくらかかるのか?また、その費用は抑えられないのか?という気になる点を、本記事で解説していきましょう。
-
合法的且つスムーズに強制退去させる方法を模索している人向けに、強制退去に至るまでの流れや注意点などをまとめました。強制退去は、法律厳守が重要です。弁護士に強制退...
-
今回の記事では、債権者の方が、債務者の財産を差し押さえる上での強制執行における基礎知識、手続きを完了させるために必要なことや手順について紹介していきたいと思いま...
差押え・強制執行の関連コラム
-
差し押さえを弁護士に依頼した場合にどのようなメリットがあるのか、弁護士に依頼すべき理由、弁護士費用について解説します。
-
第三債務者とは、例えば債権者Aに対して債務をもつ債務者Xに対してさらに債務をもつ債務者Yのことを指します。差し押さえのよる債権回収を行うにあたっては本来の債務者...
-
債務名義の取得方法についてまとめました。また債務名義の取得方法は多数あるため、どの方法で手続きを行うべきか悩む方もいるでしょう。そこで状況別に適した債務名義の取...
-
養育費を差し押さえるための条件から手続き、差し押さえ前に必ず知っておいてもらいたい注意点などをまとめました。
-
不動産を差し押さえするために必要な事前知識や、申立の手順について説明していきます。
-
強制執行を完了させるまでの流れは差押えする財産によって変わります。今回の記事では大まかな強制執行の流れや費用倒れしないための知識について解説します。
-
不動産執行とは強制執行制度のこと。この制度を使えば債務者(借金をしている人)からお金を取り戻すことも可能です。当記事では、不動産執行のメリットやデメリット、流れ...
-
今回の記事では、強制執行をするのに必要な手続きの流れに加え、確実な債権回収をする方法、また強制執行される側の債務者の方に向けて強制執行を停止する方法について紹介...
-
財産の種類ごとにおける債務者の財産を差し押さえる方法、差押えを成功させるための必要事項を紹介していきます。
-
今回の記事では、強制執行停止の手続きの方法から手順、手続きを行う上での注意点などを紹介していきます。また差し押さえを目的とする相手側の動きを知るためにも強制執行...
-
合法的且つスムーズに強制退去させる方法を模索している人向けに、強制退去に至るまでの流れや注意点などをまとめました。強制退去は、法律厳守が重要です。弁護士に強制退...
-
今回の記事では、債権回収を外部に代行するために、回収業務を行っている専門家・業者の説明から、抑えておきたい債権回収の知識などについて紹介していきます。