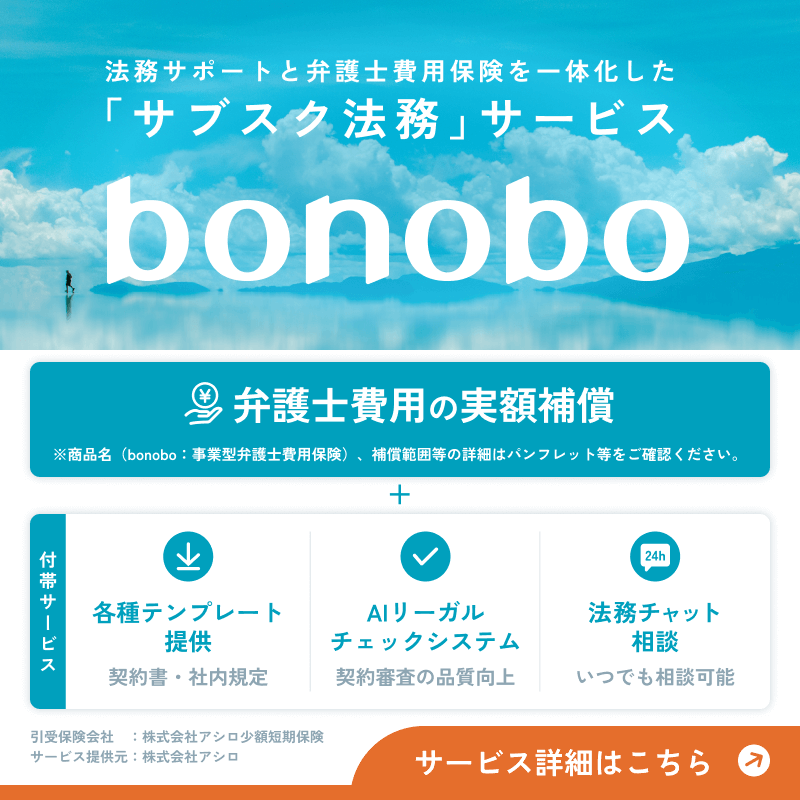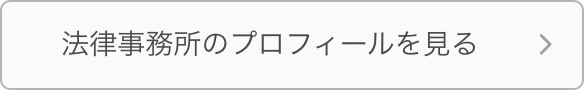無断キャンセルに頭を悩ます飲食店や、レストランの経営者は少なくないでしょう。無断キャンセルが発生すると売上が下がるだけでなく、食材も無駄になり、その時間に予約したかった他のお客さんにも迷惑がかかります。
では、無断キャンセルの割合を減らすために、飲食店やレストラン側はどのような対策すればよいのでしょうか。この記事では、無断キャンセルへの対策や、無断キャンセルが発生した場合の対処法をご紹介します。
無断キャンセル料を回収したい方へ
無断キャンセルが続いてしまうと、積り積もって大きな損害になり得ます。時効もありますので、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、債権回収することをおすすめします。
弁護士を通して内容証明や督促状を送ることで、裁判等を行わなくても回収できる可能性があります。
無断キャンセル料の時効が成立してしまう前に、ご相談ください。
無断キャンセルを減らす対策①【事前準備編】
まずは、無断キャンセルによる損失を減らすための事前対策をご紹介します。
現状を数値で把握する
無断キャンセルによる損失を減らすためにできることは、以下の2点です。
- 前提として無断キャンセルの割合を減らすこと
- 1回のキャンセルで発生する損失を抑えること
これらのことを実現するには、キャンセルの割合とキャンセルにより発生する損失を数値化することが重要です。
例えば、1日の予約数を20件と設定した場合、キャンセル率15%なら毎日3件のキャンセルが発生している計算になります。平均客単価が4,000円程度として、1日で1万2,000円、ひと月の営業日を1ヶ月あたり26日(週1日の定休日)とすると、31万2,000円の損失が発生している計算です。
もし、1日1件のキャンセルを防止できるとしたら、【4,000円×26日=10万4,000円】の損失を防げることになります。
デポジット決算を導入する
予約受付に対して、予約の段階で手付金を受け取る制度(デポジット決算制度)を設けると、キャンセルによる損害を減らすことができます。
ただし、予約に対するハードルが高くなるので、予約注文の数は減るかもしれません。この制度を導入する場合は、導入により減少した予約注文の数を計測した上で、本格的な導入を検討しましょう。
『トレタ』が提供する顧客台帳サービスを利用すると、デポジット決算が簡単に導入できます。
参考:「トレタ」
キャンセル料に関する規約を明記する
ネット予約では、直接顔を合わせることがありません。そのため、キャンセルに対する罪悪感が薄れがちです。無断キャンセルを減らす上で、キャンセル料の規約を設けることが重要です。規約の内容は、ネット予約の場合は予約の投稿画面に表示し、電話予約の場合は口頭で伝えるとよいでしょう。
仮予約・自動キャンセルの制度を設ける
中には予約を入れた日時に別の予定が入ってしまったが、連絡を忘れたために、無断キャンセルしてしまう人もいます。事前にキャンセルすることがわかっていれば、対処のしようもあるでしょう。このようなケースに備えて、仮予約制度を設けることをおすすめします。
具体的には『指定の日時までに連絡がもらえない場合は予約を自動キャンセルする』、『連絡がもらえた場合は予約が確定する』というような仕組みを設ければ、連絡もれによる無断キャンセルを防止できます。
無断キャンセルを減らす対策②【予約から来店までの流れ】
続いて予約から来店までの流れに沿って、無断キャンセルを減らすためにできる対策をご紹介します。
新たに食材調達が必要なメニューは予約で受けつけない
無断キャンセルで最も困るケースは、新たに食材調達が必要なメニューを予約された場合です。他のメニューに代用できず、お客からのオーダーもない場合、仕入れた食材が無駄になります。
そのため、食材が他のメニューに代用できないものは予約の段階では受けつけないようにしましょう。また、複数のメニューに代用できる食材をベースにして、予約用のメニューの構成を考えることも有効です。
予約時に必ず電話番号とメールアドレスを確認する
予約時に必ず相手の氏名、電話番号、メールアドレスを確認しましょう。
当日キャンセルをすることに対して、心理的プレッシャーを与える効果が期待できます。また、個人情報を取得しておくことは、のちのち大きな意味を持つことになります。こちらについては、後述します。
予約時間の前日か数時間前に通知する
無断キャンセルの多くは、予約を入れたことを忘れていたために起こります。当日忘れられないように、予約日が近くなったら相手に電話などで通知をしましょう。
無断キャンセルが発生したときの対処方法
実際に無断キャンセルが発生した場合の対処方法をご紹介します。
キャンセルにより余った食材で作れる料理を宣伝する
キャンセルによって余った食材を無駄にしないために、事前に対策をしておきましょう。
あらかじめキャンセルが発生した場合に備えた、その食材で作れる別の料理メニューを考えておくことや、看板・SNSで宣伝することも大切です。
SNSを用いて空席案内をする
空席を埋めるために、SNSに空席情報を投稿しましょう。SNSのフォロワーの中には、空席を探している人がいるかもしれません。
キャンセル客のブラックリストを作成する
キャンセルした人をリストにまとめましょう。
リストがあれば、また同じ人から予約を受けた場合、キャンセルされた場合に備えることができます。自社で作成したブラックリストを他の飲食店と共有すると、キャンセル客のデータを効率的に集められます。
ドタキャン客に対してはキャンセル料の請求が可能
予約したのに当日現れない‟無断キャンセル”をした客に対して、損害賠償を請求したい方もいるでしょう。
予約の段階で契約は成立していると考えられます。つまり、飲食店側は無断キャンセルによる損害を受けたと考えることができるため、債務不履行として、キャンセル料の請求や損害賠償を主張できます。
このあたりの具体的な内容を、無断キャンセルの請求に詳しい『まちだパートナーズ法律事務所』の町田北斗先生にお聞きしました。

旅館・ホテルや飲食店や旅行料金など、インターネットサイトでのキャンセル代請求・回収が得意。キャンセル代の発生を未然に防ぐ顧問契約など、クライアント目線でできる限り早い解決の提案を行う。
Q1 一般的に、予約の段階でも『契約』は成立しているという記載は多いですが、消費者と事業者の間にはどのような契約が発生している?
町田弁護士:一般的に予約申し込み時に施設の利用契約が成立していると考えます。事業者は施設を利用させる債務を、お客さんは利用料金を支払う債務を、それぞれ負うと考えられます。
Q2 中には店側が客を訴えるのは難しいという意見もあります。実際問題としてやはり難しい?
町田弁護士:飲食店の場合には、コース予約がなければ、平均的な損害(※)の立証は確かに難しいと思います。しかし、当該飲食店の平均客単価を客観的資料として提出すれば、損害の認定は不可能ではありません。
コース予約がない場合、キャンセルされたときには、平均客単価〇円のキャンセル料を請求する旨、事前に明示しておけば、立証する必要はなくなる(違約金の合意があった)ので、認められる可能性は高くなります。
|
※平均的な損害 |
|
『キャンセルされなければ得ていた粗利益額』×『宿泊予定日にキャンセル分を補完する別の予約を確保できない確率』 |
Q3 損害賠償請求をするために相手を特定するために『携帯番号』から弁護士会照会を利用するのは有効?
町田弁護士:弁護士会照会にコストがかかりますが、訴訟をする上では有効な手段でしょう。
Q4 無断キャンセルによる損害賠償請求とは別に慰謝料の請求は可能?
町田弁護士:無断キャンセルを不法行為と考えると、法的には不可能ではありませんが、取引的な不法行為の場合には、慰謝料が認められることはほぼないように思います。
Q5 もしキャンセル料を超える損害が発生した場合でも、消費者契約法9条で無効とならずに請求する方法はある?
町田弁護士:実際の損害を立証できれば、請求できます。
消費者契約法9条は、高額な違約金・損害賠償額を予定することを防止するための規定です。実際に発生した損害の請求を否定する規定ではありません。
Q6 無断キャンセル防止の一環として『ドタキャン防止システム(※)』が注目されていますが、法的な問題は?
町田弁護士:電話番号があれば個人を特定できてしまうため、個人情報保護法に抵触する可能性は高いです。
|
※ドタキャン防止システムとは |
|
キャンセル客の電話番号をデータにまとめ、予約時に電話番号を照会することで、キャンセルの履歴のある顧客からは前払い制などで対応するシステムのこと。 |
実際に損害賠償請求をする方法
続いて無断キャンセルが発生した場合、損害賠償請求する方法をご紹介します。
まずはお客と話し合いをする
まずは話し合いによる解決を試みてください。お店の電話番号またはメールアドレスから、以下の内容を伝えるとよいでしょう。
- キャンセル料を請求する旨
- 請求する金額
- 金額の内訳(どのような損害を被ったのか)
- 請求する理由
もし弁護士に交渉を依頼した場合、以下の費用が発生します。被害金額があまりに大きい場合は検討してみてはいかがでしょうか。
- 着手金:10万円程度
- 成功報酬金:回収金額の10~15%程度
※請求額が100万円未満の場合
催告書を内容証明郵便で送る
もし話し合いがまとまらない場合や連絡がつかない場合は、催告書(※)の内容証明郵便を送りましょう。内容証明郵便とは郵送した文書の内容を公的に示すための郵便です。
法的拘束力はありませんが、裁判所へ証拠として提出できる上に、一般の郵便と見た目が異なるため、精神的プレッシャーを与えることができます。
|
※催告書とは |
|
「払うべきものを早急に支払ってください」といった趣旨の内容を記した書面。「いつまでに返済(支払い)がなければ法的手段等による解決を図る」などの内容が記載されるケースが多い。 |
内容証明郵便の利用には1,252円(文書が1枚の場合)かかります。
関連記事:「債権回収をするときの内容証明作成ガイド|必要性と基礎知識まとめ」
裁判所を介して請求する
内容証明郵便を送っても解決しない場合は、裁判所を介して請求しましょう。裁判所を通してキャンセル料の請求を行う場合、支払督促、少額訴訟を申し立てることが一般的です。
これらの方法では、通常の訴訟と比べて短期間かつ低予算に抑えることができます。
支払督促|法廷へ出向きたくない場合
支払督促は、訴えを起こした人の代わりに裁判所が金銭の支払いを督促するための制度です。申立時以外、裁判所へ出向く必要がないため、『請求する相手が多数いる場合』『裁判所へ出向く時間がない場合』に適しています。
支払督促にかかる裁判所費用(訴訟額が100万円以下の場合)は、以下のとおりです。
|
内訳 |
金額 |
|
|
裁判所費用 |
約2,500~7,000円 |
|
|
弁護士費用 |
着手金 |
15万円 |
|
成功報酬金 |
債務名義(※)の15~20% |
|
|
※債務名義 |
|
債権者が強制執行を行うために必要な債権の存在、範囲を公的に証明した文書。 |
関連記事:「支払督促とは|費用や流れ、申請書の書き方を解説」
少額訴訟|60万円以下の場合
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払い請求について争うための制度です。
裁判官からの助言の元、当事者同士顔を合わせるため、納得ができない場合は互いの妥協案を提案でき、少額訴訟では和解協議が期待できます。
対して支払督促では当事者同士顔を合わせることがありません。
そのため、争点がある場合(中には弁済が非常識だと考える人もいるかもしれません)は少額訴訟、争点がない場合(常識的に考えて弁済が当たり前の場合)は支払督促を検討しましょう。
※キャンセル料の弁済については争点がないことが多いため、支払督促が一般的です。
関連記事:「少額訴訟とは?手続きの流れや債権回収費用をわかりやすく解説」
少額訴訟にかかる費用(請求額が100万円未満の場合)は以下のとおりです。
|
内訳 |
金額 |
|
|
裁判所費用 |
約3,000~1万1,000円 |
|
|
弁護士費用 |
着手金 |
15万円 |
|
成功報酬金 |
債務名義の15~20% |
|
キャンセル料の請求は費用倒れの有無から総合的に判断しよう
消費者を保護するために、消費者契約法では、損害賠償請求できる範囲が制限されています。
契約の解除に伴い事業者に生じる平均的な損害の額を超える金額を徴収する内容のキャンセル料条項は、その超える部分について無効である。
引用:消費者契約法9条1条
消費者契約法9条1条は、消費者から請求できるキャンセル料を制限するための法律です。また、請求にはある程度の費用がかかります。請求できる金額と請求にかかる費用を比べた上で、どうするか判断しましょう。
損害賠償請求できる金額の算出、トータルでかかる費用について詳しくは、法律事務所へ相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では無断キャンセルを予防するための対策や、キャンセルが発生したときの対処方法を紹介しました。無断キャンセルで頭を悩ませている方の参考になれば幸いです。
無断キャンセル料を回収したい方へ
無断キャンセルが続いてしまうと、積り積もって大きな損害になり得ます。時効もありますので、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、債権回収することをおすすめします。
弁護士を通して内容証明や督促状を送ることで、裁判等を行わなくても回収できる可能性があります。
無断キャンセル料の時効が成立してしまう前に、ご相談ください。

【他事務所で断られた方歓迎|土日深夜も弁護士直通・LINEできる】男女トラブル・個人間の貸金回収は、早期の相談で回収率が大幅に変わります。迅速に対応します、ご相談ください。
事務所詳細を見る
◆即日交渉可◆LINE相談可◆電話で弁護士と直接話せる◆「今すぐ弁護士に相談したい!」という方はご相談を!LINEや電話で即日ご相談いただけます【男女間の金銭トラブルにも注力!】《解決実績は写真をクリック!》
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

売掛金・未収金に関する新着コラム
-
売掛金の未回収は資金繰りに影響するため、早期に解決する必要があります。しかし、回収作業には手間と時間がかかるうえ、精神的な負担も大きいので、代行業者に依頼するの...
-
売掛金が回収できずに悩んでいる方のなかには、訴訟を考えている方もいるでしょう。売掛金の未回収は経営に大きな影響を与える深刻な問題です。本記事では、売掛金の回収を...
-
本記事では、売掛について知りたい方に向けて、売掛金の概要・意味、売掛金と間違えやすい用語、売掛金の発生や回収などに関する仕訳方法などについて説明します。本記事を...
-
近年、ホストクラブで客に対する売掛金が回収ができずに困っているホストが少なくありません。 より確実に回収するために、本記事では法的な売掛金回収の方法やコツなど...
-
病院経営を行う上で「医療費の未払い」は大きな問題といえるでしょう。未回収に終わらないためにも、適切に回収対応を進める必要がありますが、医療費には時効があり、なか...
-
相手方の倒産などにより売掛金が回収不能な場合、企業は適切に仕訳対応を行わなければなりません。回収不能の場合は「貸倒損失」にて計上を行いますが、仕訳にあたっては一...
-
病院経営を行う上で「入院費の未払い」は大きな問題の一つです。未払い分については回収対応を進めるべきですが、ケースごとに取るべき対応内容は異なり、場合によっては時...
-
相手方が倒産した場合や、任意回収に応じない場合など、売掛金の回収が困難なケースはさまざまです。企業は売掛金の放棄や法的手段の実行など、状況ごとに適切な対応を判断...
-
売掛金を回収する前に取引先が倒産した場合、全額回収することは難しいでしょう。ただし、なかには回収対応が可能なケースもあるため諦めてはいけません。この記事では、取...
-
契約書がない請負工事で代金の支払いを拒否されると、資金繰りの悪化や発注者とのトラブルにつながるため、お金や時間のロスばかりではなくストレスもたまります。ここでは...
売掛金・未収金に関する人気コラム
-
売掛金の回収は放置すればするほど解決が難しくなります。取引先の倒産などで回収が不可能になって打つ手が無くなる前に、一刻も早く対策を練ることが重要です。本記事では...
-
未収金と売掛金は、どちらも「後から支払ってもらうお金」という点で共通しており、よく混同されがちです。しかし、権利や義務の元となる取引はそれぞれ異なり、決定的な違...
-
未収金を回収できないと、会社として多大なる損になりかねません。また、対策を取るのが遅れてしまうと未収金を回収できなくなってしまいます。より確実に、そして満額回収...
-
債務者(弁済者)の方にとって、代物弁済をする上で発生する税金に関する情報は気になるポイントだと思いますが、当記事では代物弁済における債務者、債権者の双方が負担す...
-
売掛金の消滅時効が成立させないためにも、滞納する相手に対して時効の中断を行いつつ、法的に回収することも検討しなければなりません。特に、債務者の経営難が理由で滞納...
-
売掛金とは、商品やサービスを提供して売上が発生したのち、まだ回収できていない代金のことです。売掛金は金銭債権のひとつで未収金などと混同されることもあり、回収する...
-
家賃滞納され、一向に支払われない大家・管理会社が相談できる相談窓口をまとめました。また、弁護士に依頼した場合の流れやよくある質問についてご紹介します。
-
相手方の倒産などにより売掛金が回収不能な場合、企業は適切に仕訳対応を行わなければなりません。回収不能の場合は「貸倒損失」にて計上を行いますが、仕訳にあたっては一...
-
近年、ホストクラブで客に対する売掛金が回収ができずに困っているホストが少なくありません。 より確実に回収するために、本記事では法的な売掛金回収の方法やコツなど...
-
患者が診療費や入院代などを支払ってくれない場合、まずは直接催促などを行って回収を図ることになるでしょう。しかしそれでも回収が難しい場合などは、裁判所を通じた手続...
売掛金・未収金の関連コラム
-
東京オリンピックによる外国人訪問者の増加にともない、今後増加しうる外国人による医療費未払い問題について、あらかじめ対策を講じておいた方が安心でしょう。この記事で...
-
家賃滞納され、一向に支払われない大家・管理会社が相談できる相談窓口をまとめました。また、弁護士に依頼した場合の流れやよくある質問についてご紹介します。
-
売上債権回転率とは、売上債権の回収速度をはかる上で重要な指標です。与信管理をするにあたって、売上債権回転率から読み解く会社の状態や、併せて考慮にいれた経営指標な...
-
無断キャンセルが発生した場合に、飲食店の経営者はどのような対策を取れるのか弁護士に聞きました。無断キャンセルする人の割合を減らし、キャンセルが発生したときの損失...
-
未収金と売掛金は、どちらも「後から支払ってもらうお金」という点で共通しており、よく混同されがちです。しかし、権利や義務の元となる取引はそれぞれ異なり、決定的な違...
-
売掛金の未回収は資金繰りに影響するため、早期に解決する必要があります。しかし、回収作業には手間と時間がかかるうえ、精神的な負担も大きいので、代行業者に依頼するの...
-
売掛金を回収する前に取引先が倒産した場合、全額回収することは難しいでしょう。ただし、なかには回収対応が可能なケースもあるため諦めてはいけません。この記事では、取...
-
会社の法務の仕事として売掛債権の管理・回収がありますが、そもそもの売掛債権という言葉は会計用語です。売掛債権とは法律上どういう意味なのか、なぜ管理が必要なのでし...
-
近年、ホストクラブで客に対する売掛金が回収ができずに困っているホストが少なくありません。 より確実に回収するために、本記事では法的な売掛金回収の方法やコツなど...
-
工事代金の未払い状態が続いてしまうと、会社経営にも大きく響きかねません。回収方法はさまざまありますので、時効にも注意しながら、状況に合った回収方法を選択しましょ...
-
売掛金の消滅時効が成立させないためにも、滞納する相手に対して時効の中断を行いつつ、法的に回収することも検討しなければなりません。特に、債務者の経営難が理由で滞納...
-
売掛金が回収できずに悩んでいる方のなかには、訴訟を考えている方もいるでしょう。売掛金の未回収は経営に大きな影響を与える深刻な問題です。本記事では、売掛金の回収を...