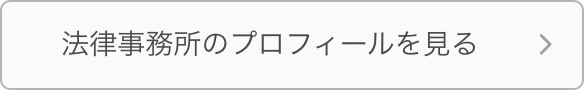債権回収の方法は、債務者と直接、交渉しながら回収する方法から、裁判所を介した方法まで色々な方法がありますがどの手段が適切なのでしょうか。実際のところ債権回収の適切な方法は、債権者の状況や債務者の対応によって十人十色です。
今回の記事では、各シチュエーション毎における債権回収の方法について、紹介していきたいと思います。
「貸したお金が返ってこない!!」このような事でお悩みではありませんか?
個人間の債権回収は、状況によっては弁護士に相談しても難しいケースがあります。
債権額が100万円以下の場合、費用倒れのリスクがあります。
ただし、債権額が100万円を超える、借用書があるといったご状況の場合、一度弁護士に相談することをおすすめします。
債務者が破産・再生手続きを行う前がチャンスです。
一般的な債権回収の方法とその手順
一般的な債権回収の方法として、債務者と直接、交渉することで回収するための方法を紹介していきます。この項で紹介する回収する債権は金銭債権を対象にしているので、金銭債権以外の回収方法に関しては、当記事の「法的手段を用いた債権回収の方法」以降を参考にしてください。
①電話による督促
まず、回収の相手(債務者)が個人であった場合に行うべきこととして、電話による支払いの督促を行いましょう。電話であれば時間も費用もかからないため、一番、簡易的にできる督促方法だからです。
電話によって督促を行う際のポイントとして、債務者の周りの人たちから電話をすることをオススメします。勤務先や自宅などに、自分が債務を抱えていることを周りの人間には知られたくないと思うため、精神的に債務者へプレッシャーをかける上で効果的です。
そして、最後に債務者、本人の携帯番号に連絡をしましょう。ケースバイケースですが、これで債務者が応じてくれる例は多々あります。
電話をかける頻度
また、電話をかける上で大切なことは、電話の回数よりも相手側とちゃんと話ができることであることを念頭に入れてください。そのため、1時間か2時間置きにかけ返すなど、電話する上での取り決めを事前に作ることをオススメします。
どうしても、電話が繋がらない場合は、事前に伝えるつもりであった用件を留守電に残しておきましょう。
②催告書の郵送
債務者が電話に応じない場合、債務の弁済を促すための催告書を内容証明郵便を介して郵送するのが一般的です。しかし、いきなり内容証明郵便を送ることはオススメしません。
相手側を下手に触発させる危険性が高いためであり、最初の内は催告書というよりはお手紙といった形で、あくまでも下手にでましょう。
内容は、「未払いの代金に関するお支払に関して、いつまでにお支払いをいただけるのか教えてください。」といった文面にすることをオススメしますが、この際に「平成○年○月○日までの返答をお願いします」と回答期限を設けてください。
また、相手側の財産状態などを聞きながら、「分割・返済期間に関する相談に乗ります」といった体で、文面を付け加えるとなお良いです。あくまで相談に乗るといった態勢をとることで、相手側の財産に関する情報を知ることもできます。
また手紙の郵送に関しては、債務者側から郵送されていないと主張されないためにも特定記録郵便、書留郵便を使用してください。
③内容証明郵便を介しての通知の督促
上記の催告書に応じない場合は、今度は内容証明郵便を介して本格的に催告書を郵送しましょう。
内容証明郵便を利用する目的は、催告書を郵送した事実を証明することができるためであり、後に訴訟へ発展した場合、証拠書類として有利に裁判を持っていくことができるためです。
内容証明郵便の使用方法については、「内容証明郵便を介した債権譲渡の通知方法」を参考にしてください。
催告書の作成
催告書を作成する上でのポイントは、①タイトルを催告書にする②債務者との契約の内容③債務者の返済残高④支払いの期日・口座番号など返済方法⑤返済に応じなかった場合の措置(法的手段)、について記述しましょう。
また、支払期限の記述に関しては、「平成○年○月○日までにお支払いください。」といったように具体的な日付で記載してください。日付を正確に指定した方が、債務者にとってプレッシャーが大きいためです。
さらに、返済に応じなかった場合の措置に関しても、「法的手段を取らせていただきます。」といった内容ではなく、「○○裁判所にて○○の支払請求訴訟の申立を行います。」といったように具体的にどのような手段にでるのか記載されている方が債務者にとってプレッシャーは大きいでしょう。
催告書の書式やフォーマットについては「内容証明郵便による催告」も参考にしてください。
④公正証書の作成
もし債務者が、催告書に応じてくれば場合、返済に関する交渉を行いましょう。交渉の際は、相手側が弁済に応じやすいように多少、弁済額を減額したり返済期間を長くしたりと猶予を与えた方が、交渉が上手くいくかもしれません。
交渉が完結したら弁済に関する契約書(債務者からの捺印が必要)を作成の上、公正役場へ公正証書を作成しにいく流れです。
公正証書とは、契約書に問題がなければ公証人役場にて公証人が作成する債務名義であり、この債務名義を取得することで債務者が再び債務不履行を働いた場合、債務者の資産の差押えを強制執行することで確実に債権回収ができます。
※債務名義とは:債権の存在を公的に証明した文書
必要書類
公正証書作成の場合、債務者・債権者共に、以下の書類が必要です。
-
・当人同士の実印・印鑑証明書(法人の場合は代表者)
-
・法人登記簿謄本または登記事項証明書
-
・印紙代
-
・公証人の手数料
|
債権額 |
印紙代 |
公証人の手数料 |
|
1万円以下 |
非課税 |
5000円 |
|
10万円以下 |
200円 |
|
|
50万円以下 |
400円 |
|
|
100万円以下 |
1000円 |
|
|
200万円以下 |
7000円 |
|
|
500万円以下 |
2000円 |
11000円 |
|
1000万円以下 |
10000円 | 17000円 |
法的手段を用いた債権回収の方法
もし先ほど、紹介した債権回収の方法に債務者が応じなかった場合は、法的手段に訴えましょう。
-
1.民事調停
-
2.支払督促
-
3.訴訟
裁判所を介した債権回収の方法として以上の3点が、手続きが容易な順にあげられます。
法的手段を用いる上で事前に知って抑えておくべきこと
これらの法的手段による債権回収の方法について紹介をしていきますが、その前に法的手段に訴える前に事前に抑えておくべき事項について確認していきましょう。
相手の資産状況
まず最初に、相手の資産状況、回収の対象にする債権を明確にすることが必要になります。手続きによって回収できる債権の種類が異なるため、債務者が保有している債権について事前に確認することが必要です。手続きの内容を決めた方が得策だからです。
いざ、裁判所への手続きが成功しても回収できる債権がなければ意味がありません。
仮差押え・仮処分
もし、債権回収をする上で目星の財産が判明した場合、仮差押え・仮処分の申し立てを行ってください。
いざ債務者の財産を差し押さえる段階になってすでに財産が処分されていたという例がありますが、仮差押え・仮処分は特定の債務者の財産が勝手に処分されることを防止することができます。
参照:「差し押さえる財産がない場合の費用倒れを防ぐ方法」
法的手段を取る意味:債務名義の取得
また、法的手段を選択する一番の意味は、公正証書と同様に債務名義を取得するためです。法的手段を選択した方が、時間や手間はかかりますが、より確実に債務名義を取得することができるため、最終的に相手側の資産・債権を差し押さえることできます。
当記事では、強制執行について詳しくは触れませんが、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【参照】
▶「強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ」
▶「強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説」
簡易裁判所による民事調停
裁判所を介した債権回収の方法として、民事調停は個人を含め一番ハードルが低い法的処置でしょう。民事調停とは、裁判所が指定した調停委員の仲介の元、当事者間(債務者・債権者)たちの意見をまとめるための手続きですが、相手側の同意が得られなければ成立しません。
実際には、調停が上手くいかないケースも珍しくなく、債務者側が訴訟問題に慣れている場合、裁判所に出頭しない場合もしばしばあります。法的手続きの中では、時間や費用がかからないため、着手しやすい法的手段ではありますが、債務者に対して法的拘束力が弱いところが難点です。
減額・分割払いなど妥協点を見つける
公正証書の際にも説明しましたが、債務者の同意を得るためには弁済の負担を減らしてあげるのも一つの手でしょう。弁済額の減額、弁済期間を延長するなど相手側が飲み込みやすい条件の場合、同意まで持ち込めるかもしれません。
調停が成立すれば、調停調書が作成されますが、調停調書は債務名義でもあるため、相手側が債務不履行を働いた場合、強制執行に持っていくことができます。
参照:「債権回収における民事調停の有効性と利用方法のまとめ」
支払督促
法的手続きにおいて、訴訟は時間と費用がかかるため、訴訟を敬遠する方の多くが支払督促を選択します。
支払督促とは、裁判所へ申立てることで、裁判所から債務者へ支払いを促すための手続きでありますが、同時に仮執行宣言付支払督促という債務名義を取得することができる手続きです。
強制執行の手続きをする上で、通常、債務名義に執行力を持たせるために執行文付与の申立を行わなければならず、執行文を付与する前に強制執行停止の申立をされることがあります。(参照:「強制執行停止の申立の手順と手続きにおける2つの注意点」)
その点、支払督促において取得できる仮執行宣言付支払督促では、既に執行力が付与されているため強制執行停止の申立をされても手続きを止めることができません。
金銭債権が対象
また、留意点としては、支払督促において対象とできる債権は、金銭債権のみであること、そして手続きの途中で債務者が督促異議の申立を行われると、訴訟へ移行しなければならない点です。支払督促に関しては、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【参考】
▶「支払い督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得する方法」
▶「支払督促に必要な申立書の書き方と添付書類の作成方法まとめ」
訴訟
法的手続きによる債権回収において、訴訟は一番確実な方法ではありますが時間や費用は一番かかります。一般的に訴訟において第一審で確定判決を貰えることはなく、仮執行宣言付判決が与えられることがほとんどです。
仮執行宣言付判決も債務名義の一種ではありますが、確定判決と同様に強制執行の申立を行うことできます。また、支払督促と異なり金銭債権以外も対象にすることが可能です。
参照:「債権回収の民事訴訟を起こす上で抑えておきたい知識まとめ」
少額訴訟
60万円以下の金銭を支払いの請求を目的とする訴訟においては、少額訴訟を行うことをオススメします。通常の訴訟と違い、1回の期日で審理を完了させることができるため、手続きにかかる時間、費用を安く抑えることが可能です。
また、債務名義として、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決においても、執行力が付与されているため執行文付与の申立が必要ありません。また、対象となる債権は金銭債権に限ります。
参考:少額訴訟の金額と請求可能な金額|少額訴訟の条件と手続き
強制執行
上記の法的手段によって債務名義を取得したのに、債務者が債務名義の内容に従って弁済を行わなかった場合、強制執行を申し立てましょう。強制執行とは、債務者の財産を差押えるための手続きになりますが、詳細は以下の記事を参考にしてください。
【参照】
▶「強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ」
▶「強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説」
経営状態の悪い会社から債権回収する方法
もし、取引先の会社へ未回収の債権が発生しているにも関わらず、その会社の経営状態が悪く資金繰りに苦労している場合、早急に債権を回収したいと思うはずです。しかしながら、資金繰りに苦労している会社から、債権回収するのは難しく、どのような方法で回収するべきでしょうか。
納入した商品の引き上げ
まず、もしその取引先の会社へ、自社商品を販売している、または他者から仕入れた商品を卸売りしているのであれば、これ以上の売掛金を増やさないためにも、経営状態の悪い会社との新規の取引や商品の引き渡しは中止にしてください。
そして、既に納入済みの商品が、取引先の社内に残っている場合は、商品を回収する手立てを考えなければなりません。しかしながら、いくら未回収の債権が発生しているとはいえ、黙って商品を持ち出すことは違法行為です。
債務者から商品引き上げ同意書
そのため商品引き上げ承諾書を作成した上で、相手側の会社から同意を貰うことで商品の回収をしましょう。未回収の売掛金を回収するよりも、まだ売りに出されていない商品を回収する方がはるかに対応に応じてもらいやすいからです。
|
商品引き上げ同意書 平成○年○月○日 記(商品名)
|
債権譲渡
また、経営状態の悪い会社から債権回収する方法として取引先から債権譲渡があります。債権譲渡とは、債権の内容を変えないまま、債権を移転するための手続きであり、債権の買収や債権回収の方法として認知されている手続きです。
もし債権回収をしたい取引先の会社が、ある未回収の債権を抱えているけど、自社にその会社が抱えているその債権を回収する能力がある場合を想定してください。
この場合、その会社が持つ債権を譲り受けることで、その会社が自社に対して抱えている債務の弁済に充てることで、両社とも負担を減らすことができます。債権譲渡に関しては、以下の記事も参考にしてください。
【参考】
▶「債権譲渡で債権回収をするために必要な知識と手続きの手順」
▶「債権譲渡の通知の重要性と対抗要件を満たすための2つの方法」
相殺
もし、債権回収したい会社に対して債務を抱えていた場合、回収したい債権の内容と、弁済すべき債務の内容が同種であれば、債権と債務を相殺することで、債権回収することができます。
相殺は相手の同意を得る必要がなく一方的な意思表示で成立するので、相殺に関する文書の証拠を残すために内容証明郵便を利用することが一般的です。
倒産した企業から債権回収をする方法
では今度は、倒産した企業から債権回収する方法について確認していきます。
代物弁済
代物弁済とは、債権者に対して債務者が賃金債権を抱えていた場合、それに代わる価値のあるもので弁済する方法です。代物弁済は債権回収においてもよく用いられる方法であり、倒産した会社に対して売掛金などの債権回収は困難なため、倒産した会社に対してもよく用いられる債権回収の方法でもあります。
また代物弁済は、債務者から資産が譲渡された段階で、資産の価値に寄らず債務者は債務の履行を完了したことになりますが、資産の価値が債権額を上回る場合、債権者はその差額分を債務者へ弁済しなければなりません。
代物弁済の対象
不動産、車、宝石など換金価値のある資産を代物弁済の対象にすることもできますが、法人同士では一般的ではないでしょう。倒産した会社に対して代物弁済の対象になるのは、その会社が自社から納入した商品、または他社から納入した商品の在庫が対象となるのが一般的です。
自社商品と比べて、他社の商品を代物弁済とするのが困難だといわれていますが、未回収の債権を全て回収するためには他社の商品も視野にいれるべきでしょう。
代物弁済の流れ
代物弁済をするためには、自社の商品だけであれば代物弁済契約書だけで事がたりますが、他社の製品も含めると他社商品の預り承諾書にも同意してもらうことが必要です。倒産した企業に対して代物弁済は早い物勝ちなところがあるため、事前に二つの契約書を作成しておきましょう。
参照:「代物弁済の効力を発生させるまでに必要な手順とその注意点」
担保権の行使
また、債務者が倒産手続きを始めている間であれ、担保権を実行することが可能ですので、債務者に対して担保権を所有している人は担保権を行使しましょう。担保権とは、契約する際に債務者が将来的に弁済できない場合(債権の保全のために)に備えた処置です。
一般的に倒産手続きを行う際、債務者に対する債権者の多くは、換金した債務者の財産を債権額に応じて均等に配当をもらうことしかできません。
しかしながら債務者が債務不履行、または倒産した際に、担保権を所有する債権者は担保権を行使することで、債務者の特定の資産(債権、財産)から優先的に弁済をうけることができます。
抵当権
担保権と聞いて一番、思い浮かべるのは抵当権でしょう。抵当権とは債務者の特定の物的財産(不動産)に対して設定される担保権です。一般的に対象は物的財産に限定されるため、債権を対象にすることはできません。
譲渡担保権
譲渡担保権とは、法人間で主に用いられる担保権ですが抵当権との違いは、物的財産だけでなく債権も対象にできるところです。
また、譲渡担保権を設定する上で所有権の登記手続きを行わなければなりませんが、登記上は譲渡担保権を設定した時点で所有権は債権者に移ります。そのため体裁上は、債務者が債権の弁済をして所有権が債務者へ戻るという形です。
また、債権を譲渡担保する場合は債権譲渡と同じステップを踏まなければなりませんが、詳しくは下記の記事を参考にしてください。
【参照】
▶「債権譲渡で債権回収をするために必要な知識と手続きの手順」
▶「債権譲渡担保で損しない為に事前に確認すべき3つの事項」
代物弁済予約
代物弁済予約とは、代物弁済の一種であり債務者が債務不履行、倒産をする際に、特定の財産にて弁済をしてもらうための担保手続きです。
代物弁済予約の特徴は二つありますが、一つ目は財産が債権者へ譲渡された時点で債務者の債務の履行が完了したこと、二つ目は資産の対象として物的資産だけでなく債権を対象にすることもできます。
また手続きの流れとしては所有権移転の仮登記手続きを行った上で、債権を対象とする場合は債権に対する(第三)債務者へ債権者が移転する旨を通知しなければなりません。
参照:「代物弁済予約を用いて債権を確実に保全する為の知識のまとめ」
保証人への債権回収
債務者との契約時に保証人を設けていた場合、債務者が倒産したら保証人へ債権回収することができます。
しかしながら、一般的に企業の倒産であれば、企業の代表や役員が保証人になっているケースが多いため、企業の倒産と共に、保証人が自己破産するリスクは否めません。
同じ倒産でも民事再生は、会社を再び建て直すための手続きであり、会社更生法と違い経営者がそのまま経営を存続できるため、代表や役員から債権回収できる可能性はあります。
【参照】
▶「債権回収における連帯保証人の有効性と連帯保証人の取得方法」
▶「民事再生法とは|倒産した企業に過払い金請求する為の知識」
動産売買先特許権による物上代位
また、倒産すべき会社に対して債権回収する方法として、動産売買先特許権による物上代位を活用することができます。
動産売買特許権による物上代位とは、売買契約を結んだ売却先の取引先が倒産する際、自社の売買契約を元に取引先の会社が保有している売掛金債権を優先的に差し押さえることで、債権回収する方法です。
例

例えば会社A(自社)が取引先の会社Bへ販売した商品aを、会社がすでに別の顧客(会社C)へ転売したにも関わらず、転売先(会社C)が取引先の会社に代金を支払っていない場合を想定してください。
この場合、先ほどの代物弁済と違い、倒産した会社Bから納入した商品aを回収したいからといって、すでに会社Cへ転売された商品aを引き上げることはできません。それは会社Cが商品aの在庫を保有しているのは、会社BとC間の契約に基づくものであり会社Aは関与していないからです。
そこで動産売買特許権による物上代位を活用することができるのですが、倒産した取引先が保有している商品aに関する売掛金債権を優先的に差し押さえることができます。
債権の施行:債権差押え
動産売買先特許権とは、法律上認められた担保権であり、当事者間(会社B、会社C)の同意がない状態でも債権を差し押さえることが可能です。その際、裁判所へ債権差押の申立を行わなければなりません。(詳細:「強制執行申立から差押えまでの流れ」)
また、債権の差押え後は、会社Aは会社Cを債務者として、売掛金を回収することになります。
|
動産売買先特許権による物上代位 |
|
|
転売された商品の引上げ |
不可 |
|
転売された商品の売掛金債権の差押え |
可 |
消滅期間が迫った債権を回収する方法
多くの未回収の債権を抱えている方が懸念していることの一つは、債権の時効が消滅期間を迎えていることでしょう。特に売掛金債権に関しては時効期間が2年のため、早めに債権回収しなければなりません。
ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。
参照:「債権回収するために必要な時効の中断方法と知識のまとめ」
時効期間を延長する
まず、債権の時効が迫っている、または時効間近の債権を所有している債権者は債権の時効期間を延ばすことが必要です。
一般的には上記で紹介した、法的手段(10年まで延長)、内容証明郵便の通知(6ヶ月の延長)によって債権の時効期間を延ばすことができますが、ここでは別の方法を紹介していきます。
債務者からの承認を得る
まず、債権の時効期間を延ばす上で、「債務者からの承認を得る」という方法がありますが、具体的には「債務者からの同意を得る」、「債務者からの一部の弁済」、「債務者からの支払猶予願い」の3点です。
しかしながら、債務者からの承認を法的に証明するためにはどうすればいいのでしょうか。
後者の二つであれば書面や明細書で残すことが可能ですが、前者の債務者からの同意を得るためには、新たに弁済に関する同意書を作成した上で、債務者から署名と捺印をもらわなければなりません。
当然ながら、時効の消滅期間の迫っているのに、書面に署名をする債務者はいないでしょう。そこで、一部だけの弁済をしてもらうことが「債務者からの承認を得る」上で効果的です。
時効も間近であるし少しだけの弁済なら仕方がないと債務者側も思うため、支払に応じやすくなります。
売買契約を準消費賃借契約に変更
また、先ほども申しましたが売掛金債権は時効契約が2年であるため、債権者にとって時効の消滅期間はシビアな問題です。そのため売掛金が発生している段階で契約内容を準消費賃借契約に代えることをオススメします。
準消費賃借契約に変更すれば、時効期間は10年、商取引の場合は5年になるためです。
相殺と消滅期間の関係
また、消滅期間を迎えてしまった債権に対しては相殺をするべきでしょう。相殺とは債権者・債務者の双方が債権・債務を抱えていた場合、双方の債権・債務を相殺するための手続きであり、一方的な相殺の主張(内容証明郵便による通知)にて相殺を行うことができます。
相殺は時効になった債権においても利用可能なため、時効期間の迫った債権に対してオススメな債権回収方法です。
債権者代位権の行使
債権者代位権とは、債権者が自身の債権(被保全債権)を保全する目的で債務者が所有する資産の所有権、または債権(被代債権)を債務者に代わり権利を行使することができる権利です。
この保全行為とは一般的に、時効期間を迎えることで債権の効力がなくなることを防止することを意味しており、時効期間が迫っている債権回収においては効果的な方法でしょう。具体的な利用要件など、詳細については以下の記事を参照にしてください。
参照:「債権者代位権を行使することで債権回収するための知識のまとめ」
債権回収を弁護士に依頼するメリット
以上、シチュエーション別に債権回収の方法を紹介しましたが、債権回収をより確実に行いたい方は弁護士に依頼するべきでしょう。
債務者の住所が不明の場合
まず、債権回収したい対象が個人である際、その債務者の住所が不明であれば、債務者から債権回収をするのは難しくなります。その場合、個人で債権回収をするよりも護士などに依頼して債務者の所在地を調査してもらう方が現実的です。
特に、裁判所を介して債権回収をする際、相手側の住所を管轄する裁判所へ申立を行うため住所を特定しなければなりません。
書類作成の委託
また、債権回収を行う上で何かしらの書類を作成するのは必須ですが、法律の知識の乏しい人間が作成するよりも業務上、書類作成に慣れている弁護士へ依頼した方が効率的です。
裁判所の申立書の確認は厳格
特に、裁判所へ申請する際の書類は、記入漏れや誤字脱字に対して厳しく、入念にチェックが入るため個人で作成した人が再提出をなるケースは珍しくありません。そのため申請書類の作成に慣れている弁護士に依頼した方が、時間的なコストがかからずに済みます。
弁護士の後ろ盾による弁済に応じやすくなる
さらに、債権回収を行う上で催告書を送りつける場合がありますが、弁護士に催告書の作成を依頼した際、弁護士の名前が催告書に入るため、相手側に弁護士に依頼したことをわからせることができます。
実際に、弁護士の後ろ盾があるとわかっただけで、債務者の対応が変わるケースも多いため、そういった点でも弁護士に依頼する効果は大きいです。
訴訟に発展した場合の代理人の委託
さらに債権回収を行う上で、時間と費用はかかりますが、他に手立てがなければ訴訟で解決をはかるべきでしょう。訴訟の際は、裁判所へ出廷しなければならないため、日頃の業務で時間を作る余裕がない方にとって負担は大きいと思います。
弁護士へ依頼することで、出廷の際の代理人を委託することができるので、訴訟に関する負担を減らす上でも弁護士に依頼するのは効果的です。
早急な対応が必要な場合
また、債権回収を行う上で、回収先の取引先の経営状態が悪く倒産しそう、または倒産した場合や未回収の債権が時効を迎えそうな場合は、早急な対応が必要です。
この場合、契約書の作成から裁判所への申立など、手間のかかる作業をしなければなりませんが、早急に対処するためにも弁護士などに依頼した方が良いでしょう。
【参照】
▶「債権回収するために必要な時効の中断方法と知識のまとめ」
▶「債権回収を弁護士に依頼するメリットと費用相場」
まとめ
債権回収をする方によって、取るべき方法は千差万別です。現在、未回収の債権を抱えている方々が、今回の記事を債権回収の参考にしていただけたらと思います。
未回収の債権でお悩みではありませんか?
債権回収には時効があるため、滞納が続くようでしたらできるだけ早く弁護士にご相談ください。弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 債務者との交渉
- 最適な債権回収方法の提案
- 内相証明や督促状の作成・発送
- 差し押えの手続き・書類作成 など
弁護士に依頼することで、最大限の金額を回収できる可能性があります。債債務者が破産・再生手続きを行う前に、弁護士にご相談ください。。

【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております
事務所詳細を見る
【法人・個人事業主のご相談専用窓口】月100件~など少額・大量債権の回収に特化!徹底したコンプラ教育と弁護士による督促、経験豊富なオペレーターによる対応でブランドイメージを守りながら着実に回収【累計2億円超の委託実績】
事務所詳細を見る
【顧問契約5.5万~|約2,000万円の債権回収実績】法人・個人事業主・不動産オーナー様の売掛金回収、未払い賃料回収なら◆企業の福利厚生でのご利用可◆オンライン面談◎※個人案件・詐欺のご相談はお受けしておりません
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

債権回収に関する新着コラム
-
はじめて債権管理を担当することになった方のなかには、上記のような不安がある方も多いでしょう。そこで、本記事では債権管理の基本的な概念・具体的な業務内容・システム...
-
未回収リスクとは、売掛金が期日通りに回収できないことで生じるリスクで、とくに中小企業にとっては経営を揺るがす大きな問題となりえます。本記事では、未回収リスクの基...
-
売掛金などの債権を長期間回収できずにいると、「長期滞留債権」として企業経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。本記事では、「長期滞留債権」とは何かや回収方法、...
-
通販では、支払いを後払いとすることも多く、代金未回収のリスクが発生します。本記事では、代金未払いで困っている場合、代金の回収のために、どのような手段を取り得るこ...
-
本記事では、どれだけ催告しても金銭債務を履行しない債務者にとることができる法的手段の種類、滞納状態にある債務者への対応を弁護士へ依頼するメリットなどについてわか...
-
債権回収が長い間できておらず売掛金があるため、債権回収の時効がどのくらいなのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、債権の消滅時効が成立する...
-
後払いの滞納に悩みがある事業者は少なくないですが、悩みの解決策の一つが少額かつ大量の債権の回収業務に注力している弁護士に依頼することです。本記事では、後払い代金...
-
占い詐欺に遭った際は、弁護士への相談がおすすめです。弁護士であれば、被害金の回収に向けた有効なアドバイスが望めるほか、返金請求を依頼することもできます。本記事で...
-
業務委託による報酬が未払いの場合、債務者に対して債権回収を行うべきでしょう。ただし対応にあたっては、状況に応じて回収方法を判断する必要がある上、時効期間などにも...
-
金銭トラブルで悩んでいる場合、弁護士に相談することでスムーズに解決できることも多いです。弁護士費用が高額にならないか不安であれば、無料相談を活用してはいかがでし...
債権回収に関する人気コラム
-
「お金を貸した相手と連絡が取れない」「いつまで経ってもお金を返してもらえない」など、借金の回収について頭を悩ませている方もいるでしょう。本記事では、借金の回収方...
-
貸したお金を返してもらえないとき、どのように回収をすれば良いかご存知でしょうか。借金の回収は、お金を貸した相手の状況に応じて適切な対応を判断する必要があります。...
-
差し押さえは、交渉での債権回収が困難な場合の最終手段として使われる法的手段です。差し押さえを行うために必要な費用や、手続き方法について、詳しくご紹介していきます...
-
少額訴訟にかかる費用は、自分で手続きを行った場合、または専門家に依頼した場合に、一体いくら発生するのでしょうか?
-
差し押さえは、債権回収の法的手段の一種で最終手段として使われます。それにより、不動産や預金、給与などの財産から強制的にお金を支払ってもらうことができます。この記...
-
債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...
-
少額訴訟は手続きがスムーズだったりしますが、訴状の書き方がわからないために諦めるという方も多くいらっしゃいます。書き方がわからない場合は、各相談窓口で教えてもら...
-
少額訴訟を行うにあたってかかる費用は自身で手続きを行う場合場合は裁判費用のみ、弁護士に依頼して行う場合は裁判費用に加え弁護士費用がかかります。この記事では詳細な...
-
債権回収を依頼した場合の弁護士費用相場は依頼状況などによっても異なりますが、ある程度の目安はあります。費用倒れを防ぐためにも弁護士費用について知っておきましょう...
-
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
債権回収の関連コラム
-
差し押さえを弁護士に依頼した場合にどのようなメリットがあるのか、弁護士に依頼すべき理由、弁護士費用について解説します。
-
少額訴訟でも弁護士に依頼するメリットはあるのか、もし依頼するとしたら弁護士費用はいくらになるのか、少しでも費用を抑えるコツはあるのか、費用倒れにならないか、など...
-
債務者本人からの債権回収が難しい場合、保証人へ請求することになりますが、請求の進め方はケースに応じて選択する必要があります。そこで今回は、保証人請求のタイミング...
-
本記事では、どれだけ催告しても金銭債務を履行しない債務者にとることができる法的手段の種類、滞納状態にある債務者への対応を弁護士へ依頼するメリットなどについてわか...
-
悪質な家賃滞納者をいつまでも野放しにしておくことはできません。
-
はじめて債権管理を担当することになった方のなかには、上記のような不安がある方も多いでしょう。そこで、本記事では債権管理の基本的な概念・具体的な業務内容・システム...
-
貸したお金が返ってこない、催促しても音沙汰無し。ある程度自分で手を尽くしても回収が難しいならば債権回収会社に委託する方が得策です。委託するメリットや債権回収会社...
-
不良債権ってイマイチ何かわからない人や回収できない人は一読することをおすすめします。この記事では、不良債権はどんなものか、債権回収のやり方についてお伝えしていき...
-
どのようにして強制執行停止の申立を行うのでしょうか。今回の記事では、強制執行停止の申立をするにあたり、申立の流れとその手順について主に解説していきたいと思います...
-
債権譲渡担保(さいけんじょうとたんぽ)とは、ある債権において債務者から買掛金の未払いなど弁済がなされなかった場合に備え、債務者が所有する債権を担保にかける目的で...
-
最近ではコロナウイルスの影響などもあり、経営状況が悪化している会社もあります。取引先が倒産した場合に備えて、この記事で対処法を身につけておきましょう。この記事で...
-
家賃滞納の問題は不動産を運営する方なら誰でも避けて通れない道だと思いますが、今回の記事では内容証明の作成方法から催告書を郵送したのに効果がなかった場合の対処方法...