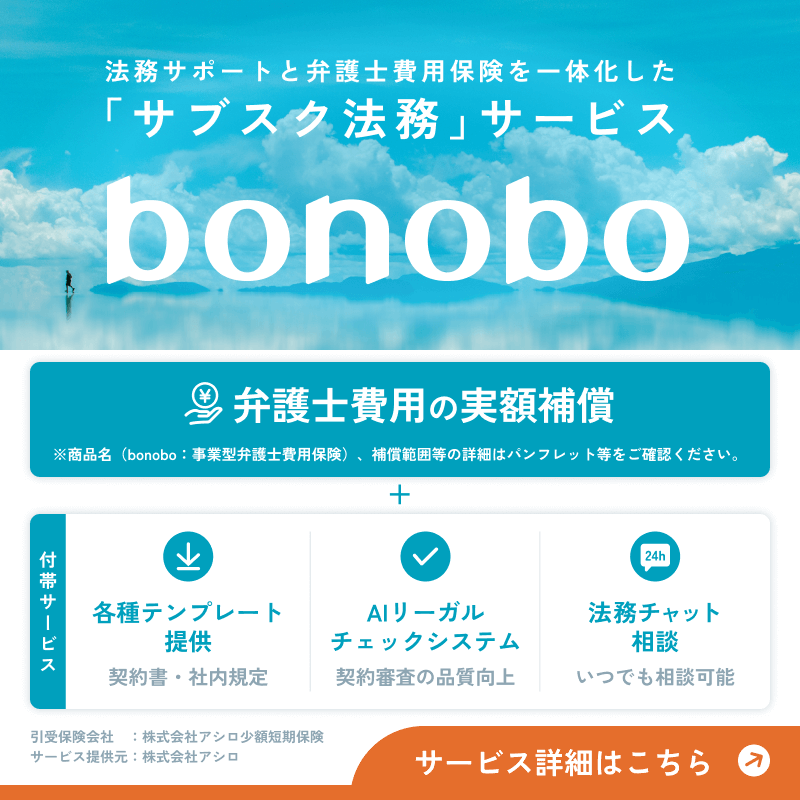詐欺被害に遭ってしまうと、どのように対応すべきか分からず、途方に暮れてしまう方がたくさんいらっしゃいます。
そんな方は、被害者支援センターなどの窓口へ速やかに相談しましょう。
各相談窓口では、詐欺被害者が救済を受ける方法などについてアドバイスを受けられます。
窓口によって受けられるアドバイスやサポートの内容が異なるので、ご自身の状況に応じて使い分けてください。
本記事では、詐欺被害に遭ったときに相談できる窓口や、詐欺被害者が救済を受ける方法などを紹介します。
詐欺被害に遭ってしまいお困りの方は、本記事を参考にしてください。
詐欺被害に遭ったときに相談できる窓口5選
詐欺被害に遭ってしまったときは、速やかに行政機関や専門家などへ相談することが大切です。
詐欺被害について相談できる主な窓口としては、以下の5つが挙げられます。
- 被害者支援センター|電話・面接によって相談できる
- 検察庁「被害者ホットライン」|被害者支援員に電話で相談できる
- 法テラス「犯罪被害者支援ダイヤル」|支援情報を提供してもらえる
- 各都道府県の弁護士会|無料相談を実施しているところも
- ベンナビ債権回収|詐欺事件に精通した弁護士に相談できる
1.被害者支援センター|電話・面接によって相談できる
公益社団法人全国被害者支援ネットワークの全国48の加盟団体(支援センター)では、犯罪被害者を支援する活動をおこなっています。
具体的には、犯罪被害者からの電話相談や面接相談を受け付けているほか、裁判所や警察への付き添いなどの直接的支援もおこなっています。
詐欺被害への対処法が全く分からない方や、詐欺被害のトラウマに悩まされている方は、公益社団法人全国被害者支援ネットワークの支援センターに相談してみましょう。
2.検察庁「被害者ホットライン」|被害者支援員に電話で相談できる
各都道府県に設置された検察庁では、犯罪被害者のための「被害者ホットライン」を設けています。電話またはファックスでの利用が可能です。
検察庁の被害者ホットラインに電話またはファックスをすると、被害者支援員に相談に乗ってもらえます。
被害者支援員は相談内容を聴いたうえで、解決策のアドバイスや問い合わせ先などの紹介をおこない、被害者が抱えているトラブルを解決する手助けをしてくれます。
被害者支援員は、被害者支援に関する経験が豊富な検察庁の職員で、被害者に対するきめ細やかな支援をおこなうための専門的な研修を受けているので、安心して相談できるでしょう。
3.法テラス「犯罪被害者支援ダイヤル」|支援情報を提供してもらえる
市民と法専門家の距離を近づけるための活動をしている法テラス(日本司法支援センター)では、「犯罪被害者支援ダイヤル」を設置しています。
犯罪被害者支援ダイヤルに電話をすると、法テラスの職員に相談できます。対応している相談内容は多岐にわたり、詐欺被害についても相談可能です。
法テラスの職員からは、詐欺被害の解決に役立つ情報や、解決を支援している機関・団体などの案内を受けられます。
また必要に応じて、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介も受けられます。
法テラスは、弁護士費用の立替払い制度を運営しているのが大きな特徴です。
収入と資産が一定水準以下の方に限られますが、弁護士費用の立替払い制度を利用したい場合には、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤルに相談してみるとよいでしょう。
4.各都道府県の弁護士会|無料相談を実施しているところも
各都道府県に設置されている弁護士会では、犯罪被害者からの相談を受け付けています。
特に詐欺の被害金を回収したい場合や、詐欺グループを刑事告訴したい場合には、弁護士のサポートを受けるのが効果的です。
相談できる弁護士に心当たりがない場合は、弁護士会に相談することが有力な選択肢となります。
弁護士会を通じた相談は有料のケースが多いですが、相談内容やタイミングによっては無料相談が利用できることもあります。
無料相談会の日程等については、各弁護士会にご確認ください。
5.ベンナビ債権回収|詐欺事件に精通した弁護士に相談できる
「ベンナビ債権回収」は、債権回収を得意とする弁護士が多数登録されているポータルサイトです。
詐欺事件への対応に精通した弁護士も数多く登録されており、電話やメールで直接問い合わせることができます。
相談内容や地域に応じてスムーズに弁護士を検索できる点が、「ベンナビ債権回収」の大きな特徴です。
詐欺被害について相談できる弁護士に心当たりがない方は、「ベンナビ債権回収」を利用すれば便利に弁護士を探すことができます。
「ベンナビ債権回収」には、無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されています。
詐欺事件への対応に精通した弁護士に無料で相談したい方は、「ベンナビ債権回収」をご利用ください。
詐欺被害で失ったお金を取り戻す方法
詐欺被害に遭って失ってしまったお金を取り戻すためには、迅速な対応が求められます。
弁護士のサポートを受けながら、以下の対応を速やかにおこないましょう。
- 振り込め詐欺救済法に基づく救済|被害回復分配金の受給を申請できる
- 被害回復給付金支給制度の利用|犯罪被害財産をもとにした給付金を受けられる
- 加害者と示談をする|弁護士に交渉を依頼するのが安心
- 裁判所に対して訴訟を起こす|時効に注意して早めに請求を
振り込め詐欺救済法に基づく救済|被害回復分配金の受給を申請できる
詐欺グループの銀行口座にお金を振り込んだ場合には、振り込め詐欺救済法に基づく救済を受けられる可能性があります。
詐欺に用いられた口座のある金融機関へ被害を届け出ると、口座が凍結され、最終的にはその残高から被害回復分配金の支払いを受けられます。
ただし、すでに詐欺グループが被害金を出金している場合には、振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金は受け取れません。
そのため、金融機関に対する被害の届出は直ちにおこなうべきです。
被害回復給付金支給制度の利用|犯罪被害財産をもとにした給付金を受けられる
検察庁は、組織的な詐欺などについて犯人から没収・追徴した金銭を原資とする「被害回復給付金支給制度」を運用しています。
対象となる詐欺事案の被害者は、一定期間内に検察官に対して申請書や被害の証拠を提出すれば、被害回復給付金を受け取れます。
被害金全額を回収できるとは限りませんが、一定の補償は受けられる可能性があるので、組織的な詐欺などの被害に遭った方は被害回復給付金の申請を検討しましょう。
加害者と示談をする|弁護士に交渉を依頼するのが安心
詐欺に遭って失った被害金は、加害者である詐欺グループに対して、不当利得(民法703条、704条)または不法行為(民法709条)に基づき直接返金を求めることができます。
詐欺グループとの間で連絡が取れる場合は、まず裁判外で返金を求めましょう。示談が成立すれば、早期に被害金を回収できる可能性があります。
示談交渉をおこなうに当たっては、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士が法的根拠に基づいて請求し、刑事告訴も辞さない旨を伝えて毅然と対応すれば、詐欺グループが返金に応じる可能性が高まります。
裁判所に対して訴訟を起こす|時効に注意して早めに請求を
詐欺グループが返金に応じない場合には、裁判所に対して訴訟を提起しましょう。
訴訟では、不当利得または不法行為の要件を被害者側が立証しなければなりません。
詐欺に関するメッセージの履歴や、被害金の振込履歴などを証拠提出して、詐欺被害の事実を立証しましょう。
訴訟では、訴状・準備書面や証拠書類など、さまざまな資料の作成・提出が必要になります。
一般の方が自力で対応するのは大変なので、弁護士に依頼することをおすすめします。
また、詐欺被害に遭ってから長期間が経過すると、返金請求権が時効によって消滅してしまうことがあります。
不当利得返還請求権の時効期間は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のうちいずれか早く経過する期間です(民法166条1項)。
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間は、損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年のうちいずれか早く経過する期間です(民法724条)。
返金請求権に係る消滅時効の完成を阻止するためには、内容証明郵便で請求書を送る、訴訟を提起するなどの方法が考えられます。
消滅時効が完成しないように、早めに弁護士へ相談して請求へ着手しましょう。
詐欺被害に遭ったら最初にとるべき2つの行動
詐欺被害に遭った方は、速やかに以下の対応をとりましょう。
被害金を回収できる可能性を少しでも高めるためには、迅速な対応が必要となります。
- 振込先金融機関に連絡する
- 警察に被害届を提出する
1.振込先金融機関に連絡する
詐欺グループの口座にお金を振り込んでしまった場合は、真っ先に振込先金融機関へ連絡しましょう。
口座が犯罪に利用された疑いがあると金融機関が判断した場合には、その口座が凍結され、詐欺グループによる出金ができなくなります。
後に被害者が受給できる被害回復分配金は、犯罪に利用された口座の凍結時点における残高から支払われます。
口座凍結が遅れると、詐欺グループによる出金がおこなわれてしまい、被害回復分配金を全く受け取れない事態になりかねません。
振込先金融機関に対しては、とにかくすぐに連絡することが大切です。
2.警察に被害届を提出する
詐欺グループを取り逃さないように、警察に対する被害届の提出も早めにおこないましょう。
被害届の提出が早ければ早いほど、警察による捜査への着手も早くなり、詐欺グループを摘発できる可能性が高まります。
詐欺グループが逮捕されれば、逃亡を防ぐことができるため、被害金の返金請求などもしやすくなります。
被害金の振込先金融機関と併せて、警察にも速やかに連絡しましょう。
詐欺被害の救済についてよくある質問と回答
詐欺被害に関する救済制度(振り込め詐欺救済法・被害回復給付金支援制度)について、よくある質問と回答をまとめました。
- 振り込め詐欺救済法の対象となる犯罪行為にはどのようなものがありますか?
- 振り込め詐欺救済法によって返金される額はどのように決められるのですか?
- 被害回復給付金支給制度を利用した場合の返金額はどのように決められますか?
- 被害回復給付金支給制度の実施状況はどこで確認できますか?
振り込め詐欺救済法の対象となる犯罪行為にはどのようなものがありますか?
振り込め詐欺救済法が適用され、被害者が被害回復分配金を受け取れる可能性があるのは「振込利用犯罪行為」です。
振込利用犯罪行為とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として被害者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいいます(振り込め詐欺救済法2条3項)。
詐欺グループの口座にお金を振り込んでしまった被害者は、振り込め詐欺救済法に基づく救済の対象となりますので、速やかに振込先金融機関へ連絡しましょう。
なお、被害回復分配金を受給するためには、当初の口座凍結依頼とは別に、振込先金融機関に対して申請書を提出する必要がありますので、忘れずに提出しましょう。
被害回復分配金の申請等に関する詳細については、金融庁のQ&Aなどをご参照ください。
振り込め詐欺救済法によって返金される額はどのように決められるのですか?
振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の額は、犯罪利用預金口座に残っている金額を、申請者の被害額に応じて按分する形で決まります。
(例)
- 被害者はA、B、Cの3名
- 被害金額はAが50万円、Bが150万円、Cが300万円の計500万円
- 詐欺グループが200万円を引き出したので、犯罪利用口座に滞留している金額は300万円
- B、Cは被害回復分配金を申請したが、Aは申請しなかった
受給できる被害回復分配金の額は、以下のとおり
- A:支払いなし(申請していないため)
- B:100万円(被害金額:150万円)
- C:200万円(被害金額:300万円)
被害回復給付金支給制度を利用した場合の返金額はどのように決められますか?
被害回復給付金は、犯人から没収・追徴して検察官が保管している給付資金から、被害回復事務管理人の報酬や手続き費用を控除した額を原資として支給されます。
支給額の上限は実際の被害額です。被害総額が原資額を超える場合は、原資額を被害額に応じて按分して支給額が決定されます。
(例)
- 被害者はA、B、C、Dの4名
- 被害金額はAが200万円、Bが300万円、Cが500万円、Dが1,000万円の計2,000万円
- 給付資金から、被害回復事務管理人の報酬や手続き費用を控除した額は1,000万円
受給できる被害回復給付金の額は、以下のとおり
- A:100万円(被害金額:200万円)
- B:150万円(被害金額:300万円)
- C:250万円(被害金額:500万円)
- D:500万円(被害金額:1,000万円)
被害回復給付金の計算方法等の詳細については、法務省のQ&Aなどをご参照ください。
被害回復給付金支給制度の実施状況はどこで確認できますか?
ご自身が被害に遭った詐欺事件が被害回復給付金支給制度の対象となっているかどうかは、官報や検察庁のホームページに掲載されます。
また、検察官が把握している被害者に対しては、被害回復給付金支給制度について個別に通知がおこなわれます。
警察署などを通じて、検察官に対して被害者である旨を伝えておきましょう。
さいごに
詐欺被害に遭ってしまったら、速やかに金融機関や警察に連絡したうえで、今後の対応等について弁護士に相談しましょう。
詐欺の被害者が救済を受けるためには、振り込め詐欺救済法や被害回復給付金支援制度などの救済制度を利用するほか、詐欺グループに対して直接返金を請求する方法があります。
詐欺グループに対する返金請求をおこなう際には、弁護士に相談するのが安心です。
「ベンナビ債権回収」を利用すれば、詐欺被害への対応を得意とする弁護士をスムーズに検索できます。
無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されているので、詐欺被害に遭ってしまいお困りの方は、「ベンナビ債権回収」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。

【他事務所で断られた方歓迎|土日深夜も弁護士直通・LINEできる】男女トラブル・個人間の貸金回収は、早期の相談で回収率が大幅に変わります。迅速に対応します、ご相談ください。
事務所詳細を見る
◆即日交渉可◆LINE相談可◆電話で弁護士と直接話せる◆「今すぐ弁護士に相談したい!」という方はご相談を!LINEや電話で即日ご相談いただけます【男女間の金銭トラブルにも注力!】《解決実績は写真をクリック!》
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

その他の債権知識に関する新着コラム
-
加害者死亡後、その家族から損害賠償の相続放棄を告げられ泣き寝入りしかないと諦めていませんか?相続放棄が無効になる3つのパターンや、債権者ができる対抗策があります...
-
本記事では、債権について理解したい方に向けて、債権に関する一覧表、発生原因別・目的別の債権の種類、種類ごとの債権のルールや特徴、債権がもっている主な効力などにつ...
-
ロマンス詐欺は解決が難しい事件です。被害回復できる事案が限られるため、信頼できる弁護士への相談が大切といえるでしょう。中には着手金をだまし取るような行為をして二...
-
債権トラブルを抱えている場合、金銭債権について把握することも大切です。金銭債権は、債権債務関係における金銭の支払い請求権を指します。本記事では、金銭債権について...
-
お金を振り込んでから、振り込め詐欺に遭ったことに気づいたとしても諦めることはありません。振り込め詐欺救済法に従って手続きをすれば返金してもらえる可能性があるから...
-
結婚詐欺の被害は弁護士に相談、依頼することで、被害金を取り戻せたり、加害者の逮捕につなげられたりする可能性があります。本記事では、弁護士に相談できる窓口を紹介す...
-
インターネット上の詐欺被害に遭ってしまい、どこに相談したらよいのかもわからず、ひとりで悩んでいる方は多いのではないでしょうか。本記事では、詐欺被害の相談先や上手...
-
本記事では、LINEで詐欺被害に遭ってしまった場合の相談窓口を紹介します。 すでに被害に遭ってしまった場合はもちろん、疑わしいLINEグループに入れられ、個人...
-
振り込め詐欺に遭ったら、一人で悩まず、すぐにでも専門機関に相談することが重要です。警察や法律事務所、消費生活センターに相談することができます。本記事では、消費生...
-
2024年から新NISAが始まり、投資に関心を持つ方が増えています。投資を始めたばかりの方は、インターネット上で横行している投資詐欺に騙されないように注意すべき...
その他の債権知識に関する人気コラム
-
債権と債務の違いをわかりやすく図解します。相続・相殺・双務契約などの状況別に債権と債務の関係性をお伝えします。個人・法人に関わらず、まずは債権債務の理解を深めて...
-
債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...
-
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
-
今回の記事では、債権者代位権における、行使することで生じる効果、利用要件、またどのようなシチュエーションで行使されるのかについてまとめました。
-
債権者にとって債権者破産はどのようなメリットがあるのでしょうか。今回の記事では債権者破産がどのような目的で行われるのか、申立方法や申立要件など債権者破産について...
-
債権者保護手続きとは、債権者の利益を保護するための手続きです。主に会社分割や合併など組織再編をする際に、必要になります。通常の債権者保護手続は、官報公告と個別通...
-
投資詐欺の被害に遭ってしまった方は、「どうすればお金を返してもらえるのか」と悩んでいるでしょう。この記事では、投資詐欺の返金を受けるための方法や、そのために準備...
-
今回の記事では顧問弁護士を利用する上で発生する各費用の相場、費用に対して請け負ってもらえる仕事内容についてまとめました。
-
今回の記事では、実際に債権者破産の申立をする上で、必要な申立方法や申立書類の作成方法、申立費用について解説していきます。
-
個人の方が顧問弁護士を利用するメリットはどこにあるのでしょうか。今回の記事では顧問弁護士を個人の方が利用するメリットや事例、顧問弁護士を利用する上での注意点につ...
その他の債権知識の関連コラム
-
債権者保護手続きとは、債権者の利益を保護するための手続きです。主に会社分割や合併など組織再編をする際に、必要になります。通常の債権者保護手続は、官報公告と個別通...
-
事業承継をする上で弁護士に依頼するメリット、弁護士に依頼する前に抑えておきたい事業承継の基礎知識、弁護士に依頼した場合の弁護士費用と事業承継の手順についてまとめ...
-
経営者がどのような目的で他社から買収(m&a)されることを選択するのか、m&aを利用するメリットについてまとめました。
-
加害者死亡後、その家族から損害賠償の相続放棄を告げられ泣き寝入りしかないと諦めていませんか?相続放棄が無効になる3つのパターンや、債権者ができる対抗策があります...
-
事業承継を円滑に行っていくためには、今この瞬間から準備しておくべきことがたくさんありますので、ぜひこの記事をご覧いただき、早めの着手をしていっていただけたらなと...
-
振り込め詐欺に遭ったら、一人で悩まず、すぐにでも専門機関に相談することが重要です。警察や法律事務所、消費生活センターに相談することができます。本記事では、消費生...
-
投資詐欺に遭ってしまったという方は、弁護士に依頼することで返金してもらえるかもしれません。この記事では、投資詐欺の返金を弁護士に依頼するメリット・依頼時の費用・...
-
投資詐欺の被害に遭ってしまった場合は、早期に弁護士へ対応を依頼することで、被害金を回収できる可能性が高まります。投資詐欺に強い弁護士を選ぶ際に注目すべきポイント...
-
2024年から新NISAが始まり、投資に関心を持つ方が増えています。投資を始めたばかりの方は、インターネット上で横行している投資詐欺に騙されないように注意すべき...
-
事業承継を行う上で、後継者の相続時の負担を減らす方法を紹介していきます。
-
投資詐欺の被害に遭ってしまった方は、「どうすればお金を返してもらえるのか」と悩んでいるでしょう。この記事では、投資詐欺の返金を受けるための方法や、そのために準備...
-
債権トラブルを抱えている場合、金銭債権について把握することも大切です。金銭債権は、債権債務関係における金銭の支払い請求権を指します。本記事では、金銭債権について...