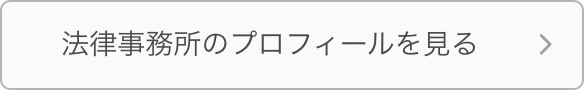事業承継(じぎょうしょうけい)とは、会社の経営権を後継者に引き継ぐことをいいます。『誰に』『どのタイミングで』で事業承継を行うかは非常に重要な問題であり、ここは慎重に決めていく必要があります。
この記事が「自分はどういった形で事業承継を行っていくべきなのか。」、「自分の思いや理念を後継者に引き継いでいくためにはどんな対策をしていくべきなのか。」などについて考えるきっかけになれば幸いです。
事業承継の仕組み

事業承継とは、現経営者から後継者へと経営権を引き継ぐことを指し、『親族内承継』、『親族外承継』、『M&A』という3種類の手法があります。
|
親族内承継 |
経営を『家族』や『親族』の従業員に後継する方法 |
|
親族外承継 |
経営を『親族ではない従業員』に後継する方法 |
|
M&A |
他の会社に経営権を移転・承継させる方法 |
ひと口に事業承継と言っても、その仕組みや内容は異なることが多く、その扱われ方も大きく変わってきました。後述しますが、たとえば過去にはそのほとんどが親族内承継だったのに対し、現在はその半数以上が親族外承継となるなど、事業承継の形も変わってきています。
単に会社を引き継ぐだけではなく、目的をしっかりと持って事業承継の形を選択していくことが大切ですね。
事業承継を行うメリット・デメリット
それではまず、事業承継を行うことのメリットとデメリットを解説していきたいと思います。
メリット
事業承継を行うことによって、廃業を避けることはもちろん、先人の経営者の思いや理念を代々引き継いでいくことができます。
一から会社を興すわけではなく、経営方針や事業内容も定まっていますので、後継者にとってもスムーズな引き継ぎを行うことができますね。事業承継には『親族内承継』、『親族外承継』、『M&A』があり、メリットもそれぞれ存在します。
どの承継においても、会社を廃業させることなく代々引き継いでいけるということは、やはり大きなメリットといえるでしょう。
デメリット
その反面、事業承継をすることのデメリットにはどういったものがあるのでしょうか? デメリットというよりも、事業承継をする際の注意点ともいえるのですが、後継者を選ぶのはそう簡単ではないということが挙げられます。
後継者を親族内から選んでも経営者としての素質があるとは限りませんし、親族外であれば会社内の理解を得にくいというリスクも出てきます。
円満な事業承継、また会社のさらなる発展のために後継者を選任していくために、しっかりと早めに準備していきたいところです。
事業承継の3つのパターン
それでは、事業承継の3つのパターンについて、それぞれ解説していきます。
親族内承継
メリット
親族内承継とはその名の通り、息子などの親族を後継者として選任することです。メリットとしては、社長の親族ということで、社内でも受け入れやすかったり、取引先ともこれまでと変わらない付き合いが期待できることが挙げられます。
自身の子供に引き継ぐことは社長にとっても喜ばしいことですし、経営方針もしっかりと引き継いでくれることが期待されます。
デメリット
その一方、息子を後継者としようと決めていたとしても、そもそも本人にその気がなかったり、経営者としての素質が備わっていなかったりといった状況も起こり得ます。
「息子に継がせるから安心。」という気持ちでいると、いざというときに承継がうまくいかないこともあります。そうならないためにも、早くから子供の意思を確認した上で経営者としての素質を見極めていくことが大切でしょう。
親族外承継
メリット
親族外承継とは、社内で働く親族以外の従業員を後継者とすることです。親族内継承がうまくいかなかった場合にも、会社内から幅広く選任することができます。
社内で長期間働いている人であれば、会社の実情をよく知っていること、会社内外からの理解を得やすいことも大きなメリットですね。
デメリット
一方デメリットとしては、現経営者からの株式を買うための資金力がないということ、後継者の社会的信用が欠けるということが挙げられます。
資金不足により経営が傾いてしまう恐れもありますので、ここはしっかりと対策をとっておきたいところです。
M&A
メリット
M&Aとは、他の会社と合併、もしくは買収されることを指します。M&Aによって、“親族内に後継者がいない”、“後継者に資金力がない”といった理由で後継者が見つからないケースでも、M&Aによって会社を存続さていくことができます。
この図からもわかるように、

引用元:中小企業庁「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会(第1回)
過去は親族内承継が85%、親族外承継が15%という比率でしたが、最近では親族内承継が35%、親族外承継が65%と、その比率が大幅に逆転していることがわかります。
後継者不足が深刻化している現代において、M&Aでの事業承継は多くの会社に取り入れられているとても便利な制度といえるでしょう。
事業承継の際に気をつけること
事業承継を行う際、気をつけていかなければいけないことにどういったものがあるのでしょうか?
ここでは2つに分け、解説していきたいと思います。
あらかじめ後継者の教育をしておく
親族内から後継者を選ぼうとするのであれば、あらかじめ、そして早めにその教育を施していくことが大切になってきます。経営者としての素質は一朝一夕で身につくものではなく、長い時間をかけて培われていくものです。
「息子だから」と安心し、自分が退いてからすぐに経営を任せたとしても、能力不足が原因で会社が傾いてしまうことにもなりかねません。
社内の従業員でも同様ですが、早めに経営者としての教育をし、いざ事業承継をするとなったときには安心して引き継ぐことができるよう準備をしておきたいところです。
社内の理解や協力を得る
親族だからという理由だけで経営権を譲ってしまったとしたら、社内の反感を買うことにもなりかねません。どういった理由で息子を後継者とするのか、これからどういった経営方針で発展させていくのかなどを社内にしっかりと提示することが大切です。
また、親族外承継やM&A承継を行う場合でも、やはり他の社員の理解を得るためにしっかりと報告やコミュニケーションをとっておきましょう。いざ事業承継をするとなった際にまったく協力を得られなかったり、反感を買ってしまったとしたら、その後の企業経営がうまくいくとは思えません。
このことは事業承継の際に限らず普段から心がけていきたいところですね。
事業承継の成功のためにできること
先代が築き上げてきたその業績を後継者が引き継いでいくことは、簡単なことではありません。それは親族内承継でも親族外承継でも同じであり、長い年月をかけた教育が必要です。
ここでは先代の思いや理念を引き継ぎ、これまでの経営をさらに発展させていくために必要なことについて、解説していきます。
後継者育成に早めに着手する
後継者の育成には早めに着手するようにしましょう。
いざというときに会社を継ぐ気がなかったと言われたり、経営者としての素質のなさが浮き彫りになったりするケースも考えられます。
今は元気でバリバリ働けたとしても、いずれ経営を退くときは必ずやってきます。そのときを見据えて今から準備をしておくことがとても大切です。
専門家のサポートを受ける
事業承継を成功させるために最も最適なのは、やはり専門家のサポートを受けることでしょう。
事業承継を成功させるためには、少なくとも5年から10年ほどの準備期間が必要だといわれています。
その間、専門的な知識のないまま時間を消費していくよりも、専門家の相談を受けながら正しい道筋に沿って進んでいくほうが圧倒的に効率的です。
「自分でやらなければ。」という固定概念は捨て、専門家の力に頼ることが、成功への一番の近道となります。
現経営者と後継者の信頼関係を築く
いくら会社を引き継いでほしいと思う人がいたとしても、現経営者とその後継者に信頼関係がない場合、それを受け入れてくれるとは思えません。
会社を引き継ぐということは単に経営権を渡すということではなく、経営方針や理念をも引き継ぐということですから、そこに信頼関係がなければ承継を成功させることは難しいでしょう。
事業承継は一朝一夕でできることではなく、長い年月をかけて考えていくもの。普段からコミュニケーションを密にとり、信頼関係の構築に励む必要があります。
これは親族内であれ親族外であれ、どちらにしても非常に大切なことですね。
事業承継を専門家に相談する場合
事業承継を相談する場合、よく選ばれている専門家とはどういった方なのでしょうか?
中小企業調査室が平成29年4月に発表した「2017年版中小企業白書 概要」によると、その相談役として一番選ばれているのは、会社内の顧問公認会計士や税理士であるということがわかりました。
会計士や税理士は、いわば事業承継のプロであり、資産の有効活用などお金にまつわる相談相手としても最適といえるでしょう。
この調査によると、59.1%という半数以上の方が会計士や税理士と答えていることから、その信頼性は非常に高いことがわかります。
また、行政書士も事業承継の相談相手としてとても適しています。
資金調達やM&Aの仲介、書類の作成などをサポートしてくれるので、自分ひとりでは難しい部分まで手を差し伸べてくれるでしょう。
2017年版中小企業白書 概要には、会計士や税理士に次いで『親や友人、知人』が続いています。
親族内継承をするのであれば、やはり身内や気心の知れた人に相談するというのはとても理にかなっていると思います。
しかし、やはりそれだけでは不十分で、第三者からの客観的なアドバイスを受けることがとても大事です。
親しい間柄だと心情が邪魔をして適切な判断を下せないということにもなりかねません。
円満な事業承継を行っていくために、税理士や会計士、または行政書士などに相談することも検討してみましょう。
まとめ

今回は事業承継について、そのメリットやデメリット、また成功させるためにやっていくべきことについて解説してきました。
廃業をしない限り、事業を誰かに承継する時期は必ずやってきます。
そのときのために今から準備しておくことはたくさんありますし、早めに対策に着手することがとても大切です。
事業承継の形はさまざまありますが、自身の会社はどの方法に最も適しているのか、今からそれをしっかりと考えていきましょう。
また、その際は1人で悩むことはなく、こちらの記事で紹介したように税理士や会計士への相談も視野に入れ、効率よく手続きを進めていきましょう。

【着手金0円プラン有】【休日対応可】【初回面談無料】貸金や売掛金の回収など、実績多数!50万円以上の返済がされずにお困りの方も、一度ご相談ください。証拠集めからサポートし、粘り強く交渉します。
事務所詳細を見る
【初回面談無料】◆訴訟経験豊富な弁護士が企業/個人事業主/個人間紛争まで迅速・徹底サポート◆行政機関勤務経験有◆提案型コミュニケーション◆具体的な回収プランを分かり易くご説明いたします◆【経歴・実績は写真をクリック】
事務所詳細を見る
◆顧問契約のご案内も可◆企業の未収金回収・継続的なサポート◆倒産手続等の経験を活かし費用対効果も含めてご提案致します。◆ご相談はすべて面談形式で丁寧に対応!◆まずは写真をクリックしてご予約方法をご覧下さい。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

その他の債権知識に関する新着コラム
-
本記事では、債権について理解したい方に向けて、債権に関する一覧表、発生原因別・目的別の債権の種類、種類ごとの債権のルールや特徴、債権がもっている主な効力などにつ...
-
ロマンス詐欺は解決が難しい事件です。被害回復できる事案が限られるため、信頼できる弁護士への相談が大切といえるでしょう。中には着手金をだまし取るような行為をして二...
-
債権トラブルを抱えている場合、金銭債権について把握することも大切です。金銭債権は、債権債務関係における金銭の支払い請求権を指します。本記事では、金銭債権について...
-
お金を振り込んでから、振り込め詐欺に遭ったことに気づいたとしても諦めることはありません。振り込め詐欺救済法に従って手続きをすれば返金してもらえる可能性があるから...
-
結婚詐欺の被害は弁護士に相談、依頼することで、被害金を取り戻せたり、加害者の逮捕につなげられたりする可能性があります。本記事では、弁護士に相談できる窓口を紹介す...
-
インターネット上の詐欺被害に遭ってしまい、どこに相談したらよいのかもわからず、ひとりで悩んでいる方は多いのではないでしょうか。本記事では、詐欺被害の相談先や上手...
-
本記事では、LINEで詐欺被害に遭ってしまった場合の相談窓口を紹介します。 すでに被害に遭ってしまった場合はもちろん、疑わしいLINEグループに入れられ、個人...
-
振り込め詐欺に遭ったら、一人で悩まず、すぐにでも専門機関に相談することが重要です。警察や法律事務所、消費生活センターに相談することができます。本記事では、消費生...
-
2024年から新NISAが始まり、投資に関心を持つ方が増えています。投資を始めたばかりの方は、インターネット上で横行している投資詐欺に騙されないように注意すべき...
-
スマートフォン(スマホ)利用者をターゲットにした、いわゆる「スマホ詐欺」が横行しています。フィッシング詐欺もスマホ詐欺の一種です。本記事では、スマホ詐欺の代表的...
その他の債権知識に関する人気コラム
-
債権と債務の違いをわかりやすく図解します。相続・相殺・双務契約などの状況別に債権と債務の関係性をお伝えします。個人・法人に関わらず、まずは債権債務の理解を深めて...
-
債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...
-
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
-
今回の記事では、債権者代位権における、行使することで生じる効果、利用要件、またどのようなシチュエーションで行使されるのかについてまとめました。
-
債権者にとって債権者破産はどのようなメリットがあるのでしょうか。今回の記事では債権者破産がどのような目的で行われるのか、申立方法や申立要件など債権者破産について...
-
債権者保護手続きとは、債権者の利益を保護するための手続きです。主に会社分割や合併など組織再編をする際に、必要になります。通常の債権者保護手続は、官報公告と個別通...
-
投資詐欺の被害に遭ってしまった方は、「どうすればお金を返してもらえるのか」と悩んでいるでしょう。この記事では、投資詐欺の返金を受けるための方法や、そのために準備...
-
今回の記事では顧問弁護士を利用する上で発生する各費用の相場、費用に対して請け負ってもらえる仕事内容についてまとめました。
-
個人の方が顧問弁護士を利用するメリットはどこにあるのでしょうか。今回の記事では顧問弁護士を個人の方が利用するメリットや事例、顧問弁護士を利用する上での注意点につ...
-
今回の記事では、実際に債権者破産の申立をする上で、必要な申立方法や申立書類の作成方法、申立費用について解説していきます。
その他の債権知識の関連コラム
-
事業承継を行う上で、後継者の相続時の負担を減らす方法を紹介していきます。
-
今回の記事では顧問弁護士を利用するメリットとデメリット、それを踏まえた上で顧問弁護士を選ぶ上で確認しておきたいポイントについてまとめてみました。
-
事業承継をする上で弁護士に依頼するメリット、弁護士に依頼する前に抑えておきたい事業承継の基礎知識、弁護士に依頼した場合の弁護士費用と事業承継の手順についてまとめ...
-
今回の記事では、債権者と債務者について理解するために、例をとって解説していきますが、債権回収を希望されている債権者の方にとっても、債権者と債務者の関係性を知る事...
-
お金を振り込んでから、振り込め詐欺に遭ったことに気づいたとしても諦めることはありません。振り込め詐欺救済法に従って手続きをすれば返金してもらえる可能性があるから...
-
投資詐欺の被害に遭ってしまった場合は、早期に弁護士へ対応を依頼することで、被害金を回収できる可能性が高まります。投資詐欺に強い弁護士を選ぶ際に注目すべきポイント...
-
債権トラブルを抱えている場合、金銭債権について把握することも大切です。金銭債権は、債権債務関係における金銭の支払い請求権を指します。本記事では、金銭債権について...
-
持株会社を使うことによってよりスムーズに、事業承継をすることが可能になってきます。 今回は、持株会社を設立して事業承継をする方法やメリットについて、解...
-
弁護士が、英語ができることで、特に債権回収という分野においてどのような利益をもたらしてくれるのでしょうか?
-
2024年から新NISAが始まり、投資に関心を持つ方が増えています。投資を始めたばかりの方は、インターネット上で横行している投資詐欺に騙されないように注意すべき...
-
事業承継を考えている経営者へ向けて、株式評価額の算出方法から、評価額を下げる方法について紹介していきます。
-
現在、まだ改正された法律の施行はされていませんが、今回の記事では債権者主義の解説、またどのような法改正がなされたのか、債権者主義が成立しそうな状況になった場合の...